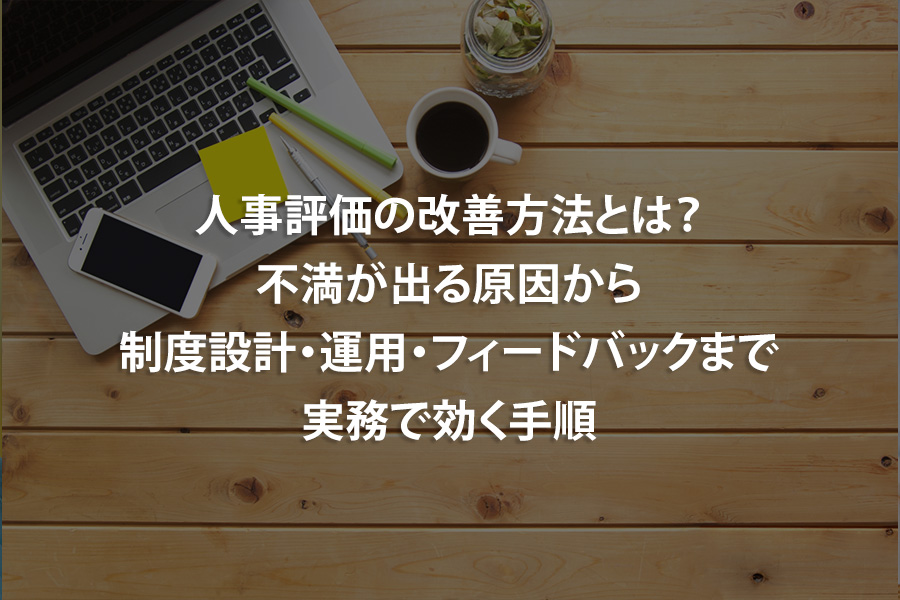
「頑張っているのに評価されない」「基準が分からない」「上司によって評価が違う」——人事評価への不満は、モチベーション低下や生産性の悪化、離職につながりやすい重大なサインです。多くの企業で評価は“賞与や昇進を決める仕組み”として受け止められがちですが、本来は組織目標の達成と人材育成を前進させるためのマネジメント手段でもあります。そこで本記事では、評価が「最悪」と思われる典型原因を分解し、制度そのもの(設計)と日々の運用(面談・フィードバック・評価者のすり合わせ)をセットで改善する実務手順を整理します。現場が明日から動けるチェックポイントまで落とし込み、“納得感のある評価”へ立て直す道筋を示します。
人事評価を改善すべきサイン|不満が増えると起きる4つのリスク
やる気低下→生産性悪化→成果が出ない「悪循環」
人事評価への不満が放置されると、まず起きやすいのが「頑張っても報われない」という感覚です。評価基準が不明確だったり、結果だけを見て過程が評価されなかったりすると、従業員は挑戦を避け、必要最低限の行動に収束しやすくなります。
その結果、個人の行動量・改善提案・協働が減り、チーム全体の生産性が落ちます。生産性が落ちると成果も出にくくなり、さらに評価への不満が強まる——という悪循環に陥ります。評価制度の改善は「やる気を上げる施策」ではなく、組織の成果を守るためのリスクマネジメントでもあります。
離職・採用コスト増:優秀層ほど去りやすい理由
評価に納得できない状態が続くと、「この会社では成長しても報われない」「公平に扱われない」という認識が広がり、離職の引き金になります。特に優秀な人ほど、転職市場で選択肢が多く、より納得感のある評価環境を求めて早期に離れてしまいがちです。
離職が増えると、採用・育成のコストが上がるだけでなく、引き継ぎや教育で現場負担が増え、残ったメンバーの疲弊にもつながります。評価改善は、採用広報や福利厚生よりも“効き目の大きい定着施策”になり得ます。
組織の信頼が崩れる:マネジメント不全と風土悪化
評価は「会社が従業員をどう見ているか」を示すメッセージです。評価に一貫性がなく、上司の主観が強く出たり、説明やフィードバックが不足したりすると、従業員は上司や会社への信頼を失い、組織の心理的安全性が下がります。
信頼が崩れると、相談や報連相が減り、課題が表面化しづらくなります。すると、ミスの再発や部門間対立、責任の押し付け合いなどが起こり、風土が悪化します。評価制度の改善は、管理職のマネジメントを補強し、健全な組織文化を維持するための土台です。
不服申立て・法的リスク(“属性”を基準にしない重要性)
評価が不透明で、理由説明ができない状態は、不服申立て(評価への異議)を招きやすくなります。社内の不満が表面化すると、個別対応に時間を取られ、現場も人事も消耗します。さらに、評価基準や処遇の決定において、職務遂行能力と関係の薄い「属性(例:家庭状況、年齢、性別など)」が影響していると疑われると、法的リスクや企業イメージへの影響も無視できません。
重要なのは、誰が見ても説明できる「職務・役割・行動」に基づく評価基準を整え、評価の根拠(事実・行動記録・面談内容)を残しておくことです。これにより、不服申立ての予防だけでなく、万一の際にも組織として説明責任を果たしやすくなります。
人事評価の不満はなぜ起きる?原因を3つに分解すると改善が速い
人事評価に対する不満は、「評価が低いから」「昇給しないから」といった結果面だけが原因ではありません。多くの場合、不満の背景には構造的なズレが存在します。ここでは、人事評価の不満を3つの原因に分解し、それぞれを整理することで、改善をスムーズに進める考え方を解説します。
原因①:評価制度の理解不足(目的・用語・流れが伝わっていない)
人事評価制度そのものが、従業員や評価者に十分理解されていないケースは少なくありません。「人事評価は何のために行うのか」「どのような観点で評価されるのか」「評価結果はどのように活用されるのか」といった基本情報が共有されていないと、不信感や誤解が生じやすくなります。
特に多いのが、「評価=賞与や昇進を決めるもの」という認識だけが先行し、本来の目的である人材育成や目標達成との関係が伝わっていない状態です。この場合、評価のフィードバックも形式的になりやすく、従業員は評価を前向きに受け止められません。制度の目的・用語・評価の流れを、定期的に説明し直すことが改善の第一歩となります。
原因②:評価者による基準の相違(“甘辛”が揃わない)
評価者ごとに基準の解釈が異なると、「上司によって評価が違う」「あの部署は評価が甘い」といった不満が生まれます。評価基準自体は存在していても、「どの行動がどの評価に該当するのか」が具体化されていなければ、評価者の経験や価値観に左右されてしまいます。
この状態では、評価される側が努力の方向性を見失い、「どう頑張れば評価されるのか分からない」と感じやすくなります。改善には、評価基準を行動レベルまで落とし込み、評価者間で事例をもとにすり合わせを行うことが重要です。評価の“甘辛”をなくすことで、制度全体の納得感が高まります。
原因③:評価者と被評価者のレベル感のずれ(期待値が合っていない)
上司が期待している水準と、部下が「できている」と考えている水準が一致していない場合、評価結果に対する不満が生じます。評価者は「まだ足りない」と感じていても、被評価者は「十分にやっている」と思っているケースは珍しくありません。
このズレは、期末になって初めて明らかになることが多く、「なぜもっと早く言ってくれなかったのか」という不満につながります。期初・期中・期末に面談を行い、期待される役割や到達レベルをすり合わせておくことで、評価結果への納得度は大きく改善します。
「上司側/部下側」不満を、改善課題に翻訳するコツ
人事評価に関する不満は、上司側・部下側の双方に存在します。上司は「成果が誇張されている」「改善意欲が見えない」と感じ、部下は「頑張っても評価されない」「基準が分からない」と感じがちです。
重要なのは、これらの不満を感情論として捉えるのではなく、「どの仕組みが機能していないのか」という改善課題に翻訳することです。例えば、「評価基準が分からない」という声は制度理解不足や基準の不明確さ、「上司によって評価が違う」という声は評価者間のすり合わせ不足を示しています。不満の声を整理し、構造的な原因に落とし込むことで、具体的かつ効果的な改善策を打ちやすくなります。
“最悪”と思われる評価制度の特徴7つ|改善の優先順位が分かるチェックリスト
人事評価制度への不満は、感情論ではなく「制度や運用の欠陥」が原因で生じることがほとんどです。ここでは、従業員から「最悪」と思われやすい評価制度の特徴を7つに整理します。自社の制度がどこに当てはまるかを確認することで、改善の優先順位が見えてきます。
評価基準があいまい/不透明(まず言語化・定義)
評価基準があいまい、あるいは従業員に十分開示されていない場合、「何を頑張れば評価されるのか分からない」という不満が生まれます。特に、数値化しにくい業務やチーム貢献が多い職種では、この傾向が顕著です。
改善の第一歩は、評価項目を言語化し、「どのような行動・成果が、どの評価につながるのか」を定義することです。基準を明確にすることで、評価の納得感と行動の再現性が高まります。
主観・先入観が入りやすい(評価誤差が起きる場面)
評価者の主観や先入観が強く影響すると、評価にばらつきが生じます。例えば、「印象が良い」「コミュニケーションが活発そう」といった曖昧な印象が、実際の行動や成果以上に評価へ影響するケースです。
こうした評価誤差を防ぐには、評価基準を行動レベルまで落とし込み、事実や記録に基づいて判断する仕組みが必要です。評価者研修や評価者間のすり合わせも有効な対策となります。
成果だけ・年功だけに偏る(役割・プロセスが落ちる)
成果のみを重視する評価や、年功序列を優先する評価は、どちらも不満を招きやすい制度です。成果主義が強すぎると、プロセスや挑戦が評価されず、短期的な成果だけを狙う行動が増えます。
一方、年功序列が優先されると、若手や中堅の成長意欲が低下します。成果・役割・プロセスをバランスよく評価することで、育成とパフォーマンスの両立が可能になります。
指標が現場実態と乖離(古い目標、達成不能KPI)
評価指標が長年見直されておらず、現場の実態と合っていない場合、従業員は「評価のための仕事」をするようになります。達成不能なKPIや、業務内容と無関係な指標は、モチベーション低下の原因です。
評価指標は、定期的に現場の声を取り入れながら見直し、業務実態と成果につながる内容に更新する必要があります。
フィードバックがない/説明不足(納得感が消える)
評価結果だけが伝えられ、理由や改善点の説明がない場合、従業員は評価を「一方的な通知」と感じます。これでは、人事評価が人材育成につながりません。
評価面談では、「どの行動が評価されたのか」「何が課題だったのか」を具体的に伝えることが重要です。フィードバックは、評価制度を機能させるための中核です。
評価が処遇に結びつかない(テーブル設計・運用の問題)
評価制度が存在していても、昇給・昇格・賞与などの処遇に反映されない場合、評価そのものの信頼性が低下します。「評価されても意味がない」と感じれば、従業員の行動は変わりません。
評価結果がどのように処遇へ反映されるのかを明示し、制度と運用の両面で一貫性を持たせることが不可欠です。
他者比較に見える運用(情報共有の扱い、伝え方)
評価結果の伝え方や情報共有の方法によっては、「他人と比べられている」と感じさせてしまうことがあります。相対評価が前面に出ると、協力よりも競争が強まり、組織の一体感が損なわれます。
評価はあくまで「本人の役割・行動・成果」に基づいて説明し、比較ではなく成長に焦点を当てることが重要です。プロセス評価や面談の目的を明確にすることで、評価制度を人材育成に寄与する仕組みへと転換できます。
人事評価の改善は「制度設計×運用」で決まる|まず目的を“人材育成”として再定義する
人事評価を改善しようとすると、「評価シートを変える」「評価項目を増やす」といった制度設計の見直しに目が向きがちです。しかし、実際には制度だけを整えても、運用が伴わなければ不満は解消されません。人事評価を機能させるためには、「制度設計」と「日々の運用」をセットで見直し、評価の目的を人材育成の視点から再定義することが重要です。
目的の再設定:評価=処遇だけにしない(育成・配置・目標達成)
多くの従業員は、人事評価を「昇給・賞与・昇格を決める仕組み」と捉えています。この認識自体が間違いではありませんが、処遇決定だけを目的にすると、評価はどうしても結果重視・短期視点になりがちです。
本来の人事評価は、従業員の強みや課題を明らかにし、育成や適正配置、組織目標の達成につなげるためのツールです。評価の目的を「人材育成」と明確に再設定し、その考え方を社内で共有することで、評価への受け止め方や面談の質も大きく変わります。
等級・評価・報酬のつながりを点検(ズレが不満を生む)
等級制度、評価制度、報酬制度は、本来一体で設計されるべきものです。しかし実務では、「評価は高いのに昇給しない」「等級が上がっても役割が変わらない」といったズレが起きやすく、これが従業員の不満につながります。
改善にあたっては、各等級で期待される役割・行動と評価基準、そして報酬テーブルが論理的につながっているかを点検しましょう。この整合性が取れていない限り、どれだけ評価運用を工夫しても納得感は高まりません。
透明性の設計:どこまで開示するか(不満を増やさない開示の仕方)
評価の透明性を高めることは重要ですが、「すべてを公開すればよい」というわけではありません。評価基準や評価プロセスが不十分な状態で詳細を開示すると、かえって不満が増えることもあります。
まずは、評価の目的、評価項目の考え方、評価結果がどのように処遇へ反映されるのかといった“骨子”を丁寧に説明することが大切です。そのうえで、具体的な基準や事例を段階的に共有することで、納得感を高めながら透明性を確保できます。
「面談」「自己申告」「基準公開」の役割を揃える(運用の骨格)
人事評価の運用は、「面談」「自己申告」「評価基準の公開」がバラバラに機能していると、制度全体が形骸化します。例えば、自己申告が形式的になっていたり、面談が評価結果の通達だけで終わっていたりするケースです。
これらはそれぞれ役割が異なります。自己申告は本人の振り返りと課題整理、面談は期待値のすり合わせと育成支援、基準公開は行動の指針を示す役割を担います。役割を揃えて運用することで、人事評価は初めて「人を育てる仕組み」として機能します。
改善方法①:評価基準を“行動レベル”に落とし込む(ばらつきを減らす)
人事評価のばらつきや不満の多くは、「評価基準が抽象的なまま運用されている」ことに起因します。成果や能力といった言葉だけでは、評価者ごとの解釈差が生まれやすく、公平性を保つのは困難です。そこで重要になるのが、評価基準を“行動レベル”まで具体化することです。ここでは、評価のばらつきを減らすための実践的な考え方を解説します。
まず職種・役割で評価軸を分ける(数字が出にくい部門の救い方)
評価基準を設計する際にありがちな失敗が、全職種に同じ評価軸を当てはめてしまうことです。営業職のように成果が数字で表れやすい職種と、バックオフィスや企画職のように成果が見えにくい職種では、適切な評価軸は異なります。
まずは職種や役割ごとに、「何を期待するポジションなのか」を整理し、その役割に即した評価軸を設定しましょう。数字が出にくい部門では、業務プロセスの質、周囲への影響、改善提案などを評価項目に含めることで、不公平感を抑えやすくなります。
良い評価基準の条件:具体性/観察可能性/再現性
評価基準を行動レベルに落とし込む際は、「具体性」「観察可能性」「再現性」の3点を意識することが重要です。
例えば、「主体性がある」という表現ではなく、「会議で自ら課題提起を行い、改善案を提示している」といった形にすると、評価者が実際の行動を観察しやすくなります。また、誰が評価しても同じ判断に近づくよう、解釈の余地をできるだけ減らすことがポイントです。
このような基準は、従業員にとっても「何をすれば評価されるのか」が分かりやすく、行動改善につながりやすくなります。
評価者間のすり合わせ(ワークショップ例:同じ行動を何点にする?)
評価基準を整備しても、評価者間で解釈が揃っていなければ、評価のばらつきは解消されません。そのため、評価者同士のすり合わせが欠かせません。
効果的なのが、具体的な行動事例を用いたワークショップです。例えば、「この行動を取った場合、評価は何点になるか」を評価者同士で話し合い、判断理由を共有します。このプロセスを通じて、評価の甘辛や判断基準が徐々に揃っていきます。
評価誤差(ハロー効果など)を前提に、運用で補正する考え方
人が評価する以上、ハロー効果(一部の印象が全体評価に影響する)や直近効果(最近の出来事に引きずられる)などの評価誤差を完全に排除することはできません。
そのため重要なのは、「評価誤差は起きるもの」と前提に立ち、運用で補正する仕組みを用意することです。複数回の面談で行動を記録する、評価会議で判断理由を共有するなどの工夫により、主観に偏らない評価に近づけることができます。
改善方法②:期初・期中・期末の面談とフィードバックで“納得感”を作る
人事評価への不満を減らすうえで欠かせないのが、面談とフィードバックの質です。評価結果だけを伝えるのではなく、期初・期中・期末の面談を通じて期待値と事実をすり合わせていくことで、評価への納得感は大きく高まります。ここでは、それぞれのタイミングで押さえるべきポイントを整理します。
期初:目標と役割の合意(上司→部下ではなく「部下から話す」工夫)
期初面談の目的は、「その期間に何を期待されているのか」を明確にし、上司と部下の認識を揃えることです。このとき、上司が一方的に目標を提示するのではなく、まず部下自身に目標や取り組みたい役割を語ってもらうことが重要です。
部下から話してもらうことで、本人の理解度や意欲、現状認識が見えやすくなります。そのうえで上司が期待値や優先順位を補足し、合意形成を行うことで、期末の評価に対する納得感が高まりやすくなります。
期中:進捗確認と支援(行動記録・事実ベースで会話する)
期中面談は、評価のためというよりも「軌道修正と支援」の場です。ここで重要なのは、成果の良し悪しだけで判断せず、行動やプロセスに目を向けることです。
日々の業務での行動記録や具体的な事実をもとに、「どの行動がうまくいっているか」「どこでつまずいているか」を整理し、必要な支援や助言を行います。期中に対話を重ねておくことで、期末評価が突然のものにならず、評価への不満を防ぎやすくなります。
期末:評価理由を言語化(どの行動が基準を満たしたか/課題は何か)
期末面談では、評価結果そのもの以上に「なぜその評価になったのか」を丁寧に伝えることが重要です。評価基準に照らし、「どの行動が基準を満たしていたのか」「どの点に課題が残ったのか」を具体的に言語化しましょう。
この説明が曖昧だと、評価が正しくても納得感は得られません。事実と行動をもとに説明することで、従業員は評価を次の成長につなげやすくなります。
面談の“目的”を外さない:能力開発とパフォーマンス向上につなげる
面談が形骸化する原因の多くは、「評価を伝えること」自体が目的になってしまうことです。本来の面談の目的は、従業員の能力開発とパフォーマンス向上にあります。
評価結果を踏まえて、次に伸ばすべき強みや改善点を整理し、具体的な行動目標に落とし込むことが大切です。面談を通じて前向きな行動変容を促せれば、人事評価は単なる査定ではなく、成長を支える仕組みとして機能します。
改善方法③:評価手法の選び方(MBO/OKR/360度/コンピテンシー/バリュー)と向き不向き
人事評価制度の改善では、「どの評価手法を使うか」が成果を大きく左右します。評価手法にはそれぞれ得意・不得意があり、自社の目的や組織フェーズに合わない方法を選ぶと、不満や形骸化を招きます。ここでは代表的な評価手法の特徴と向き不向きを整理します。
MBO:達成率評価の強みと落とし穴(易しい目標に流れる等)
MBO(目標管理制度)は、個人やチームが設定した目標の達成度合いで評価する手法です。目標が明確で、達成率という客観的な指標を用いるため、評価者の主観が入りにくい点が強みです。
一方で、「評価されやすい目標」を意識するあまり、易しい目標設定に流れやすいという落とし穴もあります。また、評価につながらない業務や挑戦的な取り組みが敬遠されやすくなる点には注意が必要です。
OKR:60〜70%達成を前提にした運用の要点(評価と切り離す設計)
OKRは、高い目標(Objectives)と、その達成度を測る指標(Key Results)を設定する手法です。60〜70%の達成でも成功と捉える設計が特徴で、挑戦的な目標設定を促します。
OKRを評価制度と強く結びつけると、失敗を恐れて目標が保守的になるため、評価とは切り離して運用するケースが一般的です。挑戦と学習を促進したい組織に向いています。
360度評価:多面性のメリット/馴れ合い・関係悪化リスク(使い所)
360度評価は、上司・同僚・部下など複数の立場から評価を行う手法です。一人の上司だけでは見えない行動や強みを可視化でき、多面的な評価が可能になります。
一方で、馴れ合いや感情的な評価が入りやすく、人間関係が悪化するリスクもあります。処遇決定ではなく、人材育成や自己理解を目的に使うことで効果を発揮しやすくなります。
コンピテンシー:行動特性で育成につなげる/設計コスト
コンピテンシー評価は、成果ではなく「成果を生み出す行動特性」に着目する評価手法です。どのような行動が高評価につながるのかが明確になるため、育成との相性が良い点が特徴です。
ただし、モデル設計には時間と労力がかかります。自社の成功人材を分析し、現場に合ったモデルを作らなければ、形だけの制度になりやすい点には注意が必要です。
バリュー評価:価値観の浸透と“見えにくい貢献”を拾う
バリュー評価は、企業が大切にする価値観や行動指針を、どの程度体現できているかを評価する方法です。数値では測りにくい貢献や、チームへの影響を評価しやすい点が特徴です。
価値観の浸透や組織文化の形成を重視する企業に向いており、成果評価や目標管理と組み合わせて使われることが多くあります。
「目標管理×行動評価×価値観」をどう組み合わせると失敗しにくいか(実務例)
単一の評価手法ですべてをカバーしようとすると、必ず無理が生じます。実務では、MBOやOKRで目標達成を確認し、コンピテンシーやバリュー評価で行動や姿勢を補完する組み合わせが有効です。
このように複数の視点を組み合わせることで、成果・行動・価値観をバランスよく評価でき、不満や偏りを抑えやすくなります。
データで見る目標管理の課題感(期初/期中/期末の詰まりどころ)
目標管理が機能しない原因は、期末の評価よりも、期初や期中の運用にあることが多いです。期初に目標が曖昧なまま始まり、期中のフォローが不足すると、期末に評価と実態が乖離します。
目標管理を有効に機能させるには、期初の目標合意、期中の進捗確認、期末の振り返りというプロセス全体を通して設計・運用することが不可欠です。
改善を定着させる実行プラン|90日で回す“評価改善サイクル”
人事評価制度の改善は、一度仕組みを変えただけでは定着しません。重要なのは、短いサイクルで検証と修正を繰り返し、「現場で使える形」に磨き上げていくことです。ここでは、約90日を目安に回せる評価改善サイクルを5つのステップで整理します。
ステップ1:現状診断(アンケート・面談・評価分布・不服件数)
最初に行うべきは、評価制度と運用の現状を客観的に把握することです。従業員アンケートや管理職へのヒアリングを通じて、「どこに不満や違和感があるのか」を洗い出します。
あわせて、評価分布(評価が極端に偏っていないか)や、不服申立て・相談件数などの定量データも確認します。感覚論だけでなく、事実に基づいて課題を整理することで、改善の方向性が明確になります。
ステップ2:小さく試す(1部門パイロット→改訂→全社展開)
制度を一気に全社展開すると、想定外の混乱や反発が起こりやすくなります。まずは1部門や一部職種でパイロット運用を行い、実際の運用上の課題を確認しましょう。
現場の声をもとに評価基準や運用ルールを微調整し、改善点を反映させてから全社へ展開することで、失敗リスクを抑えながら定着を図ることができます。
ステップ3:評価者研修(基準理解/面談スキル/フィードバックの型)
評価制度の成否は、評価者の理解とスキルに大きく左右されます。評価基準の解釈が揃っていなければ、どれだけ制度を整えても不満は解消されません。
評価者研修では、評価基準の正しい理解に加え、面談の進め方やフィードバックの伝え方を重点的に扱います。共通の「評価の型」を持たせることで、評価のばらつきを抑えやすくなります。
ステップ4:運用ルール整備(記録、調整会議、説明責任、Q&A整備)
評価改善を定着させるためには、運用ルールの整備が欠かせません。評価の根拠となる行動記録の残し方、評価者同士で判断をすり合わせる調整会議の実施、評価結果を説明する際の基本方針などを明文化します。
あわせて、従業員向けのQ&Aを用意することで、制度への不安や誤解を減らし、現場からの問い合わせ対応もスムーズになります。
ステップ5:法的・倫理的な“地雷”を踏まない(属性で差をつけない等)
評価制度の運用では、法的・倫理的な観点への配慮も不可欠です。職務遂行能力や役割と関係のない属性(年齢、性別、家庭状況など)を評価や処遇判断に反映させることは、大きなリスクを伴います。
評価基準はあくまで職務・行動・成果に基づくものであることを明確にし、判断理由を説明できる状態を保つことが重要です。こうした配慮は、不服申立ての予防だけでなく、企業としての信頼性を守ることにもつながります。
まとめ
人事評価の改善は、評価シートや制度を見直すだけでは十分とは言えません。評価への不満は、「制度の理解不足」「評価基準のばらつき」「期待値のズレ」といった構造的な原因から生まれます。そのため、評価基準を行動レベルまで落とし込み、期初・期中・期末の面談を通じて対話を重ねることが、納得感を高める近道となります。
また、MBOやOKR、360度評価などの評価手法は万能ではなく、目的や組織フェーズに応じて組み合わせることが重要です。成果・行動・価値観をバランスよく評価できる仕組みを設計し、評価者研修や運用ルール整備によって定着させていくことで、人事評価は「不満の原因」から「人材育成と成果創出を支える仕組み」へと変わります。
まずは現状診断から着手し、小さく試しながら改善を回していきましょう。評価制度の設計や運用に悩んでいる場合は、専門家への相談や外部支援を活用することも、有効な選択肢の一つです。





 導入までの流れ
導入までの流れ
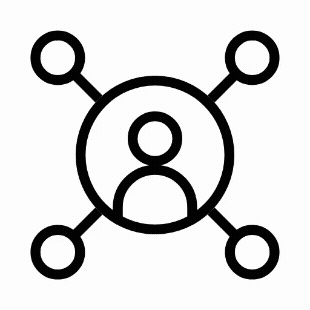
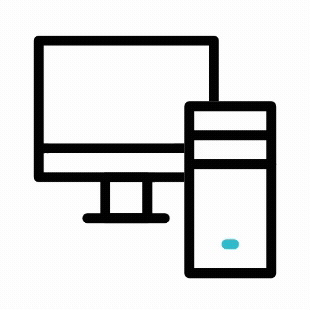

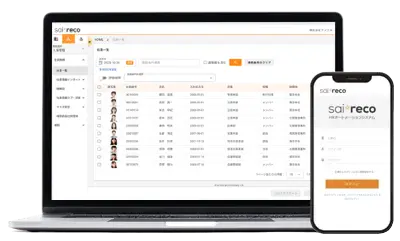



 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求