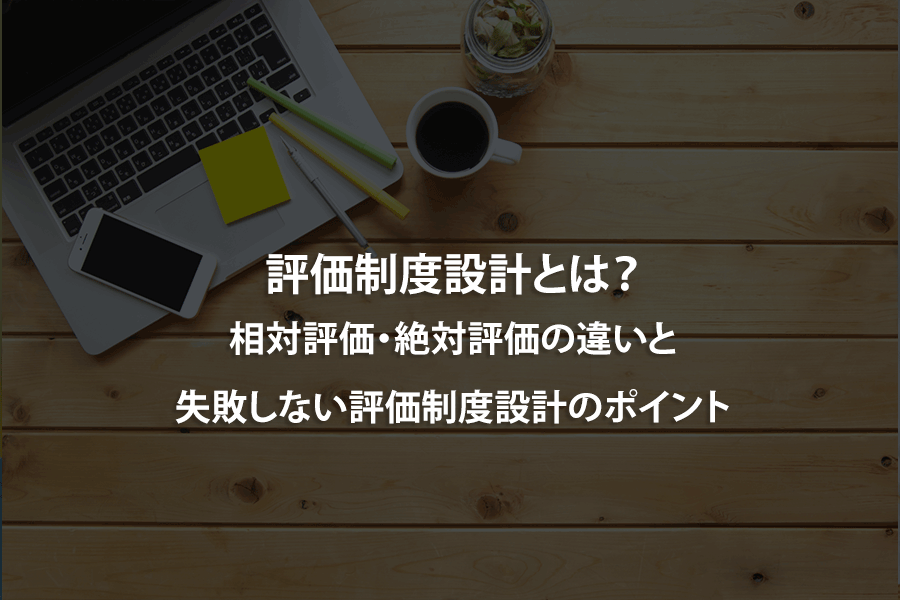
評価制度を新しく設計し直そうとするとき、多くの人事担当者がぶつかるのが「相対評価と絶対評価をどう組み合わせるか」「納得度の高い評価制度をどうつくるか」という問いです。昇給・賞与・昇格に直結する評価制度は、社員のモチベーションや離職率、ひいては業績にも大きく影響します。一方で、評価基準が曖昧だったり、運用負荷が高すぎたりすると、制度そのものが形骸化してしまいかねません。
本記事では、人事評価の基本から、相対評価・絶対評価の違いとメリット・デメリット、さらにそれらを踏まえた評価制度設計のステップまでを体系的に解説します。人事・評価制度の設計・運用に携わってきた専門家の視点から、「現場で本当に使える評価制度」をつくるための考え方と具体的なポイントをお伝えします。
評価制度設計の前提:なぜ今「評価制度の見直し」が必要なのか
評価制度がもたらす影響 ― モチベーション・離職率・人件費・採用競争力
評価制度の設計は、単に昇給・賞与・昇格を決める仕組みづくりではなく、組織全体のパフォーマンスを左右する重要な経営テーマです。 人事評価のあり方次第で、社員のモチベーションやエンゲージメント、離職率、さらには人件費のコントロールや採用競争力まで大きく変わります。 評価基準が曖昧であったり、部署や評価者によってばらつきが大きかったりすると、「どう頑張れば評価されるのか分からない」という不信感が生まれ、 優秀層からの離職や、評価に対する不満の蓄積を招きかねません。
一方で、事業戦略と連動した評価制度設計ができている企業では、「期待される行動・成果」が明確になり、日々の業務と評価が結びつきます。 その結果、社員は評価制度を通じて自分の役割や成長課題を理解でき、キャリアの納得感が高まりやすくなります。 また、評価結果と報酬・等級・育成施策を一貫して運用できれば、人件費を中長期的な投資としてマネジメントしやすくなり、 採用メッセージにも「評価と成長の仕組みが整った会社」としての魅力を打ち出すことができます。 だからこそ、評価制度の設計・見直しは、今の時代の人事・経営にとって避けて通れないテーマといえます。
日本企業の評価制度の変遷(年功序列→相対評価→成果主義・絶対評価)
日本企業の評価制度は、長らく「年功序列・終身雇用」を前提とした仕組みが中心でした。 年齢や在籍年数とともに賃金が上がり、評価制度は昇進・昇格のための補助的な役割にとどまるケースも少なくありませんでした。 しかし、バブル崩壊以降の低成長期を背景に、「限られた人件費をどう配分するか」という観点から、 社内での相対的な優劣にもとづいて評価する相対評価が広く導入されていきます。 あらかじめ評価ランクの割合を決め、分布をコントロールすることで、人件費を予算内に収めやすい点が重視された時期です。
その後、グローバル競争の激化や人材の流動化が進むなかで、「社員一人ひとりの成長や成果に報いるべきだ」という考えが強まり、 目標管理(MBO)やコンピテンシー評価など、個人の到達度を基準とする成果主義・絶対評価が注目されてきました。 とはいえ、絶対評価だけでは人件費の膨張や基準設計の難しさといった課題も表面化し、いまは 「相対評価と絶対評価を組み合わせたハイブリッドな評価制度設計」が主流になりつつあります。 評価制度を設計・見直しする際には、自社がどのステージにいるのか、この変遷の中で自社の位置づけを整理することが重要です。
テレワーク・ジョブ型・人的資本経営時代に求められる評価制度とは
近年は、テレワークやハイブリッドワークの浸透、専門性にもとづくジョブ型雇用へのシフト、 人的資本経営・人的資本開示の義務化など、評価制度を取り巻く環境が大きく変化しています。 出社前提の「見える働きぶり」に依存した人事評価のやり方では、リモート環境で働く社員を公平に評価できません。 また、職務や役割に応じて処遇が決まるジョブ型では、「どのジョブに対して、どのレベルで貢献しているか」を示す評価制度設計が不可欠になります。
さらに、人的資本経営が求められる時代には、評価制度は単なる査定の仕組みではなく、 「人材ポートフォリオをどのように強化していくか」「どの領域にどれだけ投資するか」を示す重要な経営インフラです。 評価データをタレントマネジメントや人材育成計画と連動させ、スキル・経験・ポテンシャルを可視化できる評価制度へとアップデートすることが求められます。 こうした背景を踏まえると、これからの評価制度設計では、相対評価・絶対評価のメリットを活かしつつ、 テレワーク・ジョブ型・人的資本経営に対応した、透明性と納得感の高い仕組みづくりが鍵になります。
評価制度設計の基本構造:等級・評価・報酬の関係を整理する
人事制度の三本柱 ― 等級制度・評価制度・報酬制度
評価制度の設計を考える際には、まず「人事制度の三本柱」を正しく把握することが重要です。 一般的に人事制度は、等級制度・評価制度・報酬制度の3つで構成されており、 これらが連動することで、組織全体の一貫した人材マネジメントが可能になります。
等級制度は、社員の役割・スキルレベル・貢献度を分類し、「どのレベルの人材なのか」を示す基準です。 職能型・役割型・職務型など設計方法は様々ですが、いずれも社員がどの段階にいるかを明確にします。
評価制度は、社員の成果や行動を測定し、「どの程度期待に応えているか」を判断する仕組みです。 評価結果は、等級の維持・昇格、育成施策の立案に直結します。
報酬制度は、評価結果をもとに賃金・賞与・手当などを決める仕組みです。 評価制度と報酬制度の連動度合いをどう設計するかによって、 「評価が給与にどの程度影響するのか」という納得感が大きく左右されます。
この3つがバラバラに運用されると、評価の理由が不透明になったり、 昇給や昇格の基準が分からなくなるなど、社員の不信感につながる恐れがあります。 逆に、三本柱が一貫して設計されている組織では、 社員が「何をすれば評価されるのか」「どのようにキャリアアップできるのか」を理解しやすくなり、 日々の行動や成長への意欲が高まりやすい点が大きな特徴です。
評価制度が担う役割 ― 「能力・成果の見える化」と「処遇決定の根拠」
評価制度が持つ最大の役割は、社員の能力・成果を見える化すること、 そして処遇の根拠を明確にすることです。 評価制度が機能していない組織では、昇給・昇格・賞与が属人的に決まりやすく、 社員のモチベーション低下や不公平感を生みやすくなります。
適切に設計された評価制度では、「期待される成果」「求められる行動」が明確になり、 社員は日々の働き方の優先順位をつけやすくなります。 また、評価結果が昇格や給与に反映される仕組みが整うことで、 処遇に対する納得感が高まり、キャリア形成の方向性も理解しやすくなります。
さらに、評価制度はタレントマネジメントの基盤としても機能します。 評価データは「誰がどのスキルを持っているか」「どの部署にどの能力が足りないか」を把握するための重要な情報源です。 人的資本経営では、スキルの棚卸しや適材適所配置が求められるため、 評価制度の精度は企業競争力にも直結するといえます。
評価項目の基本軸 ― 成果(業績)評価/能力・行動評価/情意・態度評価
評価制度を設計する際は、「何を評価するのか」という評価項目を整理する必要があります。 一般的には、次の3つの基本軸で構成されます。
① 成果(業績)評価
売上・利益・件数・プロジェクト達成度など、「成果として現れた結果」を評価する項目です。 目標管理制度(MBO)などと組み合わせることで測定しやすく、納得感の高い評価につながります。 ただし、職種によっては数値化が難しいケースもあるため、バランスが求められます。
② 能力・行動評価(コンピテンシー評価)
成果に至るプロセスや、職務遂行に必要なスキル・行動を評価します。 例えば「課題発見能力」「コミュニケーション」「リーダーシップ」などが該当します。 成果だけでは見えない成長や貢献を評価できるため、育成に直結しやすいのが特徴です。
③ 情意・態度評価
勤務姿勢・協働性・規律性など、組織で働く上で必要な態度を評価します。 現代では過度に重視されるべきではないものの、最低限の働き方の基準として設定されるケースが一般的です。
これらの3つの評価軸を「職種・役割・等級」に応じて適切に組み合わせることで、 評価の公平性・精度・納得感を高めることができます。 評価項目が曖昧なまま運用を始めると、評価者による判断のばらつきが増え、 制度そのものが形骸化してしまうため注意が必要です。
相対評価と絶対評価の違いとは?評価制度設計の前提知識
相対評価とは ― 集団内での相対的な位置づけで評価する方法
相対評価(ノーマティブ評価)とは、社員を「集団の中でどの位置にいるか」という観点で評価する方法です。 個人の成果そのものよりも、同じ部署・同じ等級の社員の中で相対的にどれくらい優れているかを比較し、 評価ランクを決める仕組みである点が特徴です。学校の成績評価(偏差値・順位)と考えると理解しやすい評価方法です。
■ 集団準拠型評価の考え方
相対評価は「集団準拠型」と呼ばれ、評価の基準が個人ではなく「集団」にあります。 そのため、個人の頑張りや成長が評価に反映されにくい一方、 評価の分布が明確に管理できるため、人件費のコントロールがしやすいというメリットがあります。
■ 学校・企業での具体例(評価ランクの割合設定など)
企業で代表的なのは、あらかじめ評価ランクごとの割合(分布)を設定する方法です。
- A評価:10%
- B評価:60%
- C評価:25%
- D評価:5%
このように分布を決めておくことで、評価の甘辛調整がしやすく、 部署による評価の偏りを防ぎやすい仕組みになります。 一方で、どれだけ成果を出しても「上司より成果が低いからAが取れない」などの不満が生じる可能性もあるため、 相対評価を導入する際は説明責任(透明性)が重要となります。
絶対評価とは ― 目標や基準への到達度で評価する方法
絶対評価(基準準拠型評価)とは、あらかじめ設定された目標や基準に対して、どれだけ達成したかを評価する方法です。 集団の中での順位ではなく、「目標に到達したかどうか」という絶対的な判断基準を用いる点が特徴です。 教育現場では、学習到達度評価として一般的に用いられてきました。
■ 到達度評価・目標管理(MBO)との関係
企業では、MBO(目標管理制度)と非常に相性が良く、 「期初に設定した目標に対して、期末にどれだけ達成したか」を中心に評価が行われます。 成果指標だけではなく、取り組み姿勢やプロセスを評価に入れることで、 社員の成長を促す評価制度として導入されるケースが増えています。
■ 教育現場・企業での活用例
教育現場では、定期テストで「80点以上はA」「70〜79点はB」といった基準が設定されます。 企業の場合は以下のような活用例があります。
- 営業:目標達成率80%でB、120%でAなどの具体的基準を設定
- 事務・バックオフィス:期限遵守率、品質指標、業務改善数などの目標を設定
- 管理職:チームの成果、育成状況、組織運営の指標を基準化
絶対評価は個人の成長や努力が反映されやすい半面、評価基準の作り込みが不十分だと 「評価者によって判断がブレる」「いつも平均的な評価になる」といった課題が発生します。 評価制度設計では、基準の明確化と評価者教育が非常に重要です。
比較表で整理する「相対評価」と「絶対評価」の違い
相対評価と絶対評価はどちらか一方が優れているわけではなく、 組織の目的や人件費方針、職種の特性によって使い分ける必要があります。 以下に違いを分かりやすく表でまとめます。
| 項目 | 相対評価 | 絶対評価 |
|---|---|---|
| 定義 | 集団内での順位にもとづき評価 | 基準・目標への到達度で評価 |
| 基準 | 集団(部署・等級)の中での比較 | 個人の目標・評価基準 |
| メリット | ・人件費管理が容易 ・評価分布が調整しやすい ・評価のバラつきを抑制 | ・成長や努力が反映されやすい ・納得感を得やすい ・多様な働き方に対応しやすい |
| デメリット | ・不公平感が生まれやすい ・個人の成長を評価しにくい ・部署間での評価差が出やすい | ・基準作成が難しい ・評価が甘くなると差がつかない ・人件費が膨張する可能性 |
| 向いている場面 | ・大規模組織 ・人件費管理を重視したいケース | ・専門職/企画職など成果が数値化しにくい職種 ・成長支援を重視する組織文化 |
評価制度設計では、この2つを「どのように組み合わせるか」が重要なポイントになります。 職種別・等級別に方針を変える、評価と報酬を切り離すなど、ハイブリッド型の設計を行う企業も増えています。
相対評価のメリット・デメリットと、評価制度設計での活かし方
相対評価の主なメリット
相対評価には、組織運営や人件費管理の観点から大きなメリットがあります。 あらかじめ評価ランクの割合(分布)を設定することで、評価の偏りが少なくなり、 全体のバランスを維持しやすくなる点は、特に大企業や多くの部署を抱える組織にとって重要です。
■ 全体の評価バランスを取りやすい/人件費をコントロールしやすい
相対評価では、Aランク○%、Bランク○%など、あらかじめ評価割合を決めることで、 評価のばらつきを抑え、部門や評価者による「甘い/厳しい」の差を調整できます。 結果として、賞与・昇給などの人件費を計画的に管理しやすくなるため、 経営側にとって財務的な予測可能性が高まります。
■ 評価格差をつけやすく、インセンティブを働かせやすい
相対評価は、評価結果に差をつけやすい特徴があり、 評価ランクごとの報酬差・昇格スピードの差をつけることで、 「より高みを目指す行動」を促すインセンティブ設計が可能です。 営業など成果が明確に表れる職種では、特に効果を発揮しやすい傾向があります。
■ 組織全体のパフォーマンス傾向を把握しやすい
相対評価を導入すると、「部署ごとの平均値」や「優秀層・課題層の割合」など、 組織全体のパフォーマンス傾向を俯瞰しやすくなります。 評価分布を毎年比較することで、組織の成長度合いや課題の変化を確認でき、 人材育成や配置転換の戦略にも活かすことができます。
相対評価の主なデメリット
一方で、相対評価は公平性・納得感の観点から課題を抱えることも多く、 制度設計や説明の仕方によっては、社員の不満や不信感につながりやすい側面があります。
■ 所属する集団によって評価が変わる不公平感
相対評価では、同じ成果でも「所属する部署内のレベル」によって評価が変わることがあります。 例えば、優秀者が多い部署では平均的な成果でも低評価を受け、 逆に低い成果でも上位に見える部署では高い評価を受ける可能性があります。 この仕組みは「評価の不公平感」につながりやすく、納得度を下げる要因になります。
■ 個人の成長や努力を評価しにくい
相対評価は、努力や成長より「周囲と比べてどうか」が重要になるため、 プロセスの改善や習熟度の向上など、数値化しにくい成長が評価につながりにくくなります。 その結果、社員が「頑張っても意味がない」と感じると、モチベーションの低下を招く可能性があります。
■ 下位層の固定化・足の引っ張り合いを生みやすい
固定された評価分布の中では、必ず一定割合の「低評価者」が生まれます。 これにより、下位層が変わりにくくなる、あるいは社員同士が競争しすぎて 協力関係が築きにくくなるなど、副作用が表れる場合があります。 特に「低評価=居場所がない」と感じる社員が増えると、離職率の上昇にもつながりかねません。
どのような組織・職種に「相対評価」が向いているか
相対評価は万能ではありませんが、特性を理解したうえで適切に活用すれば、 組織にとって大きな効果を発揮する評価方法です。 では、どのような企業・職種に相対評価が向いているのでしょうか。
■ 大規模組織・人件費管理を重視する企業
大人数の社員を抱える企業では、評価者のばらつきを抑え、 一定の評価分布を維持するために相対評価が有効です。 予算計画から逆算して評価ランクを設定できるため、 人件費の管理が重視される組織にとって相対評価は非常に相性の良い仕組みです。
■ 短期間で成果差が出やすい営業・販売など
営業成績や業績数値が明確に分かれやすい職種では、 相対評価によって社員間の成果差を適切に反映しやすくなります。 売上などがはっきりと見える職種では、評価ランクを使ってインセンティブをつける運用がうまく機能するケースが多いです。
相対評価は組織の特性に合わせて設計すれば大きな効果を発揮しますが、 公平性・納得感を高めるためには、評価基準の明確化・評価者研修・社員への説明責任が不可欠です。 成果の出やすい職種と、そうでない職種のバランスを見ながら、 「どこまで相対評価を使うのか」を戦略的に決めることが重要です。
絶対評価のメリット・デメリットと、モチベーション向上への活かし方
絶対評価の主なメリット
絶対評価は、あらかじめ定めた基準や目標に対してどれだけ達成したかを評価する方法で、 近年の人的資本経営・ジョブ型雇用の広がりとともに、導入する企業が増えています。 社員一人ひとりの成長や貢献をフェアに評価できる点が、多様な人材が活躍する現代にマッチしていることが大きな理由です。
■ 目標・基準が明確で納得感を得やすい
相対評価とは異なり、「誰かと比べてどうか」ではなく、 明確な評価基準と目標に対してどれだけ到達したかを判断するため、納得感が得られやすいのが特徴です。 特に、目標管理制度(MBO)やOKRなどと組み合わせることで、社員自身が達成基準を理解しやすくなり、 評価への透明性と納得度が高まりやすくなります。
■ 個人の成長プロセスを評価に反映しやすい
絶対評価は、成果だけではなく「努力の軌跡」「改善のプロセス」を評価しやすいため、 成長度合いや貢献の文脈を適切にとらえることができます。 このため、若手や新任者、中途入社者のように経験が少ない場合でも、適切に評価しやすいのが特徴です。
■ 多様な人材(若手・中途・時短など)をフェアに評価しやすい
働き方や勤務時間、キャリア背景が異なる人材が増える中、相対評価は「比較対象の違い」によって不利になりがちです。 絶対評価であれば、個々の状況に沿って評価基準を設定できるため、 短時間勤務者・専門職・育児と両立する社員など、さまざまな働き方をする人材を公平に評価できます。
■ 過剰な社内競争を抑え、協力しやすい風土をつくれる
絶対評価は、他者との競争ではなく「自分の目標達成」が評価の中心になるため、 人間関係のギスギスを生みにくく、チームで協力しやすい環境をつくることに貢献します。 心理的安全性が高まることで、1on1やフィードバック文化とも相性が良く、育成型の組織づくりに向いています。
絶対評価の主なデメリット
絶対評価はメリットが多い一方、基準設計や運用が難しく、制度設計を誤ると意図した効果が出ない場合があります。 特に評価基準の曖昧さや評価者のスキル不足は、制度の形骸化につながる大きなリスクです。
■ 評価基準の設計が難しい/設定を誤ると機能しない
絶対評価を成功させる最大の課題は「評価基準の具体性」です。 曖昧な基準や抽象的な表現のまま運用すると、評価者によって判断がバラバラになり、 「絶対評価なのに納得感がない」という逆効果を招きます。 基準の明文化・行動例の提示・評価者教育が必須です。
■ 評価格差がつきにくく、インセンティブが弱くなりやすい
努力や改善を評価する絶対評価では、「みんな平均的な評価」に収まりやすく、 結果として評価ランクの差がつきにくい傾向があります。 そのため、評価と報酬を強く連動させたい企業では、インセンティブ設計を工夫する必要があります。
■ 運用次第では人件費が膨張するリスク
基準に沿って評価を行い、達成者が多くなると、その分だけ昇給・賞与が増えやすくなります。 「達成=A評価」が多発する場合、財務的な計画が崩れる可能性があるため、 評価基準の難易度設定やキャップ(上限)設計が必要です。
どのような組織・職種に「絶対評価」が向いているか
絶対評価は、特に以下のような組織・職種で効果を発揮しやすい評価方法です。 自社の人材ポートフォリオや働き方の多様性を踏まえて、向き不向きを判断することが重要です。
■ 専門職・クリエイティブ・企画系など、プロセスや成長を重視したい職種
専門性が高く、成果の数値化が難しい職種では、 プロセス・改善・付加価値の創出など、絶対評価の方が適切に評価しやすくなります。 プロダクト開発・デザイン・研究開発・マーケティングなどが代表例です。
■ ダイバーシティ推進・ジョブ型雇用を志向する企業
多様な背景を持つ人材を活かしたい企業では、絶対評価の方が公平性を担保しやすくなります。 また、ジョブ型雇用では職務ごとに求める能力や成果基準が明確になるため、 「職務基準 × 評価基準」が整合しやすく、絶対評価との相性が良いのも特徴です。
絶対評価は、社員の成長支援や心理的安全性の高い組織づくりに大きく貢献しますが、 成功の鍵は評価基準の具体化・評価者教育・運用の一貫性にあります。 これらを丁寧に設計することで、モチベーション向上と組織成長につながる評価制度を構築することができます。
社員の「やる気」を高める評価制度設計:目標志向性とモチベーション理論
達成目標理論と3つの目標志向性
社員のやる気(モチベーション)は、単なるインセンティブだけでなく、 「どのような目標の捉え方をしているか」によって大きく左右されます。 心理学の「達成目標理論(Achievement Goal Theory)」では、人の動機づけは主に3つの目標志向性に分類されます。 評価制度設計の文脈でも、この目標志向性を理解することは非常に重要です。
■ 熟達目標志向(Mastery Goal)
自分の能力向上・スキルの習得・成長を重視するタイプ。 仕事に前向きに向き合い、改善や学習を続ける傾向があります。 最も持続的なモチベーションを生むとされ、心理学的にも望ましい志向性です。
■ 遂行接近目標志向(Performance Approach)
他者と比較して優れていること・認められることを目指すタイプ。 成果のアピールや競争の中で力を発揮しますが、ストレスが高くなりやすい側面もあります。
■ 遂行回避目標志向(Performance Avoidance)
「劣っていると思われたくない」という動機に基づき、評価や比較を回避しようとするタイプ。 挑戦を避ける、失敗を過度に恐れるなど、ネガティブな行動が生まれやすい傾向があります。
評価制度はこれらの志向性に大きな影響を与えます。 特に相対評価の比重が高すぎる組織では、「遂行回避」が生まれやすく、成長の阻害要因につながることに注意が必要です。
相対評価が高めやすい「遂行目標志向」のリスク
相対評価では、社員は常に「他者と比較される」環境に置かれます。 この構造は一見、競争を生み業績向上につながりそうに見えますが、実際には以下のようなリスクを高めやすい特徴があります。
■ 「劣っていると思われたくない」という動機付け
相対評価下では、優秀に見せたい(遂行接近)だけでなく、 「劣って見えるのを避けたい」という遂行回避目標志向が強く働きやすくなります。 その結果、以下のような行動につながることがあります。
- 挑戦が必要な仕事より、確実にできる仕事を選ぶ
- ミスを恐れ、報連相や相談が遅れる
- 他者の足を引っ張る、情報共有が滞る
- 心理的負荷が高まり、意欲の低下・離職リスクが上昇
相対評価を完全に否定する必要はありませんが、強すぎる競争構造は「長期的な成長」を阻害する点に注意が必要です。
絶対評価が支援する「熟達目標志向」
絶対評価は、「他者との比較」ではなく「個人の目標と成長」に焦点を当てるため、 社員が熟達目標志向(成長志向)を持ちやすくなります。
■ 自己成長への集中を促す
絶対評価では、前期よりどれだけ成長したか、どのスキルを習得したかが評価されるため、 「自分の成長に集中する」というポジティブな動機付けが働きやすくなります。
■ 建設的な振り返りを行いやすい
「他者より劣っている」と責められるのではなく、 「どこを改善すればよりよい成果につながるか」という建設的な対話が生まれやすくなります。 この点で絶対評価は、1on1や継続的フィードバックと非常に相性が良い仕組みです。
■ 多様な人材が活躍しやすい環境を整える
育児中の社員・時短勤務者・キャリアチェンジ直後の社員など、 働き方や経験が異なる人材でも、公平に評価されやすくなります。
つまり絶対評価は、持続的なモチベーションを形成しやすく、 成長を軸にした組織づくりに大きく貢献する評価方法といえます。
評価制度設計で意識したい「減点評価を避ける」メッセージの出し方
社員のモチベーションを左右するのは、評価制度そのものだけでなく、 評価基準の伝え方・メッセージの出し方です。 減点的なメッセージが多いほど、社員は「遂行回避志向」に偏り、挑戦を避けるようになります。
■ NG例(減点評価・萎縮を招くメッセージ)
- 「ミスをしないことが評価の前提です」
- 「もっと他の人と同じレベルにならないと評価できません」
- 「成果を出せなかった理由より、出せたかどうかが全てです」
■ OK例(熟達志向を育てるメッセージ)
- 「今回の結果から、次に活かせそうな点を一緒に整理しよう」
- 「前回よりどの部分が成長したかを見ていきます」
- 「成果だけでなく、プロセスや改善への取り組みも評価に含めています」
評価制度は「制度設計 × メッセージ × 運用」の三位一体で効果が高まります。 とくに、社員の成長意欲を引き出すためには、減点評価ではなく成長志向を伝えるコミュニケーションが欠かせません。
評価制度設計のステップ:ゼロから評価制度を組み立てる方法
ステップ1|評価制度の目的と「評価で変えたい行動」を明確にする
評価制度設計で最初に行うべきは、「制度を通じて何を実現したいのか」を明確にすることです。 闇雲に項目を作る前に、評価制度の目的と、自社が変えたい行動を言語化することで、制度の軸がブレなくなります。
- 採用につなげたい(魅力的な処遇設計・スキルの可視化)
- 定着率を改善したい(納得感のある評価・成長支援)
- 育成を強化したい(行動評価・1on1と連動)
- 生産性を向上させたい(目標管理・優先順位の明確化)
目的が曖昧なままだと、評価制度が「作って終わり」になり、社員にも浸透しません。 まずは経営・人事・現場マネジャーで目的を深くすり合わせることが重要です。
ステップ2|評価対象(成果・行動・スキル)と評価軸を整理する
次に、「何を評価するのか(評価対象)」を決めます。 評価対象は大きく以下の3種類に整理できます。
■ 成果評価(業績評価)
売上・件数・達成率など、数値成果を中心とする評価。 営業職・企画職など成果が測りやすい職種に適しています。
■ 行動評価(プロセス評価)
行動基準・協働・主体性・改善行動などを評価。 成果に至るプロセスを重視したい場合に有効です。
■ コンピテンシー評価(能力・スキル)
業務遂行能力・職種スキル・判断力・マネジメント力など、 「その職種で成果を出すために必要な能力」を言語化して評価します。
これらをバランスよく設計することで、短期成果だけに偏らず、持続的な成長を評価できる制度を構築できます。
ステップ3|相対評価と絶対評価の「基本方針」を決める
評価制度を設計するうえで避けて通れないのが、相対評価と絶対評価の割合(比率)をどうするかです。
■ 全社方針の決定例
- 原則は「絶対評価」、昇給・賞与の最終調整にのみ相対評価を使用
- 評価は絶対評価、育成目的で行動評価を重視
- 職種別に方針を変える(営業=相対評価比率高、専門職=絶対評価中心)
特に現代の働き方(テレワーク・専門職の増加・多様な働き方)においては、 絶対評価を軸としたハイブリッド評価が主流になりつつあります。
ステップ4|等級制度・報酬制度との連動設計
評価制度は単体で存在するものではなく、等級制度・報酬制度とセットで設計する必要があります。 これが欠けると、評価の意味が曖昧になり「評価されても待遇に反映されない」という不満が生じます。
■ 連動設計のポイント
- 等級(役割責任)ごとに求める成果・行動を明確にする
- 評価結果をどこまで給与・賞与・昇格に反映するかを明示
- 昇格には「成果 × 行動 × スキル」の総合評価を採用
- 高評価は昇給ではなく、業績賞与で調整することで人件費をコントロール
評価制度と報酬制度の「連動度合い」を明確にすることで、社員の納得感・透明性が高まります。
ステップ5|評価プロセス・スケジュール・ツールを設計する
制度設計の最後は、実際に運用するための評価プロセス・スケジュール・ツールを整える段階です。
■ 一般的な評価プロセスの流れ
- 期初:目標設定(MBO / OKR / 行動目標)
- 中間:進捗レビュー・1on1・振り返り
- 期末:自己評価 → 上長評価 → 部門評価会議
- フィードバック面談:結果・今後の成長課題の共有
■ ツールの整備
- Excelベース:小規模組織向け
- クラウド評価システム:中〜大規模組織/テレワーク環境に最適
- 1on1管理ツール・タレントマネジメントシステムとの連動
評価制度は「作る」よりも「運用する」ほうが難しいため、 運用負荷を減らすためのツール・会議体・フィードバック文化の整備が、成功の鍵になります。
相対評価・絶対評価を組み合わせた「ハイブリッド評価制度」の設計例
パターン①|一次評価は絶対評価・二次評価で相対調整(甘辛調整)
近年、多くの企業が採用しているのが、「一次評価=絶対評価」「二次評価=相対評価(甘辛調整)」のハイブリッド方式です。 まず一次評価で社員の目標達成度・行動・成長プロセスをしっかり評価し、 二次評価(部門長会議・全社評価会議)で分布調整を行うことで、納得感と公平性の両立が可能になります。
■ 評価会議での分布調整(キャリブレーション)
- 複数の評価者で評価のブレを確認し、過度な甘い/厳しい評価を補正
- 評価分布(S/A/B/C/D割合)を確認し、人件費計画に沿って調整
- 「評価理由」「行動証拠(エビデンス)」を共有し、透明性を担保
この手法は、公平性・納得感・財務健全性を同時に満たしやすく、 大企業からベンチャーまで幅広く活用される代表的なハイブリッドモデルです。
パターン②|職種別・等級別に評価方法を切り替える
職種ごとに成果の出方・業務特性が大きく異なる場合、 「職種別・等級別」に評価方法を切り替えるハイブリッド設計が向いています。
■ 営業職の例(成果の差が明確に出る)
- 絶対評価(目標達成率・売上・KPI)の比重を高める
- 最終的な報酬決定は相対調整を加え、格差をつける
■ 企画・管理・専門職の例(プロセス重視)
- 行動評価・プロセス評価・コンピテンシー評価を中心に絶対評価を採用
- 職種特性に合わせて、評価基準を細かく定義
「等級別」に切り替える方法も有効で、
若手=成長評価/中堅=成果+行動/管理職=戦略・組織貢献 というように設計すると、キャリアステップに沿った評価制度が実現します。
パターン③|報酬は相対評価、人材育成は絶対評価で運用する
評価制度の中でも、特に対立しやすいのが「評価」と「報酬」の関係です。 この課題を解決するモデルが、報酬=相対評価/育成=絶対評価という運用です。
■ 報酬は相対評価(理由:人件費の安定化)
- 評価ランクごとの報酬を固定し、人件費を計画的にコントロール
- 昇給・賞与の対象者割合を調整しやすい
■ 育成は絶対評価(理由:社員の成長支援)
- 成長プロセス・努力・行動改善を正しく評価し、学習意欲を引き出す
- 評価=人材開発ツールとして活用しやすい
- 職場の心理的安全性を確保しやすい
特に、ダイバーシティ推進・時短勤務・専門職採用が増えている企業では、 この方式が社員の納得感を高めると評価されています。
導入企業の事例イメージ
■ 事例①:相対評価から絶対評価への切り替え(リコーリースなど)
- 従来の相対評価では「全員が成果を出しても低評価者が出る」という不公平が発生
- 絶対評価へ切り替え、難易度の高い目標達成者は全員高評価に
- 評価者トレーニング・目標設定支援により、評価の質を維持
■ 事例②:PIP(業務改善プログラム)との組み合わせ(Amazonなど)
- 相対評価によりローパフォーマーを選出(ボトム層を明確化)
- PIP(Performance Improvement Plan)で行動改善を支援
- 改善できた場合は再評価し、早期離職・不公平感の抑制に成功
このように、ハイブリッド評価制度は 公平性・育成・人件費管理・エンゲージメント向上を同時に実現しやすい手法です。 現代の複雑な働き方を踏まえると、単一の評価制度よりも、 「組み合わせ」で組織に最適化する時代になっています。
評価制度設計を失敗させないためのチェックリスト
チェック1|評価基準は現場の実態と乖離していないか
評価制度がうまく機能しない最大の原因は、評価基準が現場の実態とズレていることです。 評価項目が抽象的すぎたり、職種の業務内容に合っていないと、評価者・被評価者ともに混乱が生じます。
- 職種・等級ごとに「求められる行動」「成果指標」が明確になっているか
- 現場マネジャー・社員の声を反映した基準になっているか
- 実際の仕事で“測れる”項目になっているか
基準の整備は、制度の納得感・運用のしやすさを左右する最重要ポイントです。
チェック2|目標難易度は「少し背伸び」で妥当か
評価制度の質を最も左右するのが、目標設定の適切さ(難易度)です。 高すぎても低すぎても意味がなく、社員の成長意欲を引き出すには「少し背伸び」できるレベルが最適とされています。
- 達成可能性70%前後の適正難易度か
- 成果目標(KPI)だけでなく行動目標も含めているか
- 期初面談で目標の認識合わせを行っているか
難しすぎる目標はモチベーションを下げ、簡単すぎる目標は評価の信頼性を失わせます。 評価制度設計では、目標難易度のコントロールが不可欠です。
チェック3|評価者研修・1on1など運用を支える仕組みがあるか
どれだけ優れた評価制度を作っても、運用ができなければ機能しません。 評価者のスキル差により評価がブレることは、制度への不満・不信感を生む最大の要因です。
- 評価者トレーニング(評価基準・甘辛調整・フィードバック方法)が整っているか
- 1on1の実施習慣があり、フィードバック文化が醸成されているか
- 評価会議の運営ルールが明確か
制度は「設計50%・運用50%」。運用支援の仕組みを整えることで初めて効果を発揮します。
チェック4|評価分布・人件費への影響をシミュレーションしているか
評価制度は組織運営だけでなく、財務(人件費)にも直結する仕組みです。 制度変更の前には、必ず「評価結果がどれくらい人件費に影響するか」を事前試算する必要があります。
- 評価ランク分布(S/A/B/C/D)を設定し、人件費の変動を試算したか
- 昇給・賞与・昇格にどの程度連動するかを計算したか
- 制度見直しによる財務インパクトが把握できているか
評価制度は人件費シミュレーションとセットで設計することが成功の鍵となります。
チェック5|社員への説明資料・FAQを用意しているか
評価制度は、社員が理解できなければ意味がありません。 制度の趣旨・目的・評価基準・反映方法などを、わかりやすく資料化して説明することが必須です。
- 制度全体像を図解した資料があるか
- 評価基準・目標設定のサンプルを提示しているか
- 社員からよくある質問(FAQ)を事前に整理しているか
- 評価面談での伝え方に関するガイドラインがあるか
社員の理解が深まるほど、制度の納得感と運用品質が高まります。
チェック6|定期的に制度を見直すサイクルが設計されているか
評価制度は、一度導入して終わりではなく、社会の変化・組織の成長に合わせて更新すべき仕組みです。
- 半年〜1年ごとに制度を振り返る仕組みがあるか
- 評価者・社員からのフィードバックを収集しているか
- テレワーク・ダイバーシティ・ジョブ型など時代の変化に合わせて改善しているか
定期的な制度改善こそ、評価制度の信頼性を高め、組織パフォーマンス向上につながる重要なステップです。
タレントマネジメントとセットで考える「これからの評価制度設計」
評価データを「人材データベース」として活用する視点
これからの評価制度は、単なる「査定のための仕組み」ではなく、 人材データベースの中核となる重要な情報源として機能させることが求められます。 評価データを活用することで、企業はより精度の高い人材配置や育成施策を実行できます。
■ 配置・登用への活用
- 評価データ×スキルデータで、適材適所の配置が可能に
- 管理職候補者・ハイパフォーマーを可視化し、計画的な登用に反映
■ 育成計画への連携
- 評価結果から「強み・弱み」を把握し、個別の育成計画を作成
- 評価と育成を一体化させ、継続的なスキルアップを支援
評価データをタレントマネジメントに統合することで、 人材戦略そのものをアップデートする基盤が整います。
人事DX/人事評価システムを活用した評価業務の効率化
評価制度を運用するうえで大きな負担となるのが、紙・Excelベースの運用です。 これを解決するのが、人事評価システムやタレントマネジメントシステムを活用した人事DXです。
■ クラウドに移行するメリット
- 評価シートの提出・管理・集計が自動化され、担当者の負荷が大幅に削減
- 評価履歴・スキル情報・1on1記録が一元管理できる
- 評価の進捗管理(未提出者管理)が容易になる
- 評価会議(キャリブレーション)がスムーズに運営できる
さらに、AIを活用した評価コメント支援・面談アシスト機能を搭載したシステムも増えています。 人事DXを取り入れることで、評価業務の正確性・スピード・透明性を大幅に向上させることが可能です。
人的資本経営・人的資本開示と評価制度設計の関係
人的資本経営・人的資本開示が義務化・推進される中で、評価制度は単なる「社内制度」ではなく、 企業価値向上に直結する重要な仕組みと位置付けられています。
■ 評価指標と人的資本KPIの紐づけ
- リスキリング率・エンゲージメント・内部登用比率など、人的資本指標を評価制度に反映
- 評価結果をKPIとして開示することで、企業の透明性と信頼性が向上
- 成長促進型の評価制度が、人的資本投資の効果測定につながる
人的資本経営の時代において、評価制度は「社員の成長」と「企業の持続的価値向上」をつなぐ重要な基盤です。 タレントマネジメントと連動させることで、組織戦略の中心として機能する評価制度へと進化します。
まとめ|評価制度は「公平性×成長×戦略」のバランスで設計する時代へ
評価制度は、単なる給与決定のための仕組みではなく、組織の成長を支える中核となる人材マネジメント基盤です。 相対評価・絶対評価のどちらか一方に寄せるのではなく、職種・等級・組織フェーズに応じて柔軟に組み合わせる「ハイブリッド評価」が主流となりつつあります。 とくに近年は、テレワーク、ジョブ型、人的資本経営など、働き方の多様化が進む中で、評価制度にも公平性・透明性・成長支援の視点が欠かせません。
また、評価制度を成功させるためには、評価基準の明確化や目標設定の適正化に加えて、運用を支える仕組み(評価者研修、1on1、評価会議、ツール整備)が不可欠です。 制度を「作る」だけではなく、現場で「使われ、納得され、成長につながる」状態にすることが重要です。 さらに、評価データをタレントマネジメントや人的資本開示へと連動させることで、企業の戦略人事を強化する大きな武器になります。
自社に合った評価制度を構築し、運用サイクルを継続的に改善していくことで、社員のエンゲージメント向上や定着率改善、生産性向上につながります。 まずは現状を見直し、理想とのギャップを整理するところから始めてみてください。必要であれば、専門家への相談や外部ツールの活用も有効な選択肢です。





 導入までの流れ
導入までの流れ
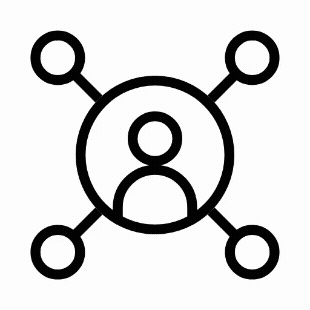
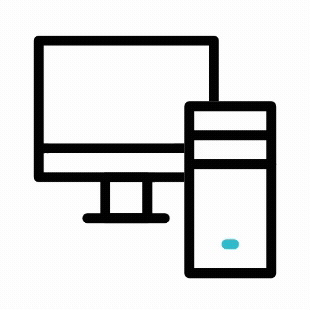

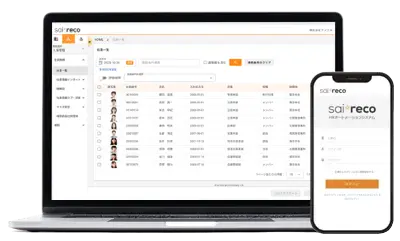



 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求