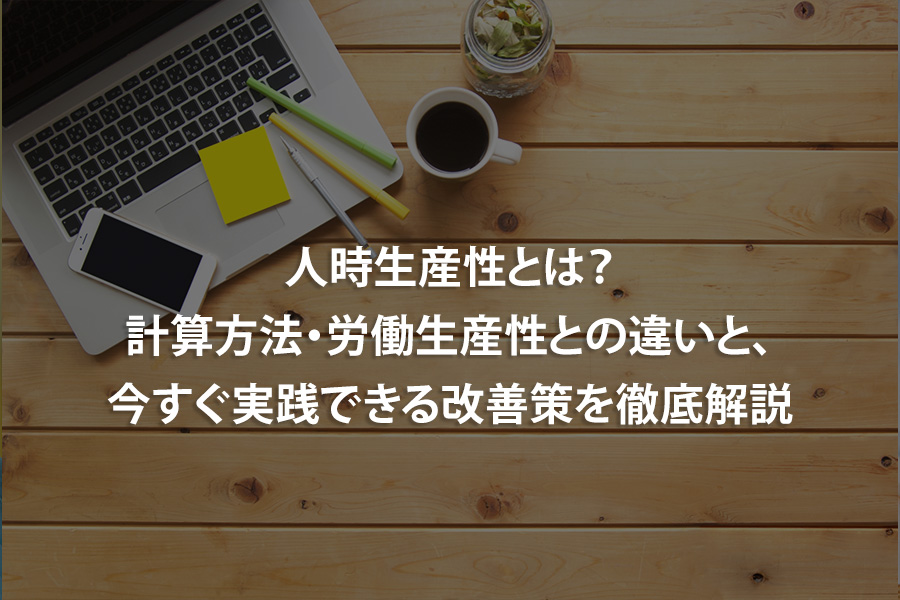
人手不足や働き方改革が進む中、限られた時間と人数で成果を出すことが企業経営の重要課題となっています。その中で注目されている指標が「人時生産性」です。人時生産性は、従業員1人が1時間あたりどれだけの粗利を生み出しているかを示す指標で、単なる売上や人数では見えにくい業務効率や収益構造を可視化できます。一方で、労働生産性や人時売上高との違いが曖昧なまま使われていたり、数値を出しただけで改善につながらないケースも少なくありません。本記事では、人時生産性の定義や計算方法といった基礎から、注目される背景、分析の進め方、そして現場で実行できる改善策までを体系的に解説します。人時生産性を正しく理解し、実務や経営判断にどう活かすべきかを知りたい方に向けた内容です。
人時生産性とは何か
人時の意味と生産性指標としての考え方
人時生産性を理解するうえで、まず押さえたいのが「人時(にんじ)」という言葉です。人時とは、1人が1時間働くことで対応できる作業量、またはその作業に投入した労働量を表す単位です。たとえば、2人で1時間かけて終える作業は2人時、2人で30分なら1人時というように、人数と時間を掛け合わせて把握します。
ここで重要なのは、人時という単位を使うことで「人数が多いから成果が大きい」「残業したから進んだ」といった印象論から離れ、投入した労働量に対する成果を比較しやすくなる点です。生産性は一般に、インプット(投入資源)に対してアウトプット(成果)がどれだけ得られたかを示します。人時生産性は、このインプットを人時(人数×時間)で捉え、時間あたりの成果に落とし込むことで、部門や業務、日別・週別などの粒度で改善ポイントを特定しやすくします。
また、雇用形態や働き方が多様化している現代では、「1人あたり」だけで比較すると実態を見誤ることがあります。短時間勤務やシフト制、派遣・業務委託などが混在する職場では、人数よりも「何時間投入したか」が実務上の管理単位になりやすく、人時で捉えることで現場の実態に沿った分析が可能になります。
人時生産性が示すもの(粗利ベースで見る理由)
人時生産性は、従業員1人が1時間働いたときに、どれだけの粗利を生み出したかを示す指標です。基本の考え方は「粗利 ÷ 総労働時間(人時)」で、総労働時間は業務に投入した人数×時間で算出します。つまり、人時生産性が高いほど、同じ時間あたりに利益を生み出せている状態だと言えます。
ここで「売上」ではなく「粗利(売上−売上原価)」を用いることには意味があります。売上だけを見ると、値引きや原価の増加があっても売上が伸びているように見え、実態としては利益が残っていないケースが起こり得ます。一方、粗利ベースで見れば、材料費や外注費などのコスト構造を含めて、どれだけ利益に結びつく仕事ができているかを評価できます。
たとえば、売上が大きくても原価が高いビジネスモデルでは、売上の増加がそのまま利益増加につながりません。人時生産性は粗利を基準にすることで、収益性の高い業務・商品・顧客に時間を投下できているかを判断しやすくなります。経営の視点では、限られた人員と時間のなかで利益を最大化することが求められるため、人時生産性は「忙しいのに利益が残らない」「残業が増えるのに成果が伸びない」といった状況を可視化するのに役立ちます。
ただし、短期的に人時生産性だけを追いすぎると、育成や引き継ぎ、改善活動など将来の成果につながる時間が削られ、長期的には組織力が落ちる可能性もあります。人時生産性は、あくまで意思決定を助ける指標として、部門特性や中長期の戦略とセットで運用することが重要です。
人時生産性が注目される背景
労働人口減少と人手不足の深刻化
人時生産性が注目される大きな背景の一つが、労働人口の減少と慢性的な人手不足です。少子高齢化の進行により、日本の労働力人口は中長期的に減少傾向にあり、多くの企業が「人を増やして対応する」成長モデルを取りづらくなっています。採用市場では人材確保の競争が激化し、必要な人数を確保できないまま業務量だけが増えるケースも少なくありません。
このような環境では、単純に従業員数や総労働時間を増やすのではなく、限られた人員と時間でどれだけの成果を生み出せているかを把握することが重要になります。人時生産性は、人数ではなく「人時」という共通単位で成果を測るため、現実的なリソース制約を前提とした生産性管理に適しています。人手不足が常態化する中で、経営や現場の意思決定に直結する指標として、人時生産性への関心が高まっています。
働き方改革・残業規制が経営に与える影響
働き方改革の推進や労働基準法の改正により、時間外労働の上限規制や割増賃金率の引き上げが進んでいます。これにより、長時間労働を前提とした業務運営はコスト面・コンプライアンス面の両方でリスクが高まっています。かつてのように残業で業務量を吸収するやり方は、経営上も現実的ではなくなりました。
この変化は、企業に対して「決められた時間内で成果を出す」ことを強く求めています。人時生産性は、労働時間を増やすことなく成果を高められているかを可視化できるため、残業削減と業績維持・向上を両立させるための指標として有効です。残業時間が減っても人時生産性が上がっていれば、業務の質や効率が改善していると判断でき、経営判断の裏付けとしても活用できます。
多様な雇用形態と「1人あたり指標」の限界
近年は、正社員だけでなく、短時間勤務、パート・アルバイト、派遣社員、業務委託など、多様な雇用形態が混在する職場が増えています。このような環境では、「従業員1人あたりの売上」や「1人あたりの利益」といった指標だけでは、実態を正確に捉えにくくなります。勤務時間や役割が異なる人材を単純に人数で比較すると、誤った評価につながる可能性があります。
人時生産性は、雇用形態に関わらず「投入した時間」を基準に成果を測るため、多様な働き方を前提とした比較が可能です。フルタイムと短時間勤務が混在する部門や、シフト制の現場でも、時間あたりの成果として横並びで分析できます。その結果、業務配分やシフト設計、外注・内製の判断など、実務に直結する改善につなげやすくなり、従来の「1人あたり指標」の限界を補う指標として人時生産性が重視されています。
人時生産性の計算方法と具体例
基本の計算式と用語整理(粗利・総労働時間)
人時生産性は、従業員1人が1時間あたりにどれだけの粗利を生み出しているかを示す指標です。基本の計算式は次のとおりです。
人時生産性 = 粗利 ÷ 総労働時間
ここで押さえておきたい用語は2つあります。まず「粗利」は、一般的に売上高から売上原価を差し引いた利益を指します。サービス業や受託業では、原価の範囲(外注費、材料費、仕入れなど)の定義が会社によって異なることがあるため、自社の会計ルールに沿って統一することが重要です。
次に「総労働時間」は、対象となる業務や部門に投入した労働時間の合計です。人数×時間で算出でき、たとえば2人が2時間作業した場合は総労働時間は4時間となります。人時生産性は、粗利を総労働時間で割るため、粗利を増やすか、同じ粗利を生み出すための時間を減らすことで向上します。
簡単な数値例で理解する人時生産性
計算イメージをつかむため、簡単な例で確認します。たとえば、ある業務で粗利が12,000円生まれ、2人が2時間作業したとします。このとき総労働時間は2人×2時間で4時間です。人時生産性は次のように計算できます。
人時生産性 = 12,000円 ÷ 4時間 = 3,000円
つまり、この業務は「1人が1時間働くと平均3,000円の粗利を生み出している」状態と解釈できます。もし同じ粗利12,000円を、2人で1.5時間(総労働時間3時間)で終えられれば、人時生産性は4,000円になります。逆に、段取り不良や手戻りで2人が3時間かかれば、総労働時間は6時間になり、人時生産性は2,000円まで下がります。
このように、人時生産性は「成果は同じでも、かかった時間によって数値が変わる」ため、改善活動の成果を見える化しやすい指標です。とくに、業務フロー改善やツール導入の効果検証と相性が良い点が特徴です。
正確な算出に必要なデータ管理のポイント
人時生産性は計算式がシンプルな一方で、入力データが不正確だと結論を誤りやすい指標でもあります。まず重要なのは、粗利の定義を固定し、部門や案件ごとにブレないようにすることです。たとえば、外注費や変動費を原価に含める範囲が案件ごとに異なると、数値の比較ができなくなります。会計上の区分と現場運用をすり合わせ、粗利の算出ロジックを統一しましょう。
次に、総労働時間を「どの単位で」集計するかを決めることが大切です。全社で見るのか、部門別で見るのか、案件別で見るのかによって、必要な工数の粒度が変わります。改善を目的とするなら、まずは部門別や業務カテゴリ別など、現場で原因を追える単位から始めると運用が定着しやすくなります。
さらに、時間データの精度も重要です。自己申告の入力だけに頼ると、入力漏れや丸め(30分単位で適当に入れるなど)が発生しやすく、分析に耐えないことがあります。勤怠データと工数データの紐づけ、入力ルールの明確化、例外処理の設計、定期的なチェック体制を用意し、継続的に「正確な数値が集まる仕組み」を整えることが、人時生産性を改善につなげる前提になります。
人時生産性と他の指標との違い
人時売上高との違いと使い分け
人時生産性と混同されやすい指標の一つが「人時売上高」です。人時売上高は、従業員1人が1時間あたりにどれだけの売上を生み出したかを示す指標で、計算式は「売上高 ÷ 総労働時間」となります。売上規模や回転率を把握するのに適しており、特に飲食店や小売業など、売上の動きが比較的わかりやすい業種で活用されることが多い指標です。
一方、人時生産性は売上ではなく粗利を基準に算出します。そのため、値引きや原価の増減といったコスト構造を反映した評価が可能です。売上は伸びているものの、原価率が高く利益が残っていない場合、人時売上高だけを見ていると問題に気づきにくくなります。人時生産性を併せて確認することで、「忙しいが利益が出ていない」「時間をかけている割に収益性が低い」といった状態を把握できます。
実務では、売上規模や現場の稼働感を見るために人時売上高を、収益性や経営効率を判断するために人時生産性を使い分けるのが効果的です。どちらか一方ではなく、目的に応じて併用することで、より立体的な分析が可能になります。
労働生産性との違いと位置づけ
労働生産性は、投入した労働量に対してどれだけの成果を生み出したかを測る、より広い概念の指標です。アウトプットには、生産数量や付加価値額などが用いられ、計算方法も「付加価値 ÷ 労働者数」や「付加価値 ÷ 総労働時間」など、目的に応じてさまざまです。企業全体や国レベルでの比較に使われることも多く、マクロな視点での生産性把握に向いています。
人時生産性は、この労働生産性の考え方を「従業員1人あたり1時間」にまで細分化した指標と捉えることができます。つまり、労働生産性を現場レベルで使いやすくした指標が人時生産性です。部門別、業務別、日別といった粒度での分析がしやすく、具体的な改善アクションにつなげやすい点が特徴です。
経営全体の方向性を確認する際には労働生産性、現場改善や業務設計の見直しには人時生産性、といったように、視点の違いで使い分けると理解しやすくなります。
経営判断で併用すべき指標の考え方
生産性指標は、単独で見ると誤解を招くことがあります。たとえば、人時生産性だけを追いすぎると、短期的に粗利を生まない育成や改善活動の時間が削られ、中長期的な競争力が低下する可能性があります。また、人時売上高が高くても、人件費や原価が膨らんでいれば利益は残りません。
そのため、経営判断では複数の指標を組み合わせて見ることが重要です。具体的には、人時生産性で収益性と時間効率を確認し、人時売上高で売上規模や稼働状況を把握し、労働生産性で全社的な付加価値創出力を見る、といった役割分担が考えられます。さらに、離職率や残業時間、従業員満足度などの定性・定量指標と併せて確認することで、数字の背景にある現場の実態を読み取りやすくなります。
人時生産性はあくまで意思決定を支えるための指標の一つです。他の指標と併用しながら、短期の効率と中長期の成長を両立できているかを継続的に確認することが、実効性のある生産性向上につながります。
人時生産性の分析方法
業種別平均との比較でわかる自社の立ち位置
人時生産性を改善につなげるには、まず「自社の現状が高いのか低いのか」を判断できる基準を持つことが重要です。その際に役立つのが、業種別平均との比較です。人時生産性は業種特性によって水準が大きく異なり、同じ目標値を一律に当てはめると、現実的でない目標設定になったり、逆に改善余地を見落としたりします。
たとえば、原価構造や単価、稼働率が異なるため、製造業と飲食店では平均値に差が出やすい傾向があります。まずは公的機関や業界団体などが公表している統計・調査を参考にしつつ、自社の人時生産性を同業種のレンジの中で位置づけましょう。ここでの目的は「勝ち負け」を決めることではなく、現状認識を揃え、改善目標を妥当な水準に設定することです。
ただし、業種平均はあくまで参考値です。同じ業種でも、店舗立地、顧客層、提供サービス、付加価値のつけ方によって粗利構造は大きく変わります。平均値に近づけること自体がゴールではなく、自社の戦略やビジネスモデルに合った人時生産性の水準を見極める視点が欠かせません。
部門別・業務別に見る分析の進め方
全社の人時生産性を把握するだけでは、改善の打ち手を具体化しにくいことが多いです。そこで有効なのが、部門別・業務別の分解分析です。会社全体で利益が出ていても、特定部門で大きなロスが発生している、あるいは収益性の低い業務に時間が偏っているケースは珍しくありません。
分析の基本ステップは、対象範囲の設定、データの整備、比較軸の用意、原因仮説の抽出、改善施策の実行と検証です。まずは部門単位で人時生産性を算出し、平均との差や前年差などの変化を確認します。そのうえで、課題が大きい部門は業務カテゴリや工程単位に落としていき、どこに時間がかかっているのか、どこで手戻りが起きているのかを特定します。
さらに、同じ業務でも担当者やチームによって人時生産性に差が出る場合があります。この差は、スキルや経験だけでなく、業務設計、ツールの使い方、情報共有の仕組み、依頼の出し方など、構造的な要因で生じていることも多いです。個人の能力差として片づけず、プロセスや仕組みの観点で比較することが、再現性の高い改善につながります。
数値比較だけで終わらせないための注意点
人時生産性は、数値が出るぶん「比較して終わり」になりやすい指標でもあります。数値を眺めて優劣を評価するだけでは、現場の納得感が得られず、改善行動にも結びつきません。重要なのは、人時生産性の変動要因を分解し、改善可能な要素に落とし込むことです。
注意したいポイントは大きく3つあります。1つ目は、粗利や工数の定義が部門ごとに異なっていないかです。定義が揃っていない比較は、結論が歪みます。2つ目は、一時的な要因に引っ張られないことです。繁忙期・閑散期、突発対応、設備トラブルなどの影響を切り分けるため、単月だけでなく複数期間でトレンドを見ることが望ましいです。3つ目は、短期最適に偏らないことです。育成、改善活動、引き継ぎ、品質管理などは短期的に粗利を生みにくい一方で、中長期の生産性向上に不可欠な時間です。
数値を「評価」ではなく「改善のための情報」として扱い、現場と一緒に原因を特定して打ち手を設計することが、人時生産性分析を成果につなげるポイントになります。
人時生産性を下げる主な要因
生産ロス・管理ロスが起きる構造
人時生産性が伸び悩む企業では、業務プロセスの中にさまざまなロスが潜んでいます。代表的なのが、生産ロスと管理ロスです。生産ロスとは、本来価値を生まない作業や待ち時間、手戻りなどによって発生する時間的損失を指します。製造業であれば、設備トラブルによる停止時間や不良品の作り直し、サービス業であれば、指示の曖昧さによる再対応や修正作業などが該当します。
一方、管理ロスは、計画や調整が不十分なことで生じる待機時間や非効率な動きを指します。たとえば、承認待ちが長引く、必要な情報が共有されていない、担当者が不在で作業が止まるといった状況です。これらは現場の努力だけでは解消しにくく、業務設計や管理体制そのものに原因があるケースが多く見られます。
生産ロスと管理ロスが重なると、現場は忙しく動いているにもかかわらず、粗利につながる時間が増えません。その結果、人時生産性が低下し、「働いているのに成果が出ない」という状態に陥りやすくなります。
動作ロス・手作業ロスの具体像
動作ロスとは、作業そのものの進め方や環境に無駄があることで生じる時間のロスです。たとえば、作業動線が整理されておらず移動が多い、操作手順が複雑で何度も確認が必要になる、教育不足により作業に時間がかかるといったケースが挙げられます。これらは一つひとつは小さく見えても、積み重なることで大きな時間損失になります。
手作業ロスは、本来であればシステムやツールで代替できる作業を、人の手で行っていることで発生します。たとえば、Excelへの転記作業、手計算による集計、紙資料の確認や入力などです。人が介在する工程が多いほど、時間がかかるだけでなく、入力ミスや確認作業による追加工数も発生しやすくなります。
動作ロスや手作業ロスは、現場にとっては「当たり前のやり方」として放置されやすいのが特徴です。しかし、人時生産性の視点で見ると、改善余地が大きい領域でもあります。業務の標準化やツール活用によって、比較的短期間で効果が出やすい点も特徴です。
編成ロスが組織全体に与える影響
編成ロスとは、業務の流れや人員配置が適切でないことによって生じるロスを指します。主に製造業のライン作業で使われる概念ですが、オフィス業務やプロジェクト型の仕事でも頻繁に発生します。たとえば、前工程が遅れて次工程が待ち状態になる、特定の担当者に業務が集中してボトルネックになるといった状況です。
編成ロスの厄介な点は、一部の工程や人員の問題が、組織全体の人時生産性を押し下げることです。個々の担当者は効率よく動いていても、全体の流れが悪ければ、待ち時間や手戻りが増え、結果として総労働時間が膨らみます。
このロスを解消するには、単に人を増やすのではなく、業務の順序や役割分担、情報の受け渡し方法を見直す必要があります。人時生産性を高めるためには、個人の頑張りに頼るのではなく、組織全体の設計を見直す視点が欠かせません。
人時生産性を向上させる実践ポイント
人員配置とスキル・適性の見直し
人時生産性を高めるうえで、最初に見直したいのが人員配置です。同じ業務でも、担当者のスキルや経験、得意分野によって、かかる時間や成果は大きく変わります。業務内容と人材の適性が合っていない場合、本人の努力に関わらず、人時生産性は上がりにくくなります。
重要なのは、単に「早くできる人に任せる」ことではありません。短期的には効率が上がっても、特定の人に業務が集中し、属人化や疲弊を招くリスクがあります。スキルの可視化や業務の棚卸しを行い、適性に合った配置と同時に、育成や引き継ぎを前提とした体制づくりを進めることで、中長期的に安定した人時生産性の向上が期待できます。
業務プロセスの可視化と効率化
人時生産性が低下している原因は、個人の能力ではなく、業務プロセスそのものにあるケースが少なくありません。そのため、改善の第一歩として、現状の業務フローを可視化することが有効です。業務の流れを書き出し、どの工程にどれくらいの時間がかかっているのか、どこで待ちや手戻りが発生しているのかを整理します。
可視化によってボトルネックが明らかになれば、不要な工程の削減、手順の簡素化、承認フローの見直しなど、具体的な効率化施策を検討できます。重要なのは、一度で完璧を目指さないことです。小さな改善を積み重ね、その効果を人時生産性の変化として確認しながら、段階的に業務を最適化していくことが、現場に定着しやすい進め方です。
ITツール・RPA導入による時間削減
人時生産性向上の施策として、ITツールやRPAの活用は非常に効果的です。データ入力、集計、転記、定型的なチェック作業など、付加価値を生みにくい業務は、自動化によって大幅な時間削減が見込めます。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に時間を使えるようになります。
ただし、ツールを導入すること自体が目的になってしまうと、期待した効果が得られないこともあります。導入前に、どの業務にどれくらいの時間がかかっているのかを把握し、人時生産性の観点で優先順位をつけることが重要です。また、ツール導入後も、実際にどれだけ時間が削減できたのかを数値で確認し、必要に応じて運用を見直すことで、継続的な改善につながります。
従業員モチベーションと中長期視点の重要性
人時生産性は、仕組みやツールだけでなく、働く人のモチベーションにも大きく左右されます。意欲が低下した状態では、同じ時間を使っても成果は出にくくなります。評価制度や目標設定が不透明であったり、改善提案が反映されにくい環境では、生産性向上の取り組み自体が形骸化しやすくなります。
また、人時生産性を短期的な数値だけで評価すると、育成や改善活動といった将来の成果につながる時間が軽視される恐れがあります。中長期的には、スキル習得や業務改善に投資した時間が、結果として人時生産性を押し上げるケースも多くあります。短期の効率と中長期の成長を両立させる視点を持ち、従業員が納得して取り組める仕組みを整えることが、持続的な人時生産性向上の鍵となります。
経営指標としての人時生産性の活かし方
収益性・コスト管理への活用
人時生産性は、現場改善だけでなく、経営レベルで収益性やコスト構造を把握するための指標としても有効です。売上や利益の総額だけを見ていると、業務量の増加や残業によって一時的に数字が伸びている状態と、効率的に利益を生み出している状態の違いが見えにくくなります。人時生産性を確認することで、同じ時間を使ってどれだけ利益を生み出せているかを把握でき、収益の質を評価しやすくなります。
また、部門別や事業別に人時生産性を見ることで、どこにコストがかかりすぎているのか、どの業務が収益性を押し下げているのかを特定しやすくなります。値上げや価格改定の検討、原価構造の見直し、外注と内製の判断なども、人時生産性を軸に考えることで、感覚ではなく数値に基づいた意思決定が可能になります。
人事施策・働き方改革との連動
人時生産性は、人事施策や働き方改革と密接に関係しています。時間外労働の削減や有給休暇の取得促進など、働き方改革を進める中で、「時間を減らした分、成果が落ちていないか」を確認する指標として活用できます。労働時間が短縮されても人時生産性が維持または向上していれば、業務の質や進め方が改善されていると判断できます。
さらに、人材育成や配置転換、評価制度の見直しといった人事施策の効果検証にも役立ちます。研修や教育に時間を投資した結果、人時生産性がどう変化したのかを見ることで、施策の成果を客観的に把握できます。ただし、人時生産性を個人評価に直結させると短期的な効率ばかりが重視されやすいため、組織や業務単位での活用を基本とすることが重要です。
短期改善と中長期成長を両立させる視点
人時生産性を経営指標として活かすうえで意識したいのが、短期的な改善と中長期的な成長のバランスです。短期的には、業務効率化やコスト削減によって人時生産性を引き上げることができますが、それだけに偏ると、育成や改善活動への投資が後回しになり、将来的な競争力が低下するリスクがあります。
中長期の視点では、スキル向上や業務標準化、システム投資などに一定の時間とコストをかけることで、結果として人時生産性が底上げされるケースも多くあります。そのため、人時生産性は単なる「削減指標」ではなく、「成長のための判断材料」として位置づけることが重要です。短期の数値変動に一喜一憂するのではなく、トレンドを継続的に確認しながら、経営戦略や人事戦略と連動させて活用することで、持続的な成果につなげることができます。
まとめ
人時生産性は、従業員1人が1時間あたりにどれだけの粗利を生み出しているかを示す、実務と経営の両面で活用できる重要な指標です。労働人口の減少や働き方改革が進む中では、単に人や時間を増やすのではなく、限られたリソースをどう使うかが問われています。その判断材料として、人時生産性は業務効率や収益性を可視化し、改善の方向性を示してくれます。
一方で、人時生産性は数値を出すこと自体が目的ではありません。業種特性や部門ごとの違いを踏まえて分析し、生産ロスや業務プロセスの課題、人員配置の偏りなど、改善できる要因を見極めることが重要です。また、短期的な効率だけを追いすぎると、育成や改善活動といった中長期的な成長の芽を摘んでしまう可能性もあります。
人時生産性を他の指標と併用しながら、収益性の向上と働きやすさの両立を目指すことで、持続的な経営につなげることができます。まずは自社の人時生産性を正しく把握し、現場で実行できる改善から着手してみることが、次の一歩となるでしょう。





 導入までの流れ
導入までの流れ
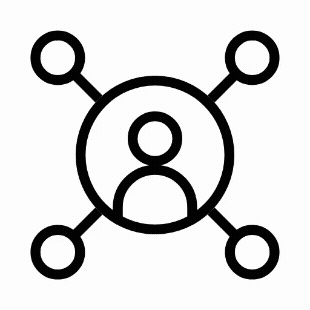
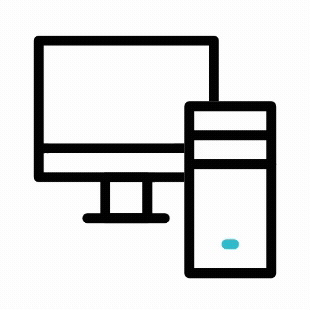

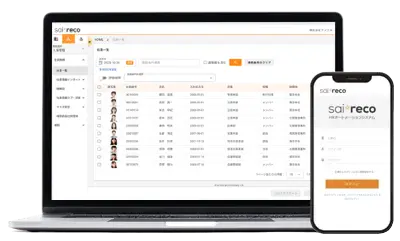



 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求