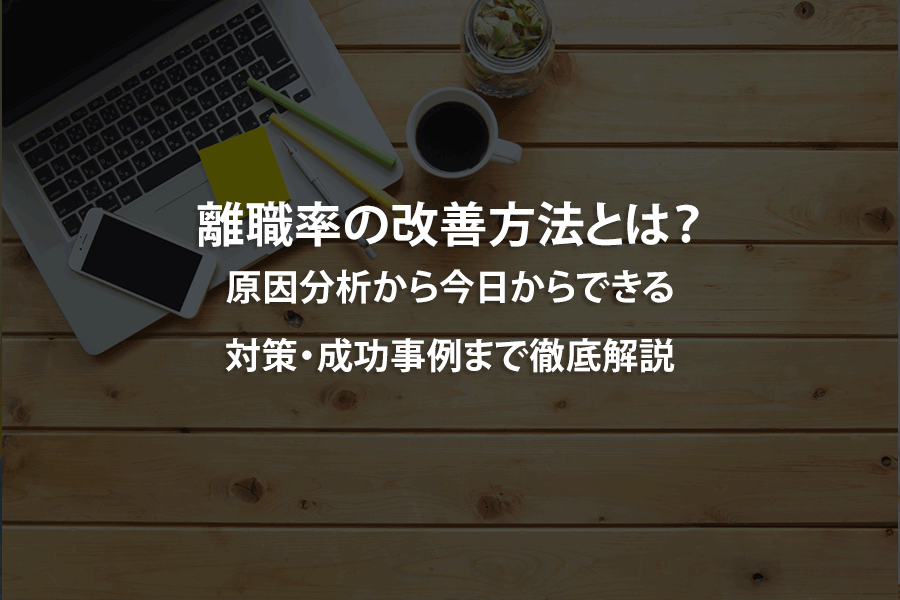
採用してもすぐに辞めてしまう、毎年のように若手が定着しない——。日本全体で人手不足が深刻化するなか、「離職率の高さ」は多くの企業に共通する悩みです。離職率が改善されないまま放置すると、採用・育成コストの増大だけでなく、既存社員の負担増加や職場の雰囲気の悪化、企業イメージの低下など、見えにくい損失が積み重なっていきます。一方で、離職の背景には労働条件、人間関係、キャリア不安など複数の要因が絡み合っており、単発の施策だけでは根本的な改善にはつながりません。
本記事では、人事・経営の立場で離職率を改善してきた実務の視点から、「なぜ離職率が高くなるのか」「どこから手をつけるべきか」「自社に合う対策の選び方」を、データと具体的施策、成功事例も交えながら体系的に解説します。
離職率とは?まずは基本の定義と計算方法をおさえる
離職率は、自社の人材マネジメントの健全性や職場環境を客観的に把握するための重要指標です。採用が難しくなる中で、離職率を正しく理解し、改善の方向性を定めることは、企業の持続的成長に欠かせません。ここではまず、離職率の基本的な定義や計算方法、見る際のポイントを整理します。
離職率の基本的な定義
離職率とは、一定期間に退職した社員数を、期初または平均在籍人数で割った指標です。一般的には、以下の式が用いられます。
離職率(%)= 期間中の退職者数 ÷ 期初在籍人数 × 100
似た指標に「退職率」や「定着率」がありますが、それぞれ意味が異なります。退職率は退職した人の割合を示す点で似ていますが、定着率は逆に「在籍している人の割合」を示します。この3つの指標を組み合わせることで、より正確に組織の状態を把握できます。
また、離職率は全社単位で見るだけではなく、新卒、中途、部署別、年齢層別などの切り口で見ると、課題の所在がより明確になります。特定の部門だけ離職率が高い、若手層が定着しないなど、問題の根本要因を探りやすくなるためです。
離職率の計算例(年次・3年以内・部門別など)
離職率の計算そのものは難しくありませんが、「どの期間」「どの母数」で計算するかによって結果は大きく変わります。以下は具体例です。
- 年間離職率の例:
期初在籍50名のうち、1年間で5名が退職した場合、離職率は「5 ÷ 50 × 100 = 10%」。 - 新卒3年以内離職率:
厚労省が公表する代表的な指標で、「入社後3年以内に辞めた人数 ÷ 同期の入社人数」で算出。 - 中途採用1年以内離職率:
採用の質やオンボーディングの課題を把握するうえで重要。
これらの指標を見る際は、自社の業界平均と比較することが有効です。ただし、業態・企業規模・働き方の違いによって離職率の「適正値」は変わるため、「平均より低いから安心」と判断するのは危険です。重要なのは、トレンド(上昇か、改善しつつあるのか)と、離職の理由の共通点を見極めることです。
指標としての限界と「質」を見る視点
離職率は便利な指標ですが、数字だけでは組織の実態を正確に表しきれません。離職率が低い企業でも、状況によっては問題を抱えているケースもあります。
- 離職率が低ければ良いとは限らない:
新陳代謝が起きず、チャレンジや成長が停滞している可能性もある。 - 「誰が辞めているのか」を見る必要:
若手ばかり辞める/管理職が続かないなどは、組織課題を示す重要なサイン。 - 離職率は単体で見るな:
エンゲージメントスコア、残業時間、有給取得率、評価データ、ストレスチェックなどと組み合わせて初めて意味を持つ。
離職率はあくまで「入口」であり、そこから原因を深掘りしていく姿勢が必要です。離職の質、退職理由の共通点、在籍者の声との比較を重ねることで、より精度の高い改善施策が打てるようになります。
なぜ離職率が高くなるのか?よくある原因と構造
狙いキーワード例:離職率 高い 原因/社員 離職 理由
離職率が高い企業には、必ず何らかの「構造的な要因」が存在します。個人の問題に見える離職であっても、背景には制度や環境、コミュニケーション、マネジメントなど、組織側の課題が潜んでいるケースが大半です。ここでは、離職率が高くなる代表的な原因を4つの観点から整理します。
労働条件・待遇への不満
離職理由として最も多く挙げられるのが、労働条件や待遇への不満です。働き方改革が進み、ワークライフバランスを重視する価値観が広がる中で、以下の点に不満を感じる社員は増加しています。
- 長時間労働、サービス残業、有休の取りにくさ
- 給与水準・昇給制度・賞与への不満
- 他社と比べて見劣りすることで転職を意識しやすくなる構造
特に給与・労働時間に関する不満は顕在化しやすく、競争力のある待遇を求めて離職するケースが多くあります。待遇への納得感が低いと、エンゲージメント低下や生産性低下にも直結するため、優先的に改善すべき領域といえます。
人間関係・ハラスメント・職場の雰囲気
離職の原因として見落とせないのが、職場の人間関係です。特に上司との関係性は、離職に大きく影響します。
- 上司との相性・マネジメントスタイルのミスマッチ
- パワハラ/セクハラ/モラハラが生み出す慢性的なストレス
- 意見が言いにくい・相談先がない職場の空気
表面化しにくい問題ですが、コミュニケーション不足や心理的安全性の欠如は、チームの雰囲気を悪化させ、静かに退職者を増やす要因になります。ハラスメント対策や管理職研修など、上司層のマネジメント力向上が離職防止に直結します。
仕事内容・キャリアパスへの不安・ミスマッチ
社員が抱える「将来への不安」も離職を引き起こす大きな要因です。特に若手社員ほどキャリア形成を重視し、会社に成長機会があるかどうかを厳しく見ています。
- 入社前の期待と現実のギャップ(リアリティショック)
- 単調作業ばかり・裁量がない・成長実感がない
- 昇進・異動・専門性のキャリアパスが見えない不安
キャリアの見通しが立たない状態が続くと、「このままでは成長できない」という不安が強まり、早期離職につながります。キャリア面談や育成計画の可視化が、離職防止の鍵となります。
採用・オンボーディングの課題
離職の多くは「入社後1年以内」に集中します。この時期の離職は、採用段階やオンボーディング(受け入れ体制)の不備が影響しているケースがほとんどです。
- 採用段階での情報不足・誇大な求人表現によるミスマッチ
- 入社直後の放置・配属先でのフォロー不足
- 「最初の半年」が離職率を左右する理由
仕事内容や働き方のリアルを伝えない採用は、期待値のズレを生み、早期離職の最大の原因になります。また、オンボーディングが不十分だと、業務理解が進まず孤立感が強まり、組織への帰属意識を失ってしまいます。
離職率改善の第一歩は、こうした構造的要因を「個人の問題ではなく、組織の課題」として捉え直し、根本から改善を進めることです。
離職率が高いと起こる5つのリスク
狙いキーワード例:離職率 高い デメリット/離職 防止 重要性
離職率の高さは、単なる人材流出にとどまらず、企業の成長・採用力・生産性に大きなダメージを与えます。特に、採用難が続く現在の労働市場では、離職率の悪化は企業の競争力低下に直結します。ここでは、離職率が高いことで発生する5つの主要リスクを整理します。
採用・教育コストの増加と投資回収の失敗
社員が早期に離職すると、採用や育成にかけた投資が回収できません。特に以下のようなコストは企業にとって重い負担となります。
- 採用単価・研修コスト・OJT工数が回収できない構造
- 「早期離職1人あたりの損失」を概算する視点
求人広告費や面接にかけた時間、入社後の研修やOJTなど、初期投資が無駄になるだけでなく、再度採用活動を行う必要があるため、コストはさらに増大します。特に1年以内の離職は投資回収がほぼ不可能で、企業に大きな財務的ダメージを与えます。
既存社員の負担増加とモチベーション低下
離職者が出ると、その空いた業務を既存社員が引き継ぐことになり、負担が急増します。その結果、現場では以下のような問題が起こりやすくなります。
- 欠員を埋めるための残業・休日出勤
- 「なぜ自分たちだけが頑張らないといけないのか」という不公平感
- これがさらに離職を生む「負のスパイラル」
負担増が続くと、疲労やストレスが蓄積し、次の離職を誘発します。この状態が続くと、組織は「退職の連鎖」という悪循環に陥り、状況はさらに深刻化します。
組織力・生産性の低下
離職が増えると、組織全体のパフォーマンスにも大きな影響が出ます。
- 顧客対応品質・納期・プロジェクト推進力への影響
- ノウハウ・暗黙知が社外へ流出してしまうリスク
特に熟練社員やキーパーソンが辞めた場合、失われるノウハウの損失は非常に大きく、短期間で代替人材を育てることは困難です。結果として、顧客満足度や生産性が低下し、事業全体の競争力低下につながります。
企業イメージ・採用力の低下
離職率の高さは、採用市場での企業イメージにも直結します。現代では口コミサイトやSNSを通じて社内の評判が求職者に広まりやすく、以下のような影響が出ます。
- 口コミサイト・SNSでの評判が採用に与える影響
- 「人がすぐ辞める会社」に応募が集まらなくなる構造
離職率が高い企業は「何か問題がある」と判断され、求職者が応募を避ける傾向があります。その結果、採用難がさらに加速し、悪循環に陥ってしまう可能性があります。
人的資本経営・ガバナンス上のリスク
近年注目されている人的資本経営の観点からも、離職率は重要な指標のひとつです。企業側には以下のような影響が生じます。
- 人的資本開示の流れのなかで、離職率が重視されつつある背景
- 投資家・金融機関からの評価に与える可能性
離職率は「人が活躍できる環境かどうか」を示す指標として、投資家・金融機関からも注目されています。離職率が高い企業は、人的資本投資の不足やマネジメント課題を疑われ、結果として企業価値や信用力が低下するリスクがあります。
このように、離職率の高さは企業に広範な影響を及ぼします。リスクを未然に防ぐためにも、早期の対策とデータに基づく改善が不可欠です。
「離職しそうなサイン」をどう見抜くか:ハイリスク社員の特徴
狙いキーワード例:離職 兆候/離職 予兆/離職率 改善 早期対応
離職を防ぐためには、社員が「辞めるかもしれない」と感じ始める初期段階で気づくことが重要です。多くの場合、社員は突然辞めるのではなく、行動や態度にゆるやかな変化が現れます。ここでは、その“予兆”を見極めるための代表的なサインを整理します。
業務へのモチベーション低下・パフォーマンスの変化
業務への意欲が下がったとき、社員の行動には明らかな変化が見られます。これらは、離職の初期サインとして最も捉えやすいポイントです。
- ミスや遅刻の増加、締切へのルーズさ
- 以前よりもチャレンジを避けるようになる
日常業務の小さな変化ですが、放置するとパフォーマンス低下が習慣化し、不満やストレスが蓄積して離職につながることがあります。問題行動として指摘する前に、背景にどんな不安があるのかを丁寧に確認することが必要です。
コミュニケーションの変化・孤立化
職場でのコミュニケーション量や態度が急に変わることも、離職の典型的なサインです。
- あいさつ・雑談・発言が目に見えて減る
- チームの飲み会や社内イベントへの不参加が増える
コミュニケーションが減る背景には、職場への不信感や孤立感、業務のストレスなどが潜んでいます。「話しかけにくい状態になっている」可能性もあるため、上司や同僚からの自然な声かけや1on1の場づくりが効果的です。
働き方の変化から見える転職活動のサイン
転職活動を始めた社員には、行動面で特徴的な変化が見られることがあります。以下は見逃せないサインです。
- 退社時間が急に早くなる・有給取得のタイミング
- 服装や身だしなみの変化、新規プロジェクトを避ける傾向
急に身だしなみが整っていたり、有給を「半日単位」で取得するケースは、面接日程のためである可能性があります。また、新規プロジェクトへの参加を避け始めるのは、辞める前提で負担を増やしたくない心境の表れです。
サインに気づいたあと「やってはいけない対応」と「すべき対応」
離職予兆を見つけた際、上司や人事がどのように対応するかで、その後の離職率は大きく変わります。特に以下のNG対応には注意が必要です。
- 引き止め一辺倒・感情的な説得は逆効果
「辞めないでほしい」と強く伝えるだけでは、本人の不満や不安を無視することになり、むしろ関係性が悪化する可能性があります。
重要なのは、本人の話を丁寧に聞き、事実ベースで状況を整理しながら支援する姿勢です。
- まずは事実ベースで話を聞く、職場要因を一緒に整理する
- 1on1やメンター制度を活用した早期フォロー
早期のフォローは離職防止に大きな効果があります。小さな不満の段階で関係構築ができれば、離職を回避できるケースは多く、「察知力」と「早期介入」が離職率改善の鍵となります。
離職率改善の第一歩:現状把握と原因分析の進め方
離職率を本質的に改善するためには、「何が原因で、どの層が、なぜ辞めているのか」を正しく把握することが不可欠です。感覚や一部の意見に左右されず、数値と現場の声の両面から分析することで、初めて効果的な改善策が導き出せます。ここでは、離職率改善の出発点となる“現状把握と原因分析”の進め方を整理します。
データで現状を把握する(数値編)
まずは客観的な数値データを整理し、自社の離職状況を可視化することから始めます。
- 全社・部門・年齢層・雇用区分ごとの離職率を可視化
- 「入社1年以内」「3年以内」など期間別の傾向を見る
- 残業時間・有休取得率・評価分布などとの相関を見る
例えば「若手だけ離職率が高い」「特定の部門だけ突出している」などの傾向が見つかれば、優先的に対策すべき領域が明確になります。また、残業時間や評価分布と離職率に相関がある場合、組織運営やマネジメントの課題が潜んでいる可能性も高く、施策設計のヒントになります。
退職者の声を構造化する(定性編)
数値データと同じくらい重要なのが「辞めた人の本音」を把握することです。
- 退職面談・退職アンケートの設計ポイント
- 本音を引き出すためのタイミング・聞き方
- 「個人の問題」と片づけず、共通パターンを抽出する
退職面談は、退職者本人の心理的負担が軽くなり、本音が出やすい退職手続き後のタイミングがおすすめです。ヒアリング内容は抽象的な「不満」ではなく、できるだけ具体的な事象に落とし込みます。複数の退職理由を集めることで「特定の上司のマネジメント」「業務量の偏り」「キャリア相談不足」などの共通点が浮かび上がり、改善の重要な手がかりになります。
在籍社員のサーベイ・エンゲージメント調査活用
離職者だけでなく、現在働いている社員の状態を把握することで、離職予備軍の早期発見につながります。
- 離職予備軍の声を早期にキャッチする仕組み
- サーベイ結果を現場の対話につなげるコツ
定期的なエンゲージメントサーベイやストレスチェックを行うことで、職場内の不満や課題が顕在化します。ただし、調査は「実施して終わり」では意味がなく、結果を上司と部下の対話につなげる運用が重要です。サーベイの点数だけではなく、記述欄の自由回答を深掘りすることで、離職兆候をより精度高く把握できます。
経営・人事・現場が共通認識を持つ場づくり
離職率改善は人事だけの仕事ではなく、組織全体で取り組むべきテーマです。そのためには、課題認識を共有する場が欠かせません。
- 分析結果を共有するミーティングの設計
- 「誰の問題か」ではなく「組織全体のテーマ」として扱う
経営・人事・現場が同じデータを見ながら議論することで、対策の優先順位や責任分担が明確になります。離職率は「現場の問題」「個人の甘え」といった個別論に落とし込むのではなく、組織の仕組みとして改善する視点を持つことが重要です。
現状把握と原因分析がしっかりできれば、施策はブレず、離職率改善の効果は格段に高まります。
離職率を改善するための具体的な施策10選
離職率の改善には、単発の取り組みではなく、組織全体に関わる包括的なアプローチが必要です。ここでは、実務で効果が確認されている具体的な施策を10項目に整理して紹介します。自社の状況に合わせて優先順位を付けながら取り組むことで、離職率改善の大きな一歩となります。
① 労働時間・負荷の適正化
- 業務棚卸し・業務の標準化・RPA/ツール活用
- 残業の見える化と、形骸化しないルールづくり
離職理由として最も多い「労働負荷の偏り」を解消するためには、業務量と働き方の見直しが不可欠です。業務棚卸しによるムリ・ムダの発見、RPAやツールによる自動化、残業時間の見える化などで、現場の負荷を構造的に削減できます。また、ノー残業デーなどの取り組みも、形骸化させない運用ルールが重要です。
② 評価・報酬制度の見直し
- 評価基準の明確化とフィードバックの仕組み
- 成果だけでなくプロセス・チャレンジも評価する設計
評価制度の不透明さは、社員の不満の大きな原因になります。評価項目・基準を明確にし、定期的にフィードバックの場を設けることで、納得度は大幅に向上します。また、短期的な成果だけでなく、学習姿勢や挑戦行動を評価する仕組みは、長期的な成長と定着を促すポイントです。
③ コミュニケーション活性化と1on1ミーティング
- 上司と部下の定期対話/心理的安全性を高める問いかけ
- 社内イベントや社内SNSなど、雑談・感謝を可視化する仕組み
離職予防において、コミュニケーションは最も効果的な施策のひとつです。1on1ミーティングでは、業務の相談だけでなく、不安やキャリアの希望を聞き出す対話が重要です。また、社内SNSや表彰制度など、感謝や成果が可視化される仕組みは、職場の一体感につながります。
④ キャリア支援・社内公募・ジョブローテーション
- キャリア面談・スキルマップの活用
- 「社内転職」の選択肢を開いておく重要性
キャリアの行き詰まりは、離職に直結する要因です。半年〜1年に一度のキャリア面談やスキルマップの作成により、社員の将来像を具体化します。また、社内公募制度やジョブローテーションを導入することで、「この会社で別のキャリアを描くことができる」という安心感を提供できます。
⑤ 研修・学習機会の設計(若手〜管理職まで)
- 若手向けオンボーディング研修・メンター制度
- 管理職向けマネジメント・ハラスメント研修の強化
若手社員には、仕事の基礎を身につけるオンボーディング研修や、相談相手となるメンター制度が有効です。一方、離職理由として多い「上司との関係性」には、管理職のマネジメントスキルが大きく影響するため、フィードバック・1on1・ハラスメント防止の研修が必要です。
⑥ 採用段階でのミスマッチ防止(リアリスティック・ジョブ・プレビュー)
- 仕事内容・残業・評価のリアルを伝える
- インターン・職場見学・先輩社員座談会の活用
採用段階の情報不足は、早期離職の最大の原因です。仕事内容や働き方の「良い点・大変な点」を正直に伝えるリアリスティック・ジョブ・プレビュー(RJP)は定着率向上の効果が高いとされます。会社の雰囲気を感じられるインターンや座談会も、ミスマッチ防止に役立ちます。
⑦ 福利厚生・柔軟な働き方(テレワーク/時短/副業容認など)
- 育児・介護などライフイベントとの両立支援
- 社員アンケートに基づく福利厚生の取捨選択
働き方の柔軟性は、離職防止に直接つながる重要な要素です。育児・介護・通院などの生活事情に合わせた働き方が可能になると、ライフステージの変化による離職を大幅に減らせます。また、福利厚生は「なんとなく導入する」のではなく、社員アンケートを基に効果的な項目に集中させることがポイントです。
⑧ オンボーディングの強化(入社〜半年の設計)
- 初日のウェルカム体験〜3ヶ月のフォロー面談
- 「誰が・いつ・何を伝えるか」を可視化したオンボーディングマップ
早期離職の多くは「入社半年以内」に発生します。オンボーディングを丁寧に設計することで、社員が組織に馴染み、早期活躍しやすくなります。初日のウェルカム体験で安心感を与え、1ヶ月・3ヶ月の節目にフォロー面談を実施することで、ミスマッチや不安を早期に解消できます。
⑨ 離職防止ツール・エンゲージメントサーベイの活用
- 定期サーベイ・ストレスチェック・ピアボーナスなど
- ツール導入を「調査で終わらせない」運用のポイント
サーベイツールは、社員の状態を見える化する強力な手段です。しかし、「スコアが出ただけで終わる」ケースが多く見受けられます。重要なのは、結果を現場で話し合い、改善アクションにつなげること。ピアボーナスのような仕組みは、職場の感謝を活性化し、日常のエンゲージメント向上に寄与します。
⑩ 経営トップからのメッセージと文化づくり
- 「人を大切にする」姿勢を制度と行動で示す
- 失敗や相談を歓迎する文化づくりが離職率改善に直結する理由
離職率改善の最終的な鍵を握るのは「企業文化」です。経営トップが明確にメッセージを発信し、心理的安全性のある職場づくりを進めることで、社員は挑戦しやすくなり、離職意向も低くなります。相談しやすい雰囲気や、失敗を許容する文化は、長期定着を促す土台となります。
これら10の施策を組み合わせることで、組織全体のエンゲージメントが高まり、離職率の継続的な改善につながります。
【成功事例】離職率を大きく改善した企業の取り組み
離職率改善の取り組みは企業ごとに異なりますが、成功企業には明確な共通点があります。ここでは、実際に離職率を大幅に改善した企業の取り組みを3つ取り上げ、最後に共通の成功要因をまとめます。
事例1|柔軟な働き方と制度への社員参画で離職率を4%台に
- 在宅・時短・フレックスなど、多様な働き方を認めた背景
- 人事制度づくりに社員が参加するプロセス
- 「自分の働き方は自分で決める」文化が定着率に与えた影響
柔軟な働き方を認める企業は増えていますが、その成功の鍵は「制度の導入」だけでなく「社員自身の参画」にあります。働き方を社員が自ら提案できる仕組みを整備したことで、自律性が高まり、働きがいと定着率が向上しました。特に、リモートワークやフレックスを組み合わせた働き方を個人ごとに最適化したことが離職率4%台という高い改善結果につながりました。
事例2|新入社員指導制度と育児・介護支援で早期離職が大幅減
- 入社直後〜半年間のメンタル・スキル両面のフォロー
- 産休・育休・短時間勤務などの拡充と職場復帰支援
- 「辞める前に相談できる」関係性づくりのポイント
新入社員の早期離職を大幅に改善した企業では、入社直後の不安を取り除くために指導員制度を導入し、メンタルと業務スキルの双方をフォローしています。また、育児・介護との両立支援制度を手厚く整えることで、ライフステージの変化による離職も減少。「相談しやすさ」を担保するために上司や先輩との定期面談を実施するなど、心理的安全性の高い職場づくりが成功の鍵でした。
事例3|メンター制度とチャレンジ評価で3年以内離職率ゼロに
- メンター指名制・若手の挑戦を後押しする評価
- 社内プロジェクト参加を通じたエンゲージメント向上
- 「手を挙げれば任せてもらえる」環境が若手定着に与える効果
若手の離職が多かった企業が3年以内離職率ゼロを達成した要因は、「挑戦を歓迎する文化」づくりでした。若手が自分でメンターを選べる制度を導入し、プロジェクトへの参加機会を積極的に提供したことで、成長実感が向上。さらに、挑戦行動を評価する制度を整備したことで、若手が安心して挑戦できる環境となり、高い定着につながっています。
事例から見える共通点
- 制度だけでなく運用・対話に力を入れている
- 管理職のマネジメント強化と、経営トップのコミットメント
- 「自社にそのまま真似できるポイント」はどこかを示す
どの事例も「制度そのもの」よりも「運用」に力を入れている点が共通しています。また、管理職のマネジメント力向上や経営トップの明確なコミットメントが、離職率改善の成功を後押ししています。自社に取り入れられる要素を見極め、できる範囲から着実に実行することが、離職率改善の第一歩となります。
離職率改善を“やりっぱなし”にしないためのKPIとPDCA
離職率改善は一度施策を導入して終わりではなく、確実に効果検証し、改善を繰り返すことが重要です。本章では、離職率改善の成果を測るためのKPI設定と、施策を継続的にアップデートするPDCA運用のポイントを整理します。
設定すべきKPIの例
- 離職率(全社・部門・年齢層・入社年次別)
- エンゲージメントスコア・サーベイ結果
- 残業時間・有休取得率・1on1実施率など行動指標
離職率だけに依存した評価では、表面的な変化しか捉えられません。エンゲージメント、働き方、面談などのプロセス指標を合わせて測定することで、「離職につながる予兆」を早期にキャッチできます。また、部門別・年齢層別・入社年次別に分けることで、課題の所在がより明確になります。
短期・中期・長期で見るべき指標
- 短期:オンボーディング満足度・面談実施率など
- 中期:1〜3年の定着率・評価分布の変化
- 長期:離職率トレンド・採用力・企業イメージの変化
離職率改善には、「すぐに数字が動く指標」と「数年かけて変化する指標」の両方があります。短期ではオンボーディングや1on1の実行度をチェックし、中期では実際の定着率や評価の偏りが是正されているかを確認。長期では、離職率トレンドや採用力、口コミの変化など、企業ブランドの強化につながっているかを見ていきます。
人事だけに任せない「全社で回すPDCA」
- 施策→データ→現場の声→施策見直しのサイクル
- 経営会議・マネジャーミーティングでの定例レビュー
離職率改善は、人事部だけが取り組むテーマではありません。現場のマネジャー、経営層、現場社員が連携し、施策の成果と課題を共有する必要があります。サーベイ結果や離職データをもとに、現場での対話を行い、経営会議・マネジャーミーティングで定期レビューすることで、組織全体で改善のPDCAが回り続けます。
こうした「短期KPI × 長期視点 × 全社PDCA」の組み合わせこそが、離職率改善を“やりっぱなし”にしないための鍵となります。
中小企業・ベンチャーが離職率を改善するための現実的ステップ
大企業と比べて予算や人員が限られる中小企業・ベンチャーにとって、離職率改善は「背伸びしすぎない現実的なステップ設計」が重要です。本章では、まず取り組むべき最初の一歩から、中長期で進める改善プロセスまでを整理します。
限られた予算でもできる「まず1年目の打ち手」
- 退職理由のヒアリングとオンボーディング見直し
- 1on1・メンター制度など、低コスト施策から始める
中小企業で最も効果が出やすいのは、まず「退職理由の把握」と「入社初期の支援強化」です。退職者へのヒアリングを仕組み化するだけでも、離職の原因が可視化され、改善の方向性が見えます。また、1on1面談やメンター制度はコストをかけずに心理的安全性を高められるため、特に最初の1年で取り組む価値の高い施策です。
すべてを一度に変えようとしない
- 3つの優先課題に絞る考え方
- 小さな成功事例を社内に共有していく重要性
離職率改善は範囲が広く、すべてに手をつけようとすると途中で止まってしまうことがよくあります。「3つの優先課題に絞る」「まずは小さな成功事例をつくる」という進め方が現実的です。たとえば、残業削減・オンボーディング見直し・評価制度改善の3つに絞り、改善できた事例を社内で共有することで、組織全体の協力を得やすくなります。
外部サービス・専門家の活用も選択肢に
- 研修・サーベイ・制度設計などの外部リソース
- 「自社だけで抱え込まない」ことがスピードにつながる
中小企業は人事機能が限定的なことが多く、すべてを自社で完結させるのは困難です。研修やサーベイ、人事制度設計は外部サービスを活用した方がスピードも質も向上します。専門家の知見を取り入れることで、「何から始めればいいかわからない」という停滞を防ぎ、実行フェーズまで短期間で進めることができます。
これらのステップを組み合わせることで、中小企業でも無理なく離職率改善を実現し、定着率の高い組織づくりにつなげることができます。
まとめ|離職率改善は「仕組み × 対話 × 現場運用」の総合戦略
離職率の改善は、一部の制度を整えるだけでは実現できません。労働条件・人間関係・評価制度・キャリア支援など、複数の要因が複雑に絡み合って離職は発生します。そのため、まずは現状を「正しく把握する」ことが出発点です。退職理由のヒアリング、離職率の分解、エンゲージメントサーベイなどを組み合わせることで、自社が取り組むべき優先領域が明確になります。
施策を実行する際は、一度に全てを変えようとせず、「オンボーディング強化」「1on1の仕組み化」「評価制度の透明化」など、効果の出やすい領域から着実に進めることが重要です。また、導入した施策を“やりっぱなし”にせず、KPIでモニタリングし、現場の声を踏まえながらPDCAを回すことで、改善が定着していきます。
成功企業に共通するのは、「制度よりも運用」「現場との対話」「トップのコミットメント」です。離職率の改善は、採用競争力の向上・組織力の強化・人的資本経営への対応など、多くのメリットをもたらします。自社の状況に合わせて、まずは小さな一歩から離職防止に取り組んでみてください。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求