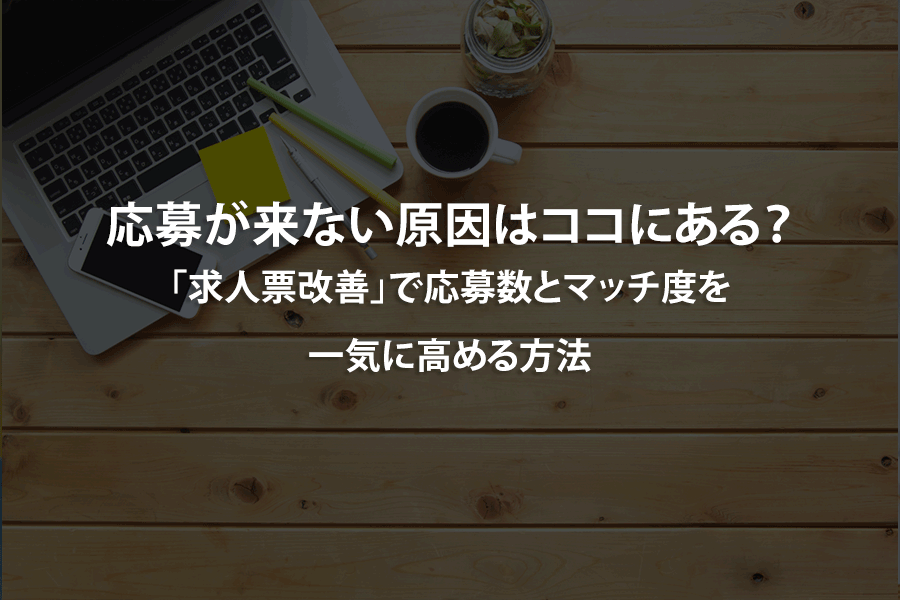
「求人広告を出しても応募がほとんど来ない」「来てもターゲットと違う層ばかり」──その原因は、給与や待遇だけでなく“求人票の中身”にあるかもしれません。人材不足が続く今、求職者は膨大な求人情報の中から、自分に合いそうな求人だけを素早く選び取っています。つまり、求人票をどう設計し、どのように改善していくかが、採用成功を大きく左右します。本記事では、採用支援・人事実務の現場で蓄積されたノウハウと最新の転職市場の傾向をもとに、「求人票改善」の考え方と具体的な見直しポイントを整理します。募集要件の決め方から、必須条件・歓迎条件・ヒューマンスキルの書き分け方、画像・表現の工夫、応募者の声とデータを使ったPDCAの回し方まで、今日から実践できる改善ステップを詳しく解説します。
なぜ今「求人票の改善」が必要なのか
応募が来ない・いい人が集まらない原因の多くは求人票にある
「応募が来ないのは、うちの給与水準や知名度が低いからだ」と考えてしまいがちですが、 原因の多くは求人票の見せ方や情報量・具体性の不足にあります。 同じ条件でも、求人票を改善することで応募数やマッチ度が大きく変わるケースは少なくありません。 求人 票 改善 に取り組むことは、「求職者にとって分かりやすく魅力的な情報設計に変えること」と言い換えることができます。
- 「給与が低いから」だけではなく、求人票の構成・表現・情報量が原因になっていることが多い
- 参考記事の「応募が集まらないのは求人のせい?」が示すように、まずは求人票の中身を疑う視点が重要
人手不足・採用難の時代に求人票が果たす役割
慢性的な人手不足・採用難が続くなかで、求人票は単なる募集要項ではなく、 候補者との「最初の接点」であり、一次面接の代わりとなる重要なコンテンツです。 短いテキストの中で、「どんな仕事か」「どんな人を求めているか」「どんな環境なのか」を具体的に伝えられているかで、 採用の成果が大きく分かれます。 また、求人票は自社の価値観やカルチャーを伝える場でもあり、中長期的には採用ブランディングにもつながります。
- 求人票は候補者との「最初の接点」「一次面接の代わり」としての役割を持つ
- 仕事内容だけでなく、自社の考え方や雰囲気を伝えることで採用ブランディングにもつながる
求人票改善で期待できる3つの効果
求人票を計画的に見直し・改善していくことで、採用活動全体にポジティブな変化が生まれます。 単に応募数が増えるだけでなく、「自社に合う人」に応募してもらいやすくなり、 結果として定着や活躍にも良い影響を与えます。
- 応募数UP(母集団形成)
ターゲットに刺さる表現に変えることで、検索結果からのクリックや応募数が増加する。 - ミスマッチ・早期離職の減少
仕事内容・求める人物像を具体化することで、入社後のギャップが減り、定着率が高まる。 - 採用工数・選考のムダ削減
「来てほしい人」からの応募が増えることで、選考のやり直しや不採用対応の工数が減り、採用活動が効率化される。
まず現状把握から:求人票改善のためのセルフチェックリスト
求人票の改善は、まず「現状のどこに課題があるか」を可視化することから始まります。
以下のチェック項目は、求人票 見直し に取り組む際に必ず確認しておきたい基本ポイントです。
曖昧な表現や情報不足は、求職者の不安やミスマッチにつながり、応募率を大きく下げてしまいます。
まずは、現在の求人票が求職者目線で分かりやすく、魅力が伝わる内容になっているかをチェックしてみましょう。
ターゲットがあいまいな求人票になっていないか
求人票改善の第一歩は、「誰に応募してほしいのか」を明確にしているかどうかです。
ターゲットが曖昧なままだと、求人票の内容も抽象的になり、結果として応募者の質と量が安定しません。
- 文章から「誰に向けた求人なのか」が読み取れるか?
- 年齢・経験・働き方の志向など、求める人物像の前提が整理されているか?
募集要件・必須条件・歓迎条件がごちゃ混ぜになっていないか
応募者に誤解を与える代表例が、要件の混在です。
「とりあえず入れておこう」という条件が多いほど、応募のハードルは不必要に高くなり、優秀層も離れていきます。
- 必須と歓迎の区別が曖昧になっていないか?
- 「一応入れておく条件」が多すぎて応募者を狭めていないか?
仕事内容や働き方が具体的にイメージできるか
仕事内容が抽象的な表現ばかりだと、求職者は自分が働く姿を想像できません。
求人票改善 の基本は、行動レベルで仕事内容を具体化することです。
▶ 悪い例(抽象的)
・「営業活動全般をお任せします」
・「コミュニケーション能力を活かせます」
▶ 良い例(具体的)
・「既存顧客への定期訪問(1日3〜5件)、提案資料の作成、問い合わせ対応が中心です」
・「社内外の関係者と日程調整し、業務を円滑に進める調整業務が多く発生します」
- 仕事内容が具体的で、1日の流れや関わる人がイメージできるか?
- 求職者が「自分でもできそう」「興味がある」と思える情報が入っているか?
自社らしさ・魅力が十分に伝わっているか
求人票は、仕事内容だけを書く場所ではありません。
求職者は、「どんな環境で働けるのか」「どんな人がいるのか」「成長できるのか」など、自分の未来を重ね合わせて判断します。
だからこそ、自社ならではの魅力や特徴を盛り込むことが重要です。
- 福利厚生・社風・働く環境についての情報が不足していないか?
- 社員の雰囲気・成長機会・チーム体制など、自社らしさを伝えられているか?
ペルソナ設計とターゲット明確化:「誰に向けた求人票か」を決める
求人票改善の効果を最大化するためには、「誰に向けて書くのか」を明確にすることが欠かせません。
採用ペルソナ(ターゲット設計)を行うことで、文章・条件・画像・訴求ポイントすべてに一貫性が生まれ、応募の質と量が大きく変わります。
ここでは、ターゲット設定の基本ステップをまとめます。
現場・人事・経営で「求める人物像」をすり合わせる
参考記事でも指摘されている通り、「求める人物像が社内で共有されていない」ことは求人票の質を大きく下げる要因です。
現場・人事・経営陣それぞれが異なるイメージを持っていると、求人票は抽象的で伝わりにくいものになり、ミスマッチも起こりやすくなります。
そのため、まずは社内の関係者で目線を揃えるプロセスが必要です。
打ち合わせで確認すべき5つの質問例
- このポジションで「絶対に必要な経験・スキル」は何か?
- 逆に、「入社後の研修で補えるもの」は何か?
- 現場が「一緒に働きたい」と思う人物像はどんな人か?
- 過去に早期離職した人の特徴・原因は何か?
- この部署や職種で活躍している人の共通点は何か?
年齢・属性・転職理由・働き方の希望まで落とし込むペルソナ設計
採用ペルソナは、ただ「20〜30代の女性」などの表面的な分類では不十分です。
より具体的な属性や行動背景まで落とし込むことで、求人票の訴求ポイントが明確になり、求職者に“刺さる”内容に変わります。
深掘りすべき項目の例
- 属性:主婦/学生/若手社会人/第二新卒 など
- 転職理由:スキルアップ/働き方改善/キャリア変更 など
- 働き方のニーズ:リモート希望、柔軟な時間帯、ワークライフバランス重視
- 価値観:安定志向・挑戦志向・人間関係重視 など
例えば同じ「20〜30代女性」でも、主婦と若手会社員では求める条件も魅力に感じるポイントも大きく異なります。
このレベルまで具体化されたペルソナを元に求人票を書くことで、よりマッチ度の高い応募を集めることができます。
理想の人物像は“社内のモデル社員”から逆算する
「どんな人が活躍しているのか」は、最も信頼できるペルソナ設計の材料です。
実際に成果を上げている社員を参考にすることで、机上の空論ではなく、実際の職場に合った人物像を設定できます。
“○○さんのような人を採りたい”を言語化するステップ
- その社員のキャリア背景(前職・経験年数)
- 転職理由や入社の決め手
- 日々の働き方・仕事への姿勢
- どんなヒューマンスキルを発揮しているか
- チームとの関わり方・価値観
これらをヒアリングすることで、求人票に落とし込むべき必須条件・歓迎条件・求める人物像を具体的に表現できるようになります。
実在するモデル社員を基準にすることで、入社後の定着率や活躍度も高まりやすくなります。
必須条件・歓迎条件・ヒューマンスキルの整理と書き方
求人票の質を大きく左右するのが、必須条件・歓迎条件・ヒューマンスキルの書き分けです。
求職者の応募判断に直結する部分であり、ここを誤ると「応募が来ない」「ミスマッチが増える」といった問題が起こります。
ここでは、募集要件 見直し の際に必ず押さえるべきポイントをまとめます。
応募を減らすNGな必須条件の典型パターン
必須条件は「この条件がないと業務が成り立たない」ものに限定すべきですが、実際には“なんとなく”設定されている必須条件が多く見られます。
これらは応募の間口を狭めるだけでなく、優秀層ほど慎重に応募を避ける原因になります。
- 「中途だからとりあえず経験3年以上」
- 「業界経験者のみ」「宅建必須」など、本質的でない“慣習条件”
優秀層ほど応募を避ける理由
- 条件が多いほど「自分は満たしていないかもしれない」と判断されやすい
- 曖昧な条件=職場が整備されていない可能性、と警戒される
- 本質を捉えていない必須条件は、“雑な採用”の印象を与える
「絶対に必要」な必須条件に絞り込むステップ
必須条件を正しく整理するには、業務の棚卸が不可欠です。
目安として「これが無いと業務が全く成り立たないか」を基準に、条件を絞り込みます。
必須条件の整理ステップ
- 1.業務の棚卸を行い、必要なスキルを洗い出す
- 2.「即戦力でないと成り立たない業務」は何かを判定
- 3.教育・研修で補えるスキルは必須条件に含めない
- 4.他のスキルで代替可能な要素は歓迎条件に回す
必須条件を整理すると、待遇とのバランスも調整しやすくなり、現実的で魅力的な求人票になります。
歓迎条件は3つ以内に絞り、“壁”ではなく“後押し”にする
歓迎条件は本来「あると嬉しい」程度の項目ですが、書き方によっては求職者に“応募の壁”として誤解されることがあります。
歓迎条件は多くても3つ以内に絞り、応募を後押しする表現に整えることが重要です。
歓迎条件が実質必須に見えるNG例
- 「営業経験豊富な方歓迎」→本当に未経験でも良いのか不安にさせる
- 「資格を複数保有している方歓迎」→応募対象が狭く見える
良い例(参考記事のBefore/Afterを踏まえた書き換え例)
- 「法人営業の経験がある方は、既存顧客との提案業務で早期に活躍できます」
- 「簿記資格をお持ちの方、もしくは勉強中の方も歓迎します」
- 「販売職や内勤営業から営業にチャレンジしたい方も歓迎しています」
“なぜそのスキルを歓迎するのか”を添えるだけで、一気に応募意欲が高まり、安心感のある求人票になります。
ヒューマンスキルは抽象語ではなく「行動」で書く
ヒューマンスキルは採用後の定着・活躍に直結しますが、抽象的な言葉(例:コミュニケーション能力、主体性)だけでは判断基準になりません。
求めるヒューマンスキルは、行動レベルに落とし込んで表現することが重要です。
抽象語 → 行動レベルの良い変換例
- 「コミュニケーション能力」
→「社内外の関係者と調整し、スケジュールをまとめた経験」 - 「主体性がある方」
→「課題を見つけ、上司に提案して改善した経験」 - 「粘り強さ」
→「困難な状況でも落ち着いて最後まで業務を完遂した経験」
職種別・役割別に求めるヒューマンスキルを整理する観点
- 営業職:顧客志向、交渉力、数字へのコミット
- マーケティング職:分析力、仮説思考、クリエイティブ性
- 管理部門:正確性、調整力、情報整理力
- リーダー職:決断力、チームマネジメント、巻き込み力
このように“行動で示せる表現”にすることで、選考基準が明確になり、応募者にも伝わりやすい求人票になります。
求職者目線で伝わる求人票のフォーマットとライティング
求人票を書き直す際は、単に文章を整えるだけでは不十分です。
求職者がスムーズに情報を理解し、自分に合う仕事かどうかを判断できるよう、項目の役割に沿った情報整理とライティングが必要です。
ここでは、求人票 書き方 の基本構成と改善の具体ポイントを整理します。
各項目の役割を理解して、情報を整理する
求人票にはそれぞれの項目に「何を書くべきか」が明確に決まっています。
役割を理解し正しい情報を配置することで、読みやすく、誤解のない求人票になります。
主な項目の例
- 募集職種名
- 仕事内容
- 勤務地
- 給与
- 勤務時間
- 休日・休暇
- 福利厚生
- 求める人物像(必須条件/歓迎条件)
ポイント:どの情報をどこに書くべきか
- 仕事内容に福利厚生を書かない
- 求める人物像は行動ベースで整理してまとめる
- 勤務地は住所だけでなく「最寄り駅・アクセス」を明記
参考記事で紹介されているフォーマットを応用し、各項目の目的に沿って情報を配置することで、 求職者から見た読みやすさが大幅に向上します。
求人コピー・冒頭リードで「読み進めたくなる一文」をつくる
求人票の冒頭は、求職者の「読む/読まない」を決める最重要ポイントです。
強みが一目で伝わる一文を置くことで、クリック率・応募率が大きく変わります。
▼ Before(よくあるNG例)
「当社では営業職を募集しています。未経験の方も歓迎です。」
▼ After(改善例)
「未経験からでも安心して挑戦できる研修制度あり/リモートワーク併用OK。若手が活躍中の営業職です。」
ポイント
- 「未経験OK」「リモート可」「残業少なめ」など強みを冒頭に
- ターゲットが求めるメリットを先に提示する
- 検索で“引っかかりやすい”キーワードを自然に配置
仕事内容は“1日の流れ”や“関わる人”まで具体的に描写する
仕事内容の項目は、求職者が「自分が働く姿をイメージできるか」を判断する最重要エリアです。
抽象的な説明では不安を与えてしまうため、1日の流れや関わるチーム・顧客との関係まで踏み込んで記載するのが効果的です。
NG例(抽象的)
「営業活動全般をお任せします。」
改善例(具体的)
「既存顧客への定期訪問(1日3〜5件)、案件提案、問い合わせ対応が中心。提案資料はテンプレートを活用できます。」
- どんな業務をどのくらいの頻度で行うか
- どんな人と関わるか(社内/社外)
- 入社後すぐに任される仕事/徐々に任される仕事の違い
これらを盛り込むことで、安心感とリアリティのある求人票に変わります。
給与・休日・働き方の情報は“比較される前提”で見せる
求職者は複数の求人を比較して応募します。
そのため、給与・休日・働き方の項目は、他社と比較される前提で具体的に書く必要があります。
給与の改善例
- 「月給◯円〜」だけでなく、想定年収・年収モデルを書く
- 昇給例や評価制度に触れる
働き方の改善例
- オンライン面接可
- リモートワーク/ハイブリッドワークの比率
- フレックス制度の有無
こうした時流キーワードを自然に入れることで、検索結果から見つけてもらいやすくなり、求人票 改善 の効果が高まります。
画像・ビジュアルで差がつく求人票改善
求人票は文章だけで伝えるものではありません。
画像・ビジュアルは求職者の第一印象を決める重要な要素であり、職場の雰囲気や働くイメージを一瞬で伝える力があります。
ここでは、求人 画像 を使った効果的な求人票改善のポイントを整理します。
メイン画像で「この会社で働く自分」を一瞬で想像させる
求職者が最初に目にするメイン画像は、求人票全体の印象を大きく左右します。
参考記事でも紹介されているように、「ポジティブな印象を与える画像」を使用することが非常に重要です。
ポジティブな印象を与える画像の条件
- 明るい雰囲気・自然な表情の写真である
- 職場の雰囲気がリアルに伝わる
- 応募者が「働いている姿」をイメージしやすい構図になっている
- 清潔感・組織の安心感を与える
実際の職場写真 vs フリー素材のメリット・デメリット
- 実際の職場写真
・リアリティが高い/入社後のギャップが少ない
・自社らしさ(雰囲気・働く人)が伝わる
・撮影コストがかかる場合がある - フリー素材
・手軽で見栄えが良い
・撮影の労力が不要
・実態とズレると不信感につながる
可能であればリアルな職場写真を使うのが理想ですが、フリー素材を使う場合でも「実態に近いイメージ」を選ぶことが大切です。
サブ画像で職場の雰囲気・商品・オフィス環境を補足する
メイン画像だけでは伝えきれない情報は、サブ画像で補完します。
求職者が「どんな環境で働くのか」「どんな人と働くのか」をイメージしやすい画像を選ぶことがポイントです。
求人票に使うべきサブ画像の例
- 従業員の笑顔・仕事中の様子
- 商品・サービスの写真
- オフィスの外観・内観
- イベント・社内交流の様子
ターゲット別に刺さる画像の違い
- 若手層向け:明るい雰囲気、活気があるチーム写真、研修風景
- 子育て世代向け:落ち着いた職場、働きやすい環境、柔軟な働き方をイメージできる写真
- 専門職向け:業務の様子、使用するツールの画像、プロとして働く姿
ターゲットに合わせて「求められる安心感」「刺さるポイント」が異なるため、画像選びはペルソナとセットで考えるのが効果的です。
NG例と注意点:実態とズレた画像は逆効果
どれだけ写真が美しくても、実態とズレた画像は採用後の“入社後ギャップ”を生み、早期離職の原因になるため注意が必要です。
入社後ギャップを生むNGな画像の特徴
- フリー素材感が強く、実際とは異なる雰囲気に見える
- オフィスが実際よりも広く明るいように見える加工写真
- 実際には存在しないチーム編成や仕事内容を想像させる構図
自社の実情に合った写真を撮るための簡易チェックリスト
- 実際のオフィス・現場で撮影したか?
- 従業員の自然な表情・動きを写せているか?
- 嘘や誤解を生むような演出・加工を避けているか?
- ターゲットが不安を感じない雰囲気が伝わっているか?
画像の改善は求人票全体の印象を大きく変えるため、ぜひ優先度高く取り組んでみてください。
応募者の声とデータを活かした求人票改善のPDCA
求人票の改善は、一度作って終わりではありません。
求職者の反応や応募データを分析しながら、継続的にブラッシュアップしていくPDCAが重要です。
ここでは、面接でのヒアリング・アクセス分析・改善サイクルの回し方をまとめます。
面接で必ず聞きたい「どこに魅力を感じて応募したか」
参考記事でも紹介されているように、応募者の“生の声”は求人票改善の宝の山です。
面接時に数分で確認できる内容でも、求人票の改善ポイントが鮮明になります。
聞くべき質問例
- 求人票のどの部分が印象に残りましたか?
- 応募の決め手になった情報はどこでしたか?
- 逆に、わかりにくかった部分はありますか?
- 他社と比較して魅力的だった点はありますか?
メモの取り方のポイント
- 抽象的な回答ではなく、具体的な言葉をそのまま記録する
- 複数の応募者が共通して挙げるポイントを優先的に改善
- 面接官ごとに記録フォーマットを統一する
応募者が求めている情報と、企業が伝えたい情報が一致しているかどうかを確認することで、 求人票 改善 に直結するヒントが得られます。
アクセス数・応募率・採用率から“詰まっている場所”を特定する
求人票のどこに課題があるかは、データを見ると明確になります。
特に重要なのは、アクセス数・応募率・採用率の3点です。
よくあるパターン
- ① アクセスはあるが応募が少ない
→ タイトル・求人コピー・画像・必須条件が原因 - ② 応募はあるが採用に至らない
→ 必須条件の設定ミス、仕事内容が抽象的、ミスマッチ発生 - ③ アクセス自体が少ない
→ キーワード・求人タイトル・カテゴリ設定の見直しが必要
数値ベースで改善テーマを決める方法
- アクセス → タイトル/画像/冒頭コピーを改善
- 応募 → 必須条件/歓迎条件/仕事内容の具体化を改善
- 採用 → 求める人物像の精度、面接プロセスを改善
直感ではなくデータに基づき改善ポイントを特定することで、採用KPIの改善速度が大きく上がります。
週1〜2回の小さな見直しで“常に最新の求人票”にする
参考記事にもあるように、HR Forceでは週2回以上の求人見直しを実施しています。
小まめな更新は、求職者のニーズ変化や市場のトレンドに迅速に対応するために非常に効果的です。
見直し項目の優先順位
- 1. タイトル(検索の入り口になる最重要項目)
- 2. 求人コピー(読み進めてもらえるかが決まる)
- 3. 必須条件の精査(厳しすぎて応募が減っていないか)
- 4. 画像(メイン/サブ)(視覚印象を刷新)
- 5. 仕事内容の具体化(安心感の向上)
特に市場トレンド(リモートワーク、オンライン面接、若手ニーズなど)は変動が激しいため、
最新情報に合わせて求人票をアップデートすることで応募が増えるケースは非常に多いです。
「毎週少しずつ直す」ことで、常に“今の求職者に刺さる求人票”を保つことができ、
採用活動全体の効率化にもつながります。
中小企業・一人採用担当でもできる求人票改善ステップ
中小企業や「ひとり人事」の環境では、求人票を改善したくても
「時間がない」「社内調整が難しい」「どこから手をつけるべきかわからない」
といった課題がつきまといます。
ここでは、限られたリソースでも実践できる現実的な求人票 改善 手順をまとめます。
社内調整をスムーズにするための合意形成の進め方
求人票は「現場」「人事」「経営」それぞれが関わるため、意見がぶつかりやすい領域です。
特に中小企業では、役割が重複しているケースも多く、合意形成の難しさがボトルネックになります。
現場・人事・経営の意見がぶつかる典型パターン
- 現場:「即戦力が欲しい」「業界経験者に絞りたい」
- 人事:「応募が来ないから、間口を広げたい」
- 経営:「長期的に育てられる人材」「カルチャーに合う人が良い」
これらが平行線のままでは、求人票が“誰にも刺さらない内容”になってしまいます。
「理想論」ではなく「現実的な落としどころ」を決めるコツ
- ① 必須条件は「絶対に必要な1〜2項目」に絞る
- ②「本音」と「建前」の優先順位を分けて事前共有する
- ③ 現場と人事で「採用成功ライン」を明確化する(例:経験者に限らない)
- ④ 論点は感情ではなく“データ”に基づいて整理する
合意形成ができると求人票の方向性がブレにくくなり、
ひとり人事でも求人改善がスムーズに回るようになります。
時間がなくてもできる「まず3つだけ直す」求人票改善
一人採用担当のよくある悩みが、「時間がなくてすべて直せない」というもの。
そんなときは、まず3つの改善ポイントだけに集中します。
① タイトル・職種名(検索とクリック率に直結)
- 例:悪い →「営業スタッフ募集」
- 例:良い →「未経験OK|研修充実|ルート営業|残業少なめ」
② 必須条件(応募のハードルを左右)
- “なんとなく必須”を削る
- 教育で補える要素は歓迎条件へ
③ 仕事内容の具体化(安心感を与える)
- 抽象表現 → 「顧客対応をお任せします」
- 具体表現 → 「問い合わせ対応(1日5〜10件)/簡単な資料作成/社内調整」
この3点を整えるだけで応募率が大きく改善するケースは非常に多く、
既存求人をゼロから作り直す必要もありません。
AI・外部サービスを使って求人票をブラッシュアップする
中小企業やひとり人事にとって、AIやHRテックサービスは強力な味方です。
AIO(AI最適化)の観点から、AIをうまく活用することで求人票改善のスピードが段違いに上がります。
AIO視点:AIに叩き台を作らせ、人事・現場がチェック・修正する流れ
- ① 現場・人事で「求める人物像」を入力
- ② AIに初稿(草案)を作成させる
- ③ 必須条件・仕事内容を人事と現場が微調整
- ④ 画像・コピーもAIで複数案を生成し比較する
これにより、ゼロから文章を作る負担がなくなり、
短時間で質の高い求人票が完成します。
転職サイト・HRテックのフォーマットを参考にするメリット
- 大手サイトは「求職者が読みやすい構成」が完成されている
- 項目ごとの情報量の基準が明確になる
- 検索結果に最適化されたタイトルやキーワードが学べる
「自社の求人票をどう改善すべきか分からない」ときは、
まず大手サイトのフォーマットを参考にすると、改善の方向性が一気に明確になります。
応募が増え・マッチ度が高まった「求人票改善」事例
求人票の改善は、応募数を増やすだけでなく、「自社に合う人」を集めるための重要な施策です。
ここでは、実際の改善ポイントをもとにした3つの事例を紹介します。
Before/After を比較することで、どのような改善が効果を生むのか明確に理解できます。
ケース1|必須条件の見直しと求人票の具体化で応募数が2倍に
ある企業では、応募数が伸び悩む原因が「必須条件の設定ミス」にありました。
業務に直接関係のない条件を必須扱いにしていたため、応募者が著しく減っていたのです。
Before
- 「業界経験3年以上」
- 仕事内容の説明が抽象的で不安が残る内容
After
- 業務内容を具体化(担当範囲・頻度・1日の流れ)
- 業務に不要な必須条件を削除し、2〜3項目に絞った
- 研修で補える部分を歓迎条件に変更
その結果、応募数が約2倍に増加し、応募者の質も向上。
必須条件を削り、仕事内容を明確化するだけで応募者のハードルが下がり、応募意欲が大きく改善しました。
ケース2|ターゲットに合わせた訴求と画像変更で若手応募が増加
この企業では、ターゲット設定が曖昧で、求人票に「誰を採りたいか」が反映されていませんでした。
さらに求人画像が汎用的なフリー素材のため、職場の実態が伝わらず若手からの応募が少ない状況でした。
Before
- 年齢不問の広すぎるターゲット設定
- テンプレートのフリー素材を使用し、職場のイメージがわかりにくい
After
- ターゲットを「20〜30代の若手」に設定し、コピーを最適化
- 若手が興味を持ちやすいポイント(研修制度・キャリアアップ)を前面に記載
- メイン画像を“実際のオフィスと従業員”の写真へ差し替え
その結果、20〜30代からの応募が大幅増加。
ターゲットを明確にした訴求と適切な画像選定が、応募者層の改善に直結した事例です。
ケース3|ヒューマンスキルの言語化で早期離職率が改善
「スキル・経験」だけで採用していた企業では、入社後のミスマッチが多発していました。
求める人物像が曖昧なまま採用を進めていたことが原因でした。
Before
- スキル・経験のみに依存した募集要件
- 職場で求められる価値観・行動特性(ヒューマンスキル)の記載なし
After
- チーム文化に合うヒューマンスキルを具体化して記載
(例:「社内外の関係者と調整した経験」「課題を自ら見つけ改善した経験」など) - 活躍社員の特徴をもとにペルソナを再設計
この改善により、入社後のギャップが減少し、早期離職率が改善しました。
ヒューマンスキルの言語化は、採用の質を高める極めて重要な施策です。
まとめ|求人票改善は“採用成功の入口”を整えること
求人票は、求職者にとって企業との最初の接点であり、応募の可否を判断する大きな材料です。
そのため、求人票を改善することは「応募数を増やす」だけでなく、自社に合う人材と出会うための採用基盤づくりでもあります。
本記事で紹介したように、ターゲット設定・必須条件の整理・仕事内容の具体化・画像の最適化・データに基づくPDCAなど、改善すべきポイントは多岐にわたりますが、どれも今日から取り組める内容です。特に、中小企業や一人採用担当でも実践できる「まず3つを直す」アプローチ(タイトル/必須条件/仕事内容)は、短期間で効果を感じやすい改善施策です。
また、応募者の声を聞く・アクセス数を分析する・AIを活用するなど、外部の“第三者視点”を取り入れることで、求人票はさらに洗練されます。求人票改善は、継続することで着実に成果が積み上がるプロセスです。
少しずつ改善を重ね、自社の魅力と強みがしっかり伝わる求人票にアップデートしていきましょう。必要であれば、専門家や外部サービスに相談することも有効です。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求