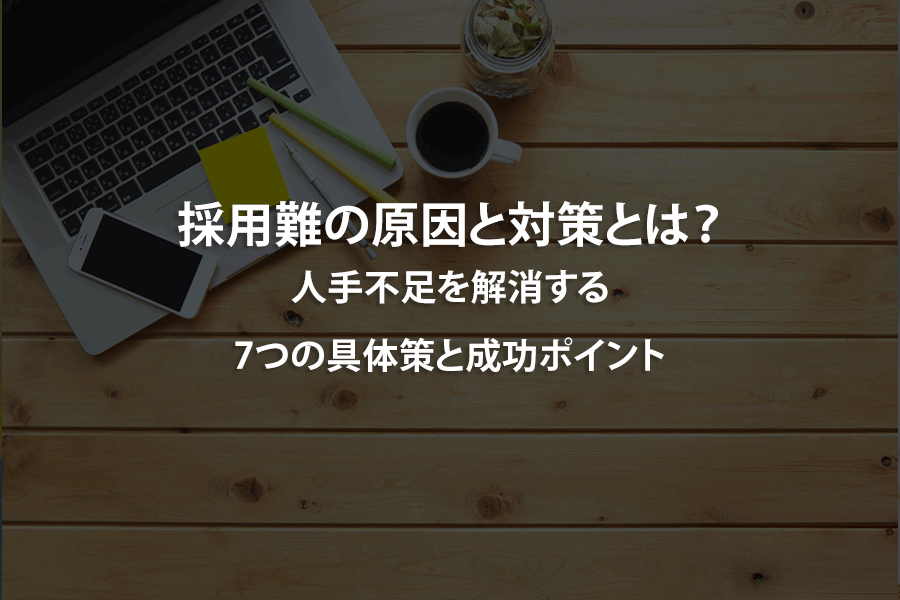
「求人を出しても応募がこない」「内定を出しても辞退されてしまう」「やっと採用してもすぐに辞めてしまう」――こうした採用難・人手不足の悩みは、いまや特定の業界だけでなく、多くの企業・人事担当者の共通課題になっています。背景には、少子高齢化による生産年齢人口の減少、働き方の多様化、転職市場の活性化など、構造的な人材不足があります。一方で、同じ環境下でも、工夫して採用難を乗り越え、人材確保に成功している企業も存在します。
本記事では、人事・採用コンサルティングの現場で蓄積してきた知見をもとに、採用難が起こる4つの原因と、今日から見直せる7つの具体的な採用難対策・人手不足解消の方法を整理します。自社の採用活動を客観的に振り返りながら、「何から手を付けるべきか」「どこに投資すべきか」を考えるための実務的なチェックリストとしてご活用ください。
なぜ今「採用難」なのか?背景と基本理解
現在、多くの企業が「採用難」に直面していますが、その実態は単に「求人を出しても応募がこない」という状況だけではありません。応募が来ても待遇や条件が合わず辞退されるケース、内定を出しても承諾されないケース、採用後すぐに離職されてしまうケースなど、複合的な問題が重なって発生しています。このような現象の背景には、採用難と人手不足が密接に絡み合う構造があり、両者を切り離して考えることはできません。
採用難=「求人を出しても人が集まらない状態」だけではない
採用難とは、単に応募数が少ないことを指すのではなく、「来ても自社の条件に合わない」「内定辞退が多い」「採用しても早期離職につながる」など、多方面で問題が発生している状態を指します。人手不足とは、必要な人数を確保できず事業運営に支障が出ている状況のことで、この2つは相互に影響し合いながら企業の採用活動を難しくしています。
日本全体の構造変化(少子高齢化・生産年齢人口の減少)
採用難の背景には、日本全体の人口構造の変化があります。特に、生産年齢人口(15~64歳)の減少は深刻で、政府の白書でも今後さらなる減少が予測されています。働き手となる人口がそもそも減っているため、1人の求職者を複数の企業が取り合う「売り手市場」が続いています。結果として、企業側が採用競争に勝つための工夫や改善を迫られる状況が生まれています。
採用市場の変化(転職の一般化・情報の透明化)
近年、転職活動は一般化し、求職者は複数の企業を比較しながら転職先を選ぶようになりました。転職サイトや口コミサイトの普及により、企業情報や社員の声が簡単に調べられるようになり、「条件」「働きやすさ」「成長環境」などを厳しく比較する傾向が強まっています。そのため、魅力づけが弱い企業は選ばれにくく、応募が集まりにくい状況が生まれています。
採用難が起こる4つの原因【社会要因+自社要因】
原因① 少子高齢化による労働人口の減少(社会要因)
採用難の最大の社会的要因は、少子高齢化による生産年齢人口の減少です。参考記事にある通り、日本では15〜64歳の働き手が長期的に減少し続けており、今後も下がり続けると推計されています。働ける人自体が減ることで、企業は労働者1人を複数社で奪い合う構造となり、結果的に採用競争が激化しています。この「売り手市場」状態が常態化していることが、採用難の本質的な背景となっています。
原因② 働き方の多様化に対応できていない
リモートワーク、時短勤務、副業など、働き方のニーズは急速に多様化しています。この環境変化に柔軟に対応できていない企業は、応募者から選ばれにくくなります。従来の「フルタイム・固定勤務・出社必須」のスタイルに固執すると、働き方に選択肢を求める求職者が他社へ流れてしまい、応募数減少や辞退の増加につながります。働き方の柔軟性は、採用における大きな競争力の一つとなっています。
原因③ 労働条件・待遇が競合より見劣りしている
給与や賞与、休暇制度、福利厚生、勤務時間の柔軟性など、労働条件は求職者が企業を比較する際の重要な判断材料です。情報が透明化された現代では、求職者はインターネット上の求人情報や口コミをもとに企業同士を細かく比較します。そのため、労働条件が「最低限の基準を満たしているか」ではなく、「競合他社より魅力的か」が採用の成否を大きく左右します。待遇改善を後回しにする企業ほど、採用難に陥りやすくなります。
原因④ 採用ミスマッチと離職率の高さ(企業固有要因)
採用難には、企業内部の課題も深く関係しています。求める人物像と実際の仕事内容・待遇との間にギャップがあると、採用ミスマッチが発生し、早期離職につながります。特に、企業が高いスキルを求めているにもかかわらず、給与体系が年功序列型のままでスキルと報酬が見合っていない場合、入社後の不満や離職を招きやすくなります。早期離職が増えることで再び採用活動が必要となり、結果として採用難をさらに悪化させる負の循環が生じます。
採用難が企業にもたらすリスクとコスト
事業機会損失・サービス品質低下リスク
採用難が続くと、欠員が埋まらない状態が長期化し、まず事業機会の損失が発生します。本来獲得できたはずの売上が失われ、顧客対応の遅れや品質低下にもつながります。さらに、現場では一部の社員に業務が集中し「属人化」が進行します。属人化が強まるほど、特定の社員が辞めた際の影響が大きくなり、採用・育成がますます難しくなる悪循環に陥ります。
社員の負荷増大とエンゲージメント低下
人手不足の状態で業務を回すと、少人数が膨大な仕事を抱えることになり、残業の増加や精神的な疲弊を引き起こします。負荷が高まり続けると、社員のモチベーションは徐々に低下し、エンゲージメントの低下、ひいては離職につながりやすくなります。「辞める人がいる → 業務量が増える → さらに辞める」という負のスパイラルが生まれ、組織力の低下が加速してしまいます。
採用・育成コストの肥大化と投資効率の悪化
採用難が続くほど、1人の採用にかかる採用単価は上昇し、採用活動に必要な時間や工数も増えていきます。さらに、ようやく採用した人材が教育投資の回収前に離職してしまうと、企業の費用負担は一段と大きくなります。これは経営視点で見ると「採用難を放置するコスト」であり、放置すればするほど投資効率が悪化します。中長期的に成長を目指す企業にとって、採用難の改善は経営課題として優先順位の高いテーマといえます。
採用難を抜け出すための7つの対策【全体像】
採用難を解消するためには、単一の施策だけでなく、複数のアプローチを組み合わせて総合的に取り組むことが重要です。ここでは、後続の各H2で詳しく解説する「7つの対策」をマップとして整理し、自社の採用課題を俯瞰できるようにまとめています。
採用難対策の全体マップ
- 対策1:労働条件・待遇の見直し
- 対策2:多様な働き方に対応する環境整備
- 対策3:デジタル化・業務効率化による「働きやすさ」向上
- 対策4:採用ターゲットの拡大(シニア・女性・外国人・地方など)
- 対策5:複数の採用手法の組み合わせ(求人広告+ダイレクト+リファラル等)
- 対策6:インターン・広報での母集団形成と認知向上
- 対策7:採用プロセスの改善・ミスマッチ防止・フォロー強化
これらの対策は、それぞれ独立した取り組みのように見えますが、実際には相互に関連しています。「待遇改善」だけ、「採用手法の変更」だけでは十分な効果は得られず、複数の施策を組み合わせることで初めて採用力が強化されます。
自社の現状を診断するチェックリスト
採用難を改善するためには、まず自社のどこに課題があるのかを正確に把握することが不可欠です。以下の指標を用いて、現状を客観的に診断してみましょう。
- 応募数は足りているか
- 書類通過率・面接参加率は適正か
- 面接辞退率・内定辞退率は高くないか
- 3年以内離職率はどの程度か
- 競合他社と比較して待遇・働き方は見劣りしていないか
これらの項目をチェックすることで、自社が強化すべき対策が明確になります。次の章以降では、7つの対策それぞれを詳しく解説していきます。
対策1:労働条件・待遇を見直す【まず手を付けるべき基本】
採用難を抜け出すために、最も効果が大きく、かつ優先順位が高い取り組みが「労働条件・待遇の見直し」です。求職者は複数企業を比較しながら応募先を決めるため、給与・福利厚生・勤務制度などが競合より魅力的でなければ、応募は集まりにくくなります。まずは自社の条件が「業界の平均」「近隣の競合企業」と比べてどうなのかを客観的に把握し、改善できる部分から着手することが重要です。
給与・賞与・手当を「業界水準」で比較する
給与や賞与、各種手当は、求職者が企業を選ぶ際の最重要ポイントの一つです。求人情報サイト、業界統計、転職サービスの給与レポートなどを参考にしながら、自社の条件が業界平均と比べてどの程度の位置にあるかを確認しましょう。「最低限の基準を満たしているか」ではなく、「競合と比較して選ばれる条件かどうか」が採用力を左右します。
休暇制度・福利厚生の充実で競合と差別化する
給与だけでなく、休暇制度や福利厚生も応募者が重視するポイントです。有給取得率、特別休暇制度、育児・介護との両立支援、健康促進施策など、働きやすさにつながる制度を充実させることは、求職者の安心感につながります。また、制度が「ある」だけでなく「実際に利用されているか」「利用しやすい雰囲気があるか」も重要で、運用実態をアピールできると大きな差別化になります。
雇用形態や評価・昇格のルールを透明化する
雇用形態の選択肢やキャリアパスが見えにくい企業は、応募者から敬遠されやすくなります。非正規から正社員への登用制度、昇格の基準、成果やスキルがどのように評価されるのかなどを明確にし、求職者に示すことが大切です。「どれだけ頑張れば、どのようにキャリアが進むのか」が見えることで応募のハードルは下がり、入社後の定着率向上にもつながります。
対策2:多様な働き方に対応できる環境を整える
求職者が企業を選ぶ際の基準は、給与や待遇だけでなく「働き方の柔軟性」に大きくシフトしています。リモートワーク、時短勤務、副業容認など多様な働き方に対応できる環境は、採用競争力を高めるうえで欠かせません。柔軟な働き方を取り入れることは、応募者の幅を広げるだけでなく、既存社員の定着率向上にもつながります。
リモートワーク・ハイブリッド勤務の導入可能性を検討する
リモートワークやハイブリッド勤務は、場所にとらわれない働き方を実現でき、採用の幅を大きく広げる手段です。導入の際は、業務を「出社必須業務」と「オンラインで完結できる業務」に切り分ける発想が重要です。また、セキュリティ対策、成果の評価方法、コミュニケーション設計など、運用面のルール整備も不可欠です。適切に整えれば、遠隔地の人材や多様な働き方を求める層にもアプローチできるようになります。
時短勤務・フレックスタイム・副業容認という選択肢
育児や介護、学び直しなど、ライフステージに応じて柔軟に働きたいというニーズは年々高まっています。時短勤務やフレックスタイム制、副業容認などの制度がある企業は応募者からの支持を得やすくなります。また、週数日の勤務や短時間勤務でもしっかりと戦力になるポジションを構築できれば、多様な層の人材が活躍できる環境を整えることができます。
社内の生産性向上=「時間あたりの価値」を高める視点
多様な働き方を推進する際に重要なのは、単に労働時間を減らすことではなく、「時間あたりの生産性を高める」視点を持つことです。ITツールの活用による業務効率化、無駄な会議や手作業の削減、アウトソーシングの活用など、生産性向上の取り組みとセットで検討することで、柔軟な働き方を無理なく実現できます。働きやすさと生産性向上が両立すれば、採用力・定着率ともに高まります。
対策3:業務のデジタル化と効率化で「魅力ある職場」にする
採用難を抜け出すためには「働きやすい職場」であることが欠かせません。その中心となるのが、業務のデジタル化・効率化です。長時間労働が常態化している職場は、応募者から敬遠されやすく、さらに既存社員の離職にもつながります。ムダを削減し、生産性を高めることで、企業の魅力は大きく向上します。
長時間労働を生み出している業務を棚卸しする
まず必要なのは、長時間労働の原因となっている業務の棚卸しです。紙での管理、手作業での集計、二重入力など、旧来型の作業には多くのムダが潜んでいます。これらを洗い出し、RPA(自動化ツール)やクラウドサービスを活用することで、工数を大幅に削減できます。単純作業の削減は、社員がより付加価値の高い業務に集中することにもつながり、職場全体の生産性が向上します。
採用・労務領域のDX(ATS・WEB面接・電子契約など)
採用領域でもデジタル化は非常に効果的です。ATS(採用管理システム)を使用すれば、応募管理や連絡の自動化が可能になり、応募者対応のスピードが向上します。また、WEB面接や電子契約の導入により、選考プロセスを迅速化できるため、応募者の離脱防止にもつながります。スピーディーな選考は「採用率UP」に直結するため、採用難の時代において欠かせない取り組みです。
業務効率化は既存社員の定着にも効く
デジタル化と業務効率化は、採用だけでなく、既存社員の定着率にも大きく貢献します。不要な負担が軽減されれば、働きやすさが向上し、離職の抑制につながります。つまり「採用難 × 高離職率」という二重の課題を同時に解決できる手段となります。効率的でストレスの少ない職場づくりは、長期的に見ても企業の競争力強化に不可欠です。
対策4:採用ターゲットを広げる【シニア・女性・外国人・地方など】
採用難が続く中で、従来のターゲットに限定した採用では応募を十分に集めることが難しくなっています。そこで重要になるのが、シニア人材・主婦層・外国人材・地方人材など、これまで積極的に採用してこなかった層に目を向けることです。多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れることで、採用の選択肢が広がるだけでなく、組織の活性化にもつながります。
シニア人材・主婦層を戦力化するポイント
シニア人材や主婦層は、時間や働き方に制約がある一方で、豊富な経験や高いスキルを持つケースが多く、適切に活かせば大きな戦力になります。時短勤務や柔軟シフトを設定しやすい職種を検討するほか、教育やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を丁寧に行うことで活躍の幅が広がります。また、世代間のコミュニケーションギャップやハラスメントに配慮した環境整備も重要です。
外国人採用のメリットと注意点
外国人採用は、若手労働力の確保やグローバル視点の獲得につながる重要な選択肢です。一方で、在留資格の要件を理解することや、言語・文化の違いを踏まえたコミュニケーション設計、受け入れ体制の整備が欠かせません。専門的なサポートを提供する外部サービスと連携することで、初めての外国人採用でもスムーズに進められます。
地方・リモート人材を活用する「場所にとらわれない採用」
地方在住者やリモートワーク人材の活用は、採用の母集団を大きく広げる効果があります。オンライン面接を活用すれば、遠方の候補者とも負担なく選考を進められます。また、フルリモート勤務や一部出社型のハイブリッド勤務を認めることで、地方に住みながら働きたい人材にもアプローチできます。さらに、交通費や移転費用の支援があるかどうかで応募のハードルが変わるため、制度整備を検討することも重要です。
対策5:採用手法を組み合わせる【求人広告+ダイレクト+リファラル】
採用難の時代では、1つの採用手法に依存するのではなく、複数の手法を組み合わせて母集団を広げることが不可欠です。求人広告・ダイレクトリクルーティング・リファラル採用・人材紹介サービスなど、それぞれに役割が異なります。自社の強みや採用ターゲットに合わせて、最適な組み合わせを見つけることが採用成功の鍵となります。
求人広告サイトの活かし方を見直す
求人広告は、依然として多くの求職者にアプローチできる基本的な採用手法です。ただし効果を最大化するためには、ターゲットに合った媒体選定が重要になります。総合求人サイト、職種特化型サイト、地域特化型など、媒体ごとの特徴を把握し、自社に合ったプラットフォームを選定しましょう。また、求人票の作り込みも採用成果を左右します。タイトルや仕事内容の具体性、写真の訴求力、企業のストーリーを盛り込むことで、求職者の共感を呼び応募率が高まります。
ダイレクトリクルーティングで「攻めの採用」に転換する
ダイレクトリクルーティングは、企業側から候補者に積極的にアプローチする「攻めの採用」です。スカウトメールを送る際は、候補者の経歴に合わせたメッセージ構成や、返信率を高めるための書き方が重要になります。また、いきなり応募を促すのではなく「まずはカジュアル面談から」という導線をつくることで、候補者の心理的ハードルを下げ、接点を生みやすくなります。専門職や経験者採用では特に効果を発揮する手法です。
リファラル採用・人材紹介サービスの位置付け
リファラル採用(社員紹介制度)は、ミスマッチが起こりにくく、採用コストも抑えられる手法として注目されています。成功のポイントは、インセンティブの設計や紹介方法の整備、社員が「紹介したい」と思える社風づくりにあります。また、人材紹介サービスは即戦力人材を確保したい場面で有効です。担当者との連携を密にし、要件定義を明確にすることで、より精度の高い母集団形成が可能になります。
対策6:インターンシップ・採用広報で母集団を育てる
採用難の時代において、応募者が自然に集まる環境をつくるためには「母集団を育てる」視点が必要です。インターンシップや採用広報は、中長期的に自社への認知を高め、応募に至るまでの接点を増やす強力な手段です。特に中小企業は大企業に比べて情報量が少ないため、意図的に自社の魅力や働く姿を発信していくことが重要になります。
インターンシップで「近くの候補者」と出会う
インターンシップは、学生や若手層に自社への理解を深めてもらう絶好の機会です。1day型の短時間インターンは「まず知ってもらう」入り口として効果的で、短期型・長期型インターンは実務体験を通してスキルや適性を見極めやすくなります。実務体験ばかりに偏らず、会社理解につながるプログラム設計を行うことで、双方のミスマッチを防ぎながら応募意欲を高めることができます。
採用広報(オウンドメディア・SNS・動画)の活用
採用広報は、多くの求職者に自社の魅力を伝えるための重要な施策です。オウンドメディアやSNSでは、社員インタビュー、1日の過ごし方、キャリア事例など、日常のリアルな姿を発信することで親近感を持ってもらえます。動画コンテンツを活用すれば、文章だけでは伝わりにくい雰囲気や文化がより具体的に伝わり、中小企業でも大企業に負けない「顔が見える情報発信」が可能になります。
ミスマッチを防ぐ「リアルな情報開示」のススメ
採用広報において重要なのは、良い面ばかりを見せるのではなく、課題や大変な点も適切に伝えることです。リアルな情報を開示することで、求職者はより正確に自社を理解でき、入社後のギャップを防ぐことができます。社員の経験談や失敗事例をコンテンツとして発信することで、表面的な魅力ではなく「この会社なら頑張れるかもしれない」という共感を生み出すきっかけになります。
対策7:採用プロセスの見直しとミスマッチ防止・フォロー
採用難の時代においては、母集団形成だけでなく「応募後の歩留まり」を改善することが極めて重要です。選考スピード、面接品質、内定後フォローの強化は、ミスマッチ防止や内定辞退の削減に直結します。採用プロセス全体を見直すことで、効率的かつ質の高い採用活動が実現し、定着率向上にもつながります。
応募者との接点を増やし、選考スピードを高める
応募者との接点が少ない企業ほど、途中辞退が発生しやすくなります。選考フロー(書類選考→一次面接→二次面接→最終面接)を必要以上に増やしていないか見直し、短縮できる部分は積極的に削減しましょう。また、連絡スピードは辞退率に直結します。面接候補日を複数提示する、リマインドを送るなど、応募者にとっての負担を減らす工夫が必要です。
面接官トレーニングと面接評価シートの活用
面接の質は採用成功に大きな影響を与えます。面接官が質問の意図や評価基準を統一できていないと、ミスマッチを招いたり、応募者に不信感を与えたりする原因になります。評価基準・質問例・NG質問をまとめた面接評価シートを導入し、面接官同士の認識を揃えることが効果的です。また、面接時には「志望度を上げるコミュニケーション」を意識することで、応募者の離脱を防ぐことができます。
内定後・入社後のフォロー体制で定着率を高める
内定承諾後の辞退や入社後の早期離職は、採用プロセス全体の成果を大きく損ないます。内定者向けの懇談会やチャットコミュニティの運用、先輩社員によるメンター制度などを活用し、安心して入社できる環境を整えましょう。また、入社後も3ヶ月・半年・1年といったタイミングで面談を実施し、業務理解や人間関係の不安を解消するオンボーディングが効果を発揮します。これにより定着率が高まり、採用難の根本的な改善へとつながります。
事例:採用難を乗り越えた企業の取り組み(仮想または簡易ケース)
ここでは、採用難の改善に成功した企業の取り組みを、仮想または簡易ケースとして紹介します。各社の工夫点や成功要因を知ることで、自社の採用改善に活かせるヒントが得られます。
ケース1|地方中小企業が「採用手法×待遇改善」で応募数2倍に
Before:求人を出しても応募が月1名程度
施策:給与の底上げ、求人票の内容改善、ダイレクトリクルーティングの導入
After:半年で応募数が2倍に増加し、採用単価の削減にも成功。待遇改善と攻めの採用手法を組み合わせたことで、慢性的な応募不足を解消した。
ケース2|IT企業がリモートワークとリファラル採用で採用難を解消
Before:首都圏フル出社前提のため応募が伸びない
施策:フルリモート勤務を可能にし、社員紹介制度(リファラル採用)を強化
After:地方在住のエンジニア採用に成功し、既存社員の定着率も向上。柔軟な働き方の導入が採用力向上に直結した。
ケース3|サービス業がインターンと育成強化で早期離職を半減
Before:新卒の3年以内離職率が50%と高止まりしていた
施策:長期インターンを導入し、入社前から業務理解を深めてもらう仕組みを構築。その後、入社後OJTの再設計と定期的な1on1面談を導入。
After:早期離職率が大幅に改善し、現場の教育負荷も軽減。ミスマッチ防止と育成体制強化が相乗効果を生んだ。
まとめ
採用難は、少子高齢化や働き方の多様化、情報の透明化など、社会全体の構造変化が背景にあるため、単なる一時的な課題ではありません。しかし、同じ環境下でも、採用戦略を見直し、労働条件の改善や働き方の柔軟化、業務の効率化、採用手法の多様化などに取り組むことで、応募数や採用率が大きく改善した企業は数多く存在します。採用難の本質は「企業の魅力づくり」と「応募者から選ばれる仕組みづくり」にあり、本記事で紹介した7つの対策はその基盤になります。
まずは、自社の応募数・面接辞退率・内定辞退率・離職率などのデータを振り返り、「どこに課題があるのか」を明確にすることが重要です。そのうえで、労働条件の見直し、採用手法の組み合わせ、働き方改革、選考プロセス改善、情報発信など、効果が大きい施策から順番に取り組んでいきましょう。また、必要に応じて採用コンサルティングや外部サービスを活用することで、よりスピーディーに改善が進みます。中長期的に人材が集まり定着する仕組みを整え、持続的に成長できる組織づくりを目指しましょう。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求