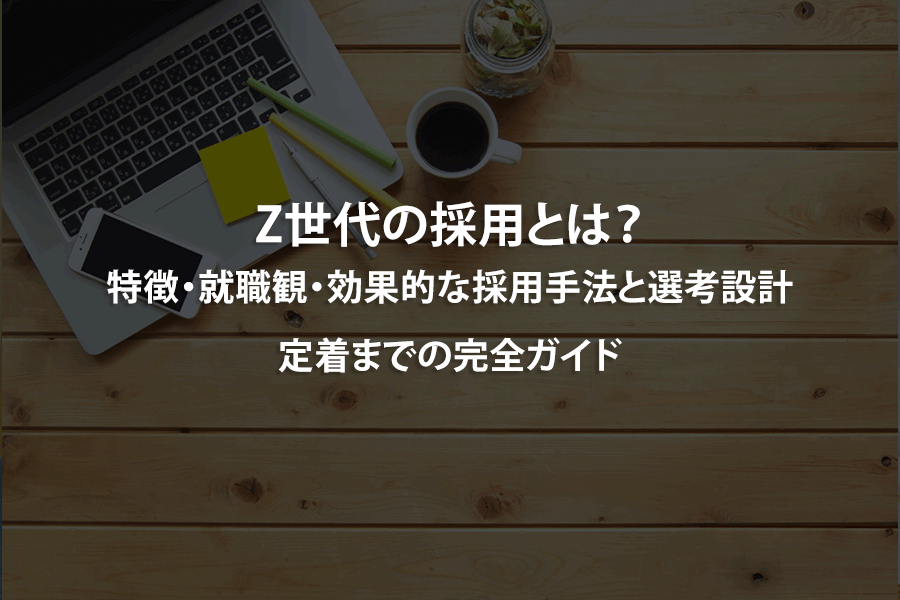
Z世代(1990年代半ば〜2010年代前半生まれ)はデジタルネイティブで、多様性・社会的意義・タイパを重視し、ジョブ型志向や柔軟な働き方への期待が高い世代です。新卒・第二新卒の採用現場では、従来のナビ中心・一括説明会型だけではリーチも説得も不十分になりつつあります。本稿では、参考データと現場の実務経験をもとに、(1)Z世代の理解 →(2)採用チャネル戦略 →(3)候補者体験設計 →(4)育成・定着 →(5)KPIで回すまでを体系化。SNS/動画・ダイレクトリクルーティング・インターン設計・ハイブリッドワーク運用・オンボーディング90日プランなど、すぐ実装できる施策とチェックリストを提示します。読了後、貴社は自社の採用要件とZ世代の期待値を接続した、実行可能なロードマップを描けるはずです。
Z世代とは:定義・年代幅・前後世代との違い
定義と年代幅:1990年代半ば〜2010年代前半(国内外の呼称差と実務上の扱い)
Z世代とは、1990年代半ばから2010年代前半に生まれた世代を指し、インターネットやスマートフォンとともに育った「デジタルネイティブ世代」です。 海外では“Gen Z”と呼ばれ、日本では「脱ゆとり世代」とも重なります。ミレニアル世代(Y世代)の次にあたるため、社会の価値観転換期を象徴する層です。
前後世代との比較:X/Y(ミレニアル)/α世代―情報収集・価値観・就業観の違い
- X世代:バブル期の影響を受け、個人主義・安定志向が強い。
- Y世代(ミレニアル):インターネット黎明期を経験し、物より体験を重視。
- Z世代:多様性・SDGs・透明性を重視し、SNSや動画で情報収集。
- α世代:生まれながらのAI・スマホ世代。直感的なデジタル操作が特徴。
Z世代は、上の世代に比べて「所属より個の実感」「情報の透明性」「共感ベースの選択」を重視する傾向があります。
採用上のポイント要約:ジョブ型志向/透明性/動画・SNS主導の情報収集
- 配属・勤務地・評価などを明確に提示する「ジョブ型採用」の導入が効果的。
- 企業情報の“誇張”よりも“リアルで誠実な情報発信”が信頼を生む。
- TikTok・Instagram・YouTubeなどの動画SNSで採用広報を展開することが必須。
Z世代の就職観・価値観:重視項目と離職要因
Z世代は「楽しく働きたい」「やりがいを感じたい」といった内面的な満足度を最も重視します。
次いで「安定している」「成長できる環境」「柔軟に働ける制度」が上位に挙がります。
給与や肩書きよりも、仕事の意義・成長実感・プライベートとの両立が優先される傾向にあります。
タイパ志向・短尺動画への親和性/コミュニティ思考(内定者座談会の効用)
Z世代は「限られた時間で最大の成果を得たい」と考えるタイムパフォーマンス志向(タイパ)が特徴です。
SNSやYouTubeショート、TikTokなどの短尺動画を通じて情報を得る傾向があり、採用広報も動画化が効果的です。
また、コミュニティ志向が強く、内定者座談会や社員交流イベントなど、共感・つながりを感じられる場がエンゲージメント向上に繋がります。
離職理由の型:待遇不満/キャリアチェンジ/成長機会の不透明さ
Z世代の離職理由は「給与や待遇への不満」だけでなく、キャリアチェンジ志向や「成長の停滞」を感じたことが多いです。
「自分のキャリアが描けない」「評価や昇進が不明確」など、成長機会の不透明さが早期離職に直結します。
定期的な1on1やキャリアレビューの導入が、離職防止に効果的です。
誤解の是正:「給与だけで惹きつけられない」「配属ガチャ忌避」「透明性が最重要」
採用現場での誤解として、「給与を上げれば採用できる」という認識がありますが、Z世代は報酬よりも透明性と納得感を重視します。
特に「配属ガチャ」への不安が強く、勤務地・職務・上司・評価制度などの明確な説明が欠かせません。
企業側の「誠実な情報提供」と「選択できる仕組み」が信頼構築の鍵となります。
Z世代が“入社したくない”企業の特徴(自社診断チェックリスト)
古い体質のシグナル:年功序列・長時間労働・紙/属人運用・ITリテラシー不足
Z世代が最も敬遠するのは、「昭和型の組織文化」や「柔軟性のない体制」です。
年功序列が強く、長時間労働を美徳とする文化や、いまだに紙や口頭での業務が中心の属人化された運用は、デジタルネイティブ世代にとって大きな違和感を与えます。
また、上司層のITリテラシー不足はコミュニケーションの断絶を生み、成長意欲の高い若手ほど離脱しやすくなります。
情報の曖昧さ:職務内容・評価基準・勤務地・働き方が不透明
Z世代は「透明性」を重視する傾向があります。
採用段階で職務内容や評価基準、勤務地、働き方が曖昧な企業は、入社後のギャップを想起させ、応募率・内定承諾率の低下につながります。
採用ページや説明会では、「どんな仕事を、誰と、どこで行うのか」を具体的に示すことが求められます。
ハイブリッド未整備:出社/リモートのルール不在、機材・ペーパーレス未整備
リモートワークと出社を組み合わせたハイブリッド勤務は、Z世代の理想的な働き方の一つです。
一方で、「リモートは許可制」「紙資料中心」「VPN環境が不安定」など、制度と設備の整備不足はマイナス評価になります。
テクノロジーに精通したZ世代ほど、環境のストレスや非効率さに敏感です。IT基盤の整備は採用競争力に直結します。
即改善リスト(20項目):業務定義・勤務地選択・工数可視化・有休/残業ルール 等
- 職務・ミッションの明文化(募集要項に具体的な業務内容を記載)
- 勤務地の選択制・テレワーク可否を明示
- 残業時間・有休取得率を実数で開示
- 人事評価基準・昇給条件の開示
- 電子承認・デジタル文書の導入
- 社内SNS・チャットツールによる情報共有
- 上司・部下間1on1の定期化
- メンター・OJT制度の明文化
- キャリア面談・異動希望制度の運用
- 在宅勤務用ツール・セキュリティ整備
- ペーパーレス化と業務マニュアルの共有
- 勤怠・業務の可視化(工数・成果の見える化)
- ダイバーシティ&インクルージョン施策の提示
- 情報発信の一貫性(採用広報・SNS運用)
- 若手社員インタビュー・現場レポートの掲載
- 新入社員オンボーディング計画の整備
- 社内アンケート・エンゲージメント調査の実施
- コンプライアンス・ハラスメント研修の明示
- 経営層・マネージャーのIT研修の実施
- 採用・育成・評価のPDCA化
これらの項目を定期的に点検し、「Z世代に選ばれる企業」への更新を続けることが重要です。
採用チャネル戦略:SNS/動画×ダイレクトリクルーティング×口コミ
SNS/動画運用:1日密着・ロールモデル紹介・職務の“1週間”(短尺×シリーズ化)
Z世代は日常的にYouTubeショート・TikTok・Instagramリールなどの短尺動画に慣れています。
企業の採用広報も、短く・テンポよく・リアルな職場の雰囲気が伝わる構成が効果的です。
「1日密着」「職務の1週間」「若手社員の1年」などのシリーズ化でストーリー性を持たせると、エンゲージメント率が向上します。
また、若手社員が自ら出演しリアルなコメントを発信することで、企業文化への共感を醸成できます。
ダイレクトリクルーティング:スカウト文面テンプレ/ABテスト/歩留まり指標
ナビ媒体に頼らず、学生や若手人材へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングが主流になりつつあります。
スカウト文面は、候補者ごとのプロフィールに合わせて「共感+具体的な提案」で構成することが重要です。
ABテストで件名や導入文の反応を比較し、返信率・面談化率・内定承諾率のデータを追うことで歩留まりを改善できます。
テンプレート化+データ検証により、属人化せず継続的な成果を出せる仕組みを整えましょう。
口コミ/コミュニティ:OB/OG・インターン生コミュニティ/選考体験のUGC化
Z世代は口コミやリアルな体験談を重視します。
「就活会議」「ONE CAREER」「OpenWork」などの口コミサイトに加え、OB・OG訪問やインターン卒業生とのSNSコミュニティを整備することで、信頼のある情報源を確保できます。
また、内定者や現場社員の声をSNSやYouTubeで発信し、選考体験をUGC(User Generated Content)化することで、共感ベースの応募動機を生み出せます。
媒体/組み合わせ設計:母集団の質×コスト×運用体制でポートフォリオ最適化
採用チャネルは、「数」よりも「質」と「運用体制の持続性」が鍵です。
ナビ媒体・スカウト・SNS・自社採用サイトなどの特性を整理し、目的別に組み合わせることでROIを最大化します。
例)ナビ媒体=母集団形成、ダイレクト=ターゲット精査、SNS=ブランド認知、口コミ=信頼形成。
採用担当者の稼働リソースとコストを可視化し、年間ポートフォリオとして設計することが、Z世代採用の成功を左右します。
候補者体験(CX)設計:説明・面接・連絡の“透明性”が決め手
情報開示テンプレ:職務内容・成果基準・評価/昇給モデル・勤務地選択・研修計画
Z世代は、企業からの情報提供において「透明性」と「納得感」を最も重視します。
採用ページや説明会では、以下の要素をテンプレートとして整理・提示すると効果的です。
- 職務内容と具体的な成果指標(どんな業務をどの水準で行うのか)
- 評価・昇給モデル(何をどう達成すれば昇格・昇給するのか)
- 勤務地の選択肢と希望反映プロセス
- 研修・育成計画(初期研修・OJT・1on1・資格支援など)
この情報を事前に明示することで、候補者の不安を軽減し、応募率と内定承諾率の両方を高められます。
面接の問い:経験不足前提で行動特性を測る質問設計(例:困難克服/役割/再現性)
新卒・第二新卒など、実務経験の少ないZ世代に対しては「スキル」よりも行動特性を見極める面接設計が重要です。
例として、以下のような質問で候補者の思考・姿勢・再現性を測ることができます。
- 困難を乗り越えた経験と、その際の具体的な行動・工夫
- チームでの役割分担と、周囲を支援したエピソード
- 新しい知識やツールをどのように学んだか
- 今後挑戦したいテーマと、達成までのステップイメージ
質問の目的を「評価」ではなく「理解」に置き、候補者の価値観を引き出す姿勢が信頼形成につながります。
事前連絡・当日運営:チェックリスト+自動リマインドで離脱を最小化
Z世代は情報社会で育っており、「連絡不足」に不安を感じやすい世代です。
選考当日までの流れを明確にし、リマインドメールやチャット連絡を活用することで離脱を防げます。
- 面接日程・会場・アクセス・服装・持ち物の明記
- 前日リマインドと、緊急時の連絡先案内
- 当日の受付・所要時間・面接官構成の共有
- 選考後の連絡予定時期・合否通知方法の明示
これらをテンプレート化・自動化(メール配信・LINE通知など)することで、候補者体験を大幅に向上できます。
オンライン面接の型:推奨環境・入室/命名規則・背景/照明・録画同意
オンライン面接では、対面以上に「環境整備と運営ルール」が重要です。
以下を事前案内として共有し、候補者が安心して面接に臨める環境を整えましょう。
- 推奨環境(PC推奨/通信安定・静かな場所・イヤホン着用)
- 入室・命名ルール(例:「氏名_大学名」形式で入室)
- 背景・照明・画角の調整(顔の明るさと視線位置の統一)
- 録画の有無とデータの取り扱いに関する同意取得
オンライン面接を円滑に運用することで、候補者の安心感と企業の信頼度が高まり、CX(候補者体験)の品質が向上します。
インターン/体験型プログラム:実務密着で“やりがい”を可視化
プロジェクト型:実課題×メンター伴走で職務理解と相互評価を両立
Z世代に響くインターン設計の鍵は、「実課題への挑戦」と「伴走するメンター制度」にあります。
架空テーマではなく、実際の事業課題やクライアント案件をベースにした内容にすることで、職務理解が深まり、学生のモチベーションも高まります。
また、メンター社員がフィードバックを行うことで、学生と企業の双方向評価(相互理解)が可能になります。
参加学生が「自分がどんな場面で力を発揮できるか」を実感できる環境づくりが重要です。
ジョブシャドウイング:1日の動線・会議観察・業務同席でリアリティ担保
ジョブシャドウイングとは、社員の1日を追体験する形で仕事を観察するプログラムです。
朝礼・会議・商談・資料作成など、リアルな業務の動線を体験することで、学生が仕事の「リアリティ」を具体的に掴むことができます。
特にZ世代は、「働く姿」を動画やSNSで視覚的に理解してきた世代のため、こうした体験設計が納得感に直結します。
成果発表と評価Rubric:プロセス重視(再現性・協働・学習軌跡)
インターンの成果発表では、最終アウトプットだけでなくプロセス評価を行うことが効果的です。
具体的には、以下のような評価Rubric(ルーブリック)を設定します。
- 再現性:課題に対して論理的にアプローチできたか
- 協働性:チームでの役割意識・貢献度・コミュニケーション力
- 学習軌跡:フィードバックを活かし成長・改善できたか
成果発表会をオンライン配信やSNSで共有することで、学生の努力を可視化し、採用ブランディングにも活用できます。
内定者コミュニティの運営:Slack/Discordで継続接点→入社意思の醸成
インターン後のフォロー施策として、内定者や参加者を対象にしたオンラインコミュニティ運営が有効です。
SlackやDiscordなどを活用し、社員との座談会・相談会・社内イベント情報などを共有することで、内定辞退の防止やロイヤリティ向上につながります。
Z世代は「共感・つながり」を重視するため、入社前から関係性を構築することが、最終的な入社意思の醸成に直結します。
オファー前後の訴求:配属・育成・福利厚生・柔軟性を具体で示す
キャリア可視化:1年以内の昇給可能性/職級モデル/スキル期待値の明文化
Z世代は将来への不透明感を嫌い、「成長の見通し」を求めます。
内定時には「1年以内の昇給・昇進の可能性」や「職級モデル」「スキル期待値」を可視化し、キャリアのロードマップを具体的に提示しましょう。
例えば、「入社9か月でリーダー昇格」「スキル評価基準は5段階」など、明確な基準と期間の見える化が、入社決定率の向上につながります。
育成施策:メンター/1on1、資格支援、社内副業・新規事業提案
Z世代は「学び続けられる職場」への期待が高い世代です。
配属前後でメンター制度を整え、定期的な1on1ミーティングを実施することで、心理的安全性と定着率が向上します。
また、資格取得や外部セミナー費用の補助、社内副業・新規事業提案制度など、挑戦と成長を支援する環境をアピールすることで、Z世代からの共感を得られます。
働き方:フルフレックス/コアタイム、ハイブリッド、選べる勤務地
Z世代はワークライフバランスを重視し、柔軟な働き方を求めます。
出社とリモートを組み合わせたハイブリッドワーク、またはフルフレックス制度を導入することで、個々のライフスタイルに合わせた働き方が可能になります。
さらに、「勤務地を自分で選べる」「Uターン・Iターン勤務が可能」といった選択肢を明示することで、地方在住の学生にも安心感を与えます。
福利厚生:自己啓発系・ワークライフ系(休暇設計・ボランティア休暇 等)
Z世代は「福利厚生=働く安心感」と捉えています。
単なる制度の羅列ではなく、自己啓発系・ワークライフ系の福利厚生を具体的に伝えることが大切です。
- 自己啓発系:資格取得支援/セミナー・研修費用補助/キャリアコーチング制度
- ワークライフ系:リフレッシュ休暇/ボランティア休暇/誕生日休暇/時短勤務
- 柔軟制度:副業・複業の許可、在宅勤務手当、フレキシブル休暇制度
企業の「人を大切にする姿勢」を具体的に示すことで、Z世代のエンゲージメントと定着率を高められます。
オンボーディング90日ロードマップ:定着を加速する初期設計
0–30日:MVV理解×業務地図×役割期待の合意/先輩同行/週次1on1
入社初期の30日間は、Z世代が「自分の役割」と「会社の目的」を結びつけるフェーズです。
まずはMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の理解を深め、業務の全体像を可視化した業務地図を共有します。
先輩社員の同行や週次1on1を通じて、心理的安全性と早期キャッチアップを実現しましょう。
小さな成功体験を積み上げることが、初期モチベーション維持の鍵になります。
31–60日:ミニゴール×振り返り/メンター切替/社内ネットワーク拡張
2か月目は、実務を通じた成長と自立のステージです。
「ミニゴール」を設定し、週次・月次で振り返りを行うことで、学習の定着を促します。
このタイミングでメンターを切り替え、部署横断の人脈形成や他チームとの関わりを強化すると、社内ネットワークの広がりが生まれます。
Z世代にとって、「誰と働くか」がエンゲージメントを左右する重要要素です。
61–90日:初成果の可視化/評価フィードバック/次四半期の育成プラン
3か月目には、業務の中で得た成果を可視化し、正式な評価・フィードバックを行うタイミングです。
「初成果」を数値または行動レベルで記録し、本人の成長と課題を共有します。
上司・メンター・本人の三者面談を実施し、次の四半期に向けた育成プラン(OKR・学習目標など)を設定することで、定着と自律を同時に促せます。
必要な可視化:ダッシュボード(出社率・学習進捗・1on1頻度・初期成果)
オンボーディング施策の効果を高めるには、可視化されたデータ管理が不可欠です。
ダッシュボードを活用して、以下のような指標を定期的にモニタリングしましょう。
- 出社率・リモート稼働率(勤務習慣の安定度)
- 学習進捗・トレーニング完了率(スキル習得度)
- 1on1実施頻度・内容ログ(コミュニケーション密度)
- 初期成果・小タスク完了件数(成長と成功体験の見える化)
これらのデータを四半期ごとにレビューし、改善・強化サイクルを回すことで、定着率とエンゲージメントの両方を高められます。
KPIと改善:採用から定着まで“回る仕組み”
採用KPI:媒体別CVR・スカウト返信率・面接通過率・承諾率・辞退理由
採用活動の成果を可視化するには、定量指標(KPI)の設定が欠かせません。
媒体ごとのCVR(応募→面接→内定の転換率)やスカウト返信率を把握することで、チャネルごとの効率を見極められます。
また、面接通過率・内定承諾率・辞退理由を定期的に分析することで、ボトルネックを特定し、採用プロセスの改善に活かせます。
KPIは「数」だけでなく、「なぜその数字になったのか」を分析する仕組みづくりが重要です。
初期定着KPI:3/6/12か月の在籍・エンゲージメント・1on1実施率・学習進捗
採用後の成功は、入社後の定着と成長スピードによって測られます。
特に、入社後3か月・6か月・12か月時点での在籍率やエンゲージメントスコアを追跡することで、オンボーディング施策の効果を定量的に評価できます。
1on1の実施率や学習タスクの完了率など、日常行動に紐づくKPIを設けることで、早期離職を予防し、組織学習を促進します。
品質指標:職務適合・評価の納得度・心理的安全性・FB密度(サーベイ設計)
定量的なKPIだけでなく、定性的な品質指標のモニタリングも不可欠です。
社員サーベイで以下のような指標を測定し、職場環境の“質”を継続的に改善します。
- 職務適合度:仕事内容と本人の希望・スキルの一致度
- 評価の納得度:評価基準やプロセスの理解・公平感
- 心理的安全性:チーム内での発言・提案のしやすさ
- FB密度(フィードバック密度):1on1や評価面談の頻度・質
サーベイ結果を「一時的な満足度」ではなく、エンゲージメントの構成要素として可視化することで、戦略的な組織改善が可能になります。
改善サイクル:四半期レビューで施策の間引き・強化/OKR連動
KPI・サーベイ・インタビューなどのデータをもとに、四半期ごとに振り返りと改善を行う仕組みを構築します。
成果が薄い施策を間引き、効果が高いものを強化し、次の四半期OKRと連動させることで、採用から育成・定着まで一貫したPDCAを実現できます。
これにより、採用が単発イベントではなく、「学習する採用システム」として機能し始めます。
まとめ|Z世代採用の成功は「理解×透明性×データ運用」
Z世代の採用で成果を上げるためには、従来型の大量採用や属人的対応から脱却し、候補者体験(CX)とデータドリブンな改善サイクルを両立させることが鍵となります。
彼らは「給与」よりも「成長・納得・共感」を重視し、企業の価値観や透明性に敏感です。そのため、採用チャネルの多様化(SNS/動画/ダイレクトリクルーティング)や、面接・オンボーディング設計における“見える化”が欠かせません。
また、採用後の定着率・1on1実施率・心理的安全性などをKPIとして定期的に可視化し、四半期単位で施策を振り返る「改善ループ」を仕組み化することで、組織全体の学習と信頼が生まれます。
Z世代が共感し、長く働きたいと感じる企業とは、言葉だけでなく行動とデータで「一緒に成長できる」と示せる企業です。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求