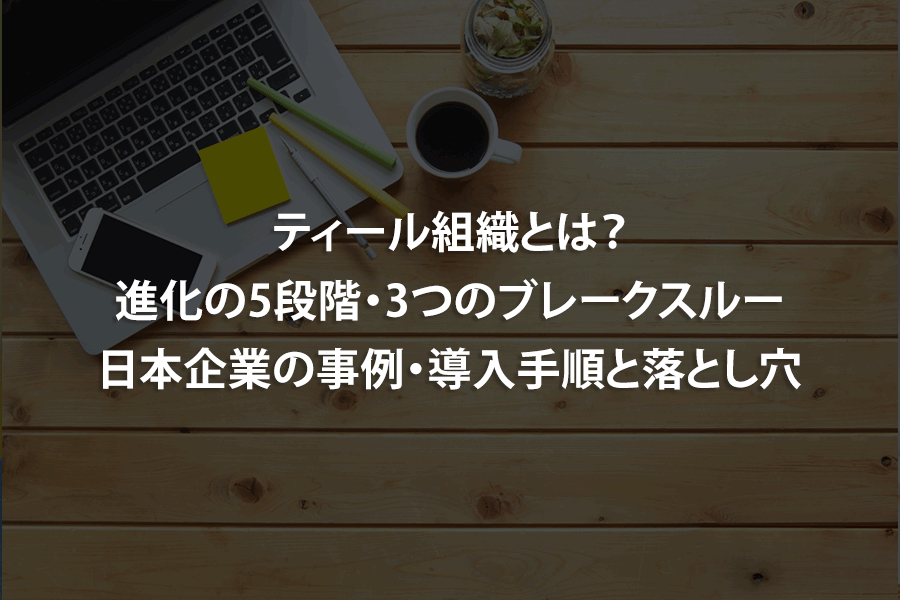
変化が常態化したいま、トップダウン前提のヒエラルキーだけでは意思決定が遅れ、現場の自律性も育ちません。そこで注目されるのがティール組織です。フレデリック・ラルーの『Reinventing Organizations/ティール組織』で提示された概念は、組織を“生命体”と捉え、進化する目的(パーパス)/セルフマネジメント/ホールネスの3要素を核に、現場分散の意思決定で価値創出を加速します。本稿では、ティール組織の定義、レッド〜グリーンを経る進化の5段階、ホラクラシーとの違い、日本企業の実践事例、導入の適性・手順・落とし穴、そしてOKR・KPI・サーベイによる効果測定まで、導入検討者が知りたい情報を一次情報に基づく実務目線で整理。メリットだけでなく限界や代替策まで俯瞰し、読者が次の一歩を踏み出せるようにガイドします。
ティール組織とは:定義・背景・検索意図の要点
ティール組織の定義
- 自律・分散・協調:意思決定は現場に分散し、助言を得ながら協調して進める。
- 進化する目的(パーパス):固定ビジョンではなく、環境変化に応じて目的が更新される。
- 全体性(ホールネス):心理的安全性を基盤に、個人が「ありのまま」で価値発揮できる。
定義の要約――「自律・分散・協調」「進化する目的」「全体性(ホールネス)」
ティール組織とは、ヒエラルキー中心の統制ではなく、 自律・分散・協調を基調に現場が意思決定する次世代型の組織モデルです。 その核は、環境に呼応して更新される進化する目的(パーパス)と、 個人の特性や価値観を尊重する全体性(ホールネス)にあります。 これにより、意思決定のスピードと当事者意識が高まり、学習と適応が継続的に循環します。
なぜ今ティール組織が検索されるのか――働き方改革/イノベーション速度/権限委譲の遅れ
- 働き方改革と人材定着:過度な統制や属人化を見直し、エンゲージメントと自律性を両立させたい企業が増加。
- イノベーションの速度:市場変化に即応するため、現場判断の迅速化(リードタイム短縮)が必須。
- 権限委譲の遅れ:中間管理層に意思決定が滞留し、ボトルネック化。分散型ガバナンスへの関心が高まる。
結果として、「ティール 組織 とは」「パーパス 経営」「心理的安全性」などの検索が増え、 自社に適用可能な運用設計(助言プロセス/情報公開ルール/評価制度)への具体的ニーズが強まっています。
進化の5段階:レッド/アンバー/オレンジ/グリーン/ティール
フレデリック・ラルーの『Reinventing Organizations(邦訳:ティール組織)』では、 組織の発展を「色」で表現しています。
各段階はそれぞれの価値観やマネジメントスタイルの進化を示しており、 「ティール組織」はその最も成熟した進化段階とされています。
レッド(衝動型)――強権と短期志向
最も原始的な組織形態であり、強いリーダーの支配によって成り立ちます。 メンバーはリーダーに従属し、恐怖や力による統制が中心です。 短期的な利益追求が目的で、組織文化よりも生存本能に近い運営が特徴です。 現代では、一部のベンチャー企業や危機対応時の組織行動に類似するケースがあります。
アンバー(順応型)――厳格ヒエラルキーと安定志向
ヒエラルキー構造が明確で、秩序や役割を重視する組織です。 軍隊や官僚組織に多く見られ、安定した長期運営を可能にしますが、 変化に対応しにくい硬直性を持ちます。 メンバーはルール遵守を第一に行動し、創造性や自発性が抑制されやすい傾向にあります。
オレンジ(達成型)――数値管理・競争・イノベーションの促進と限界
現代の多くの企業が採用しているモデルで、成果主義・競争・効率化が中心です。 メンバーはKPIや数値目標で評価され、「達成」が最大の価値となります。 イノベーションが生まれやすい一方、過度な競争により過労・モチベーション低下などの課題を生みやすい側面もあります。
グリーン(多元型)――多様性・ボトムアップ・合意形成コスト
個々のメンバーが主体的に意見を出し、多様性を重視する組織です。 上下関係よりもチームワークを重視し、ボトムアップ型の意思決定が特徴です。 心理的安全性が高まりやすい反面、合意形成に時間がかかるため、 意思決定スピードの低下が課題になることもあります。
ティール(進化型)――生命体メタファー/役職固定からの脱却と“役割”の流動化
ティール組織では、組織を一つの生命体とみなし、全員が目的に共鳴して行動します。 指揮命令ではなく、セルフマネジメント(自主経営)と進化するパーパスを軸に、 個々のメンバーが自律的に意思決定を行います。 役職は固定されず、役割(ロール)が流動的に変化します。 心理的安全性・透明性・助言文化が成立条件となります。
誤読への注意――ティールは前段階を否定しない/状況により混在する
ティール組織はオレンジやグリーンを「否定」するものではありません。 事業内容・業種・企業規模によっては、複数の段階が併存・混在することが自然です。 組織が進化するとは、各段階で得た価値観を内包しながら最適化することを意味します。
ティール組織とホラクラシーの違い
「ティール組織」と並んで語られることの多い概念に「ホラクラシー(Holacracy)」があります。 どちらも“ヒエラルキーを排したフラットな組織運営”を目指す点では共通しますが、 実際には目的・構造・適用範囲が異なるため、混同しない理解が重要です。
ホラクラシー=具体的運用モデル(サークル/ロール/ガバナンス)
ホラクラシーは2007年に米国のブライアン・ロバートソン氏が提唱した組織運営モデルです。 明確なルールブックがあり、組織を「サークル(Circle)」と呼ばれる単位に分け、 それぞれが自律的に意思決定を行います。役職ではなく、プロジェクトや目的に応じた ロール(役割)を複数担うことができ、必要に応じて交代や変更も可能です。 また、ガバナンス会議によって権限の分配やロールの定義が更新され、 組織の透明性と俊敏性を両立させるのが特徴です。
ポイント: ホラクラシーは「運用ルール」「ガバナンス設計」が明文化された、
“実践可能な仕組み”としての側面が強い。
ティール=概念フレーム(到達段階・価値観)
一方のティール組織は、フレデリック・ラルーの著書『Reinventing Organizations』で提示された 「組織進化の概念フレーム」です。明確なルールや手法を定義するものではなく、 組織が“進化型(Teal)”の価値観――進化する目的(パーパス)・セルフマネジメント・ホールネスを 実現している状態を指します。 つまり、ティールは「あり方(Being)」、ホラクラシーは「やり方(Doing)」の違いと捉えると理解しやすいでしょう。
現実的には“ティールの一形態としてホラクラシーを採用”という関係
実務の現場では、ティール組織の理念を実装するための仕組みとして、 ホラクラシーを一部導入している企業が多く存在します。 たとえば、意思決定の透明化やロール制を取り入れながら、 自社の文化や事業特性に合わせてカスタマイズする形です。 したがって両者は対立概念ではなく、ティール=価値観・哲学、ホラクラシー=運用ツールとして 補完関係にあるといえます。
ティール組織の3つのブレークスルー(原典に基づく骨子)
フレデリック・ラルーの『Reinventing Organizations(邦訳:ティール組織)』では、
組織がティール段階に進化するために必要な3つのブレークスルー(突破口)が示されています。
それは「進化する目的(Evolutionary Purpose)」「セルフマネジメント」「ホールネス(全体性)」です。 以下では、それぞれの要素を原典に基づいて整理し、実務で応用するための設計ポイントを解説します。
進化する目的(Evolutionary Purpose)――固定的ビジョンから応答的パーパスへ
従来の組織はトップが掲げる固定的なビジョンや目標を基準に運営されてきました。 一方、ティール組織では、組織そのものを“生きた存在(生命体)”と捉え、 外部環境の変化や社会の要請に応じて目的(パーパス)が進化・変容していくと考えます。
- 経営者やマネージャーが「方向性を決める」のではなく、組織全体が「環境の声を聴く」。
- パーパスは固定目標ではなく、学習と適応を通じて更新される“生きた指針”。
- パーパス経営の根本思想と重なり、社会的意義と個人の意義の重なりを重視。
実務ポイント:年度計画ではなく四半期単位で“目的の再定義”を行い、社員対話で共創する仕組みを。
セルフマネジメント――助言プロセス/情報の透明性/権限の分散
ティール組織の中核となるのがセルフマネジメント(自主経営)です。 階層的な上司・部下の関係を廃し、メンバー全員が意思決定の責任と権限を持ちます。 ただし“放任”ではなく、助言プロセス(Advice Process)によって 適切な判断を行うための透明な仕組みを整えます。
- 助言プロセス:意思決定前に、関係者や専門家の意見を聞くことを義務化。
- 情報の透明性:経営・財務・人事データを原則全メンバーに開示。
- 権限の分散:ロール(役割)単位で権限を配分し、柔軟に更新する。
実務ポイント:意思決定の記録(ログ)を共有し、誰が何を判断したかを可視化することで信頼を担保。
ホールネス(全体性)――「ありのまま」でいられる設計と心理的安全性
従来の組織では、社員が「役割を演じる」ことが期待され、 個人の感情や価値観は職場に持ち込まないのが一般的でした。 ティール組織では、メンバーがありのままの自分(全人格)でいられることが前提です。 そのために不可欠なのが、心理的安全性の確保と多様性を尊重する文化設計です。
- 心理的安全性:意見や失敗を安心して共有できる環境を整える。
- 多様性の受容:個性や感情を否定せず、チーム全体の学習資源とする。
- 全体性の仕組み:感謝の日(Thanks Day)や雑談サークルなど“人間らしさ”を活かす制度。
実務ポイント:心理的安全性サーベイや1on1を定期的に行い、チーム温度を定量化。
補助設計――情報公開ルール、意思決定ガイド、紛争解決プロトコル
ティール組織を安定運用するためには、理念だけでなく仕組みの裏付けが必要です。 特に「情報公開の原則」「意思決定のルール」「紛争時の対応プロトコル」の3点を整備することで、 メンバーの自律性を守りつつ、混乱を防ぐことができます。
- 情報公開ルール:例外なく原則公開。非公開とする場合は理由と期間を明示。
- 意思決定ガイド:助言プロセスの手順書化と、意思決定の合意形成プロセスの明確化。
- 紛争解決プロトコル:上位者に頼らず、当事者間の対話と第三者メディエーションを制度化。
実務ポイント:「仕組みで守る」ことがセルフマネジメントの前提。制度=自由の土台と捉える。
日本企業の実践例に学ぶ:施策・副作用・学びの抽象化
ティール組織の理念は理論的に理解しても、実際に運用するとなると多くの課題が伴います。 ここでは、日本企業でティール的アプローチを取り入れたオズビジョンとネットプロテクションズの事例から、 具体的施策と得られた示唆、そして運用上の注意点を整理します。
オズビジョンの示唆――ホールネス支援制度(Thanks day/Good or New)→理念浸透と制度の陳腐化リスク、継続的な取捨選択
ポイントサイト「ハピタス」を運営するオズビジョン社は、 社員の幸福と自己実現を理念に掲げ、ホールネス(全体性)の浸透に力を入れています。 代表的な施策が「Thanks Day」と「Good or New」の2つです。
- Thanks Day:年に1日、誰かに感謝を伝えるための特別休暇を取得でき、感謝内容を社内ブログで共有。
- Good or New:毎朝の短いミーティングで、メンバー同士が「良かったこと」や「新しい気づき」を共有。
これらの施策は、組織内に心理的安全性を醸成し、感謝文化の定着に寄与しました。 しかし同時に、制度の形式化・マンネリ化といった課題も発生。 同社は継続的なモニタリングを通じて「やめる勇気」も持ち、理念を体現する制度だけを残す形で進化を続けています。
学び:理念に沿った制度は有効だが、“維持すること”を目的化しない。制度は理念の道具にすぎない。
ネットプロテクションズの示唆――マネージャー役職廃止/カタリスト/バンド制/360度評価による自律・分散・協調
ネットプロテクションズ社では、「自律・分散・協調」を理念に掲げ、 役職や上下関係を撤廃しながらも、機能的なガバナンスを維持しています。 特徴的な取り組みは以下の4点です。
- マネージャー役職廃止:恒常的な権限集中を避け、全員が意思決定に参加できる構造へ。
- カタリスト制度:各部署に複数名配置される“促進者”。役割は流動的で期ごとに交代。
- バンド制:5段階のグレードにより成長指標を明示し、給与レンジを全社員に開示。
- 360度評価:メンバー同士で相互フィードバックを行い、昇格・昇給を決定。
この仕組みにより、組織全体の透明性と当事者意識が高まり、 自律・分散・協調の文化が日常業務レベルで浸透しています。
学び:「全員がマネージャー的に考える」構造を支えるのは、評価の透明性と役割の明確化。
事例から抽出できる原則――役割の流動化・評価の透明性・“権限の再集中”を避ける設計
2社の事例から見える共通点は、制度そのものよりも「設計思想」にあります。
- 役割の流動化:固定的な役職をなくし、目的や状況に応じてロールを再定義する。
- 評価の透明性:誰がどのように評価するかを可視化し、納得感を担保。
- 権限の再集中を防ぐ:マネジメント層が“意思決定のボトルネック”にならない設計にする。
ティール的アプローチは「ヒエラルキーの否定」ではなく、 目的に合わせて流動的にリーダーシップを共有する仕組みの設計にあるといえます。
学び:リーダーシップの“所有”ではなく、“循環”を設計することがティール型の本質。
適用限界――全員が一律に自律できるわけではない/業務特性と規制業種の制約
ティール組織はすべての企業に適するわけではありません。 自律的な意思決定を行うには、メンバーの成熟度・専門性・価値観の共有が前提となります。 また、金融・医療・公共など高い法規制やリスク管理が求められる業種では、 完全なフラット構造の導入は現実的ではありません。
- 段階的導入:まずは小規模チームや特定プロジェクトで試行。
- 補完型アプローチ:オレンジ/グリーン型とのハイブリッド運用を検討。
- サーベイ活用:心理的安全性やエンゲージメントを定量的に把握しながら調整。
成功事例を“コピー”するのではなく、自社の文脈に合わせた最適化が鍵です。
導入の適性診断:向く組織・向かない組織(チェックリスト付き)
ティール組織は、すべての企業・チームに一律で適用できるモデルではありません。 組織文化・業種・規模・メンバー構成などにより、適性の高い組織とそうでない組織があります。 以下のチェックリストと前提条件をもとに、自社がどの段階にあるのかを客観的に把握してみましょう。
適性チェック(20項目)
以下の項目のうち、「はい」と答えられる数が多いほど、ティール型への移行に向いている傾向があります。 反対に「いいえ」が多い場合は、まず基礎的な組織開発や心理的安全性の向上から始めるのが現実的です。
- パーパスの定義と更新頻度:明確な存在意義があり、定期的に見直している。
- 情報公開の範囲:経営・財務・人事情報を原則オープンにしている。
- 助言プロセスの有無:意思決定時に関係者・専門家からの助言を得る仕組みがある。
- 心理的安全性のベースライン:メンバーが自由に意見・提案・異議を表明できる。
- 紛争解決手順:上下関係ではなく対話と合意形成で解決するルールがある。
- 財務・人事の可視化:報酬や評価の仕組みを透明化している。
- 規制・コンプライアンス要件:法的制約を踏まえつつも自律運営を妨げない設計をしている。
- 現場の能力密度:各メンバーが一定レベルの専門性と自律性を持っている。
- 採用・育成の方針:「自律・共創」を重視した採用基準を設定している。
- 経営の透明性:意思決定理由を明確にし、全社員に説明できる文化がある。
- 役割の明確化:職務よりも「役割(ロール)」ベースで仕事を定義している。
- フィードバック文化:上司だけでなく同僚同士でもフィードバックを行っている。
- チーム内信頼度:お互いの強み・弱みを理解し補い合う風土がある。
- 成果の測定基準:短期利益よりも学習・改善・価値提供を重視している。
- 柔軟な意思決定:役職ではなく当事者に意思決定権がある。
- コミュニケーション設計:情報がトップダウンだけでなく双方向に流れている。
- マネジメントスタイル:指示ではなく伴走・コーチングが主流になっている。
- 制度運用:制度を維持することよりも理念との整合性を重視している。
- 学習文化:失敗から学びを得る仕組み(レビュー・ふりかえり)がある。
- 外部への開放性:社外パートナーや顧客とも目的を共有し、共創できている。
判定目安: ・15項目以上:高適性。ティール型導入に前向きな準備段階。
・10〜14項目:中適性。部分導入(助言プロセスや透明性施策)から開始。
・9項目以下:低適性。まず心理的安全性・情報共有の基盤整備を優先。
導入の前提――経営の覚悟、ミドルの役割再定義(コーチ・カタリストへ)
ティール型への移行を成功させるには、単に制度を導入するだけでなく、経営の覚悟が不可欠です。 トップが「任せる」と決めた瞬間に、組織の構造も関係性も変化し始めます。 その過程で最も大きく変わるのが、ミドルマネジメント層の役割です。
- コントロールから支援へ:進捗や成果を管理する立場から、成長を支えるコーチへ。
- 意思決定から促進へ:方向性を決めるのではなく、助言と調整で意思決定を支える。
- 権限から信頼へ:「管理権限」を手放し、チームの自律性を信じるリーダーシップへ。
経営層は「信頼して任せる覚悟」を、ミドルは「手放して支える覚悟」を持つ。 この相互理解があって初めて、ティール組織の価値が発揮されます。
導入ロードマップ:小さく始めて広げる(パイロット→制度化→スケール)
ティール組織の導入は、いきなり全社展開するのではなく、小さく実験しながら学習を積み上げていくプロセスが重要です。 ここでは、実践的な5つのステップと、隣接・代替アプローチを整理します。
Step1 パイロット領域の選定――プロダクト小チーム/コーポレートの一部機能など
最初の一歩は、リスクを限定しながらも効果が見えやすい領域を選定することです。 小規模なプロジェクトチームや、コーポレート部門(広報・人事・R&Dなど)で試行するのが現実的です。 成功体験と失敗要因を抽出し、社内の学習資産として蓄積することを目的とします。
- 影響範囲が限定された領域でスタート。
- 経営層・人事部門が観察・支援できる距離感を保つ。
- メンバーの主体性が高く、変化に前向きなチームを選定。
Step2 助言プロセスと情報公開ルールの明文化(意思決定ログ/可視化)
パイロットを開始したら、まずは意思決定の透明化と助言プロセスの整備を行います。 「誰が・どんな理由で・どのような助言を得て判断したのか」を可視化し、判断の質を高めることが目的です。
- 助言プロセス:意思決定前に関係者・専門家の意見を聞くことをルール化。
- 意思決定ログ:判断内容・背景・助言内容を共有フォルダやノートで記録。
- 情報公開ルール:原則オープン、非公開の際は理由・期間を明示。
ポイント:透明性が信頼を生み、信頼が自律を支える。
Step3 役割設計――固定役職→ロール化(流動的役割+任期)
ティール組織では、従来の「役職」ではなく、ロール(役割)ベースの設計を採用します。 ロールは固定的ではなく、プロジェクトや目的に応じて柔軟に変更されます。 任期やスキルに応じて入れ替えを行い、流動性と責任のバランスを保ちます。
- 役職 → 役割(ロール)へ転換。
- ロールごとに「目的・責任・期待成果」を明記。
- 任期や成果レビューのタイミングを明文化。
ポイント:流動的ロール設計により、権限の固定化と属人化を防止。
Step4 人事制度の整合――評価は360度+行動指標(セルフマネジメント・貢献度)
ティール組織では、成果主義一辺倒ではなく、行動・姿勢・貢献度を重視した評価が必要です。 特に360度評価を取り入れ、個人の自己管理力・他者への貢献・チーム協働を定性的に測定します。
- 360度評価:上司・同僚・部下・他チームから多面的に評価。
- 行動指標:セルフマネジメント・学習意欲・支援行動をKPI化。
- 制度整合:報酬・昇格基準を透明にし、信頼性を確保。
ポイント:「成果を出した人」よりも「仕組みを支えた人」を評価する文化へ。
Step5 学習ループ――月次レトロスペクティブ/四半期ガバナンスレビュー
ティール型運営では、施策を「実行して終わり」にしないことが重要です。 レトロスペクティブ(振り返り)とガバナンスレビューを定期的に実施し、 組織全体で学習サイクルを回します。
- 月次レトロスペクティブ:チーム単位で成功・失敗・改善点を共有。
- 四半期ガバナンスレビュー:制度運用・意思決定プロセス・透明性を再点検。
- サーベイ併用:心理的安全性やエンゲージメントの変化を可視化。
ポイント:学習の「儀式化」が組織の進化を加速させる。
代替・隣接アプローチ――グリーン強化/アジャイル組織/一部ホラクラシー併用
ティール導入が難しい場合でも、隣接アプローチを取り入れることで組織変革を進められます。 たとえば、ボトムアップ文化を重視するグリーン組織の強化や、 スプリント中心のアジャイル開発組織、一部領域のみでのホラクラシー導入などです。
- グリーン強化:心理的安全性・多様性・共感型リーダーシップを育む。
- アジャイル組織:短期目標と振り返りサイクルで変化適応力を高める。
- ホラクラシー併用:助言プロセスやロール制を限定領域で試行。
完全なティール化を目指さずとも、自社に適した形で「進化の方向性」を示すことが重要です。
メリット・デメリットと“落とし穴”:回避策の設計
ティール組織は理想的なモデルとして注目されますが、導入時には必ず利点とリスクの両面を理解しておく必要があります。 以下では、メリット・デメリットに加えて、誤解されがちなポイントと、実務的な回避策の設計指針を整理します。
メリット――意思決定の高速化/現場裁量・当事者意識/採用ブランディング
ティール組織の最大の魅力は、現場の自律性と意思決定スピードの向上です。 指示待ちの文化を脱し、目的に基づいて自ら判断する文化が生まれることで、変化への対応力が飛躍的に高まります。
- 意思決定の高速化:現場主導で判断できるため、承認プロセスの遅延が解消される。
- 現場裁量・当事者意識:メンバーが主体的に考え、行動する文化が根付く。
- 採用ブランディング:「フラットで挑戦できる環境」を訴求でき、共感人材の採用が進む。
ポイント:目的・意思決定基準・情報公開ルールを明確にするほど、現場の判断精度は高まる。
デメリット――責任の所在曖昧化/調整コスト/“なんちゃって自律”の蔓延
一方で、権限を分散することは責任の所在を不明確にしやすいというリスクを伴います。 また、意思決定に時間がかかる「逆・非効率」な状況を招くこともあります。
- 責任の所在曖昧化:全員が関与する構造により、「誰が最終判断者か」が不明確になる。
- 調整コスト:助言や合意形成に時間がかかり、スピードが落ちる場合もある。
- “なんちゃって自律”:ルールや目的の共有がないまま自由だけを拡大すると、混乱を招く。
注意:「自由=放任」ではない。明確な目的と信頼関係の設計がなければ破綻する。
よくある誤解――会議や目標を“全廃”することではない/全員が即自律できるわけではない
ティール組織は「会議も目標も不要」「すべてフラットで決定できる」と誤解されがちです。 実際には、必要な会議体・目標設定・ロール設計を維持しながら、意思決定の基準を現場に移すことが重要です。
- 目標(OKR/KPI)は必要。ただし「成果」ではなく「目的貢献度」で測る。
- 会議体は継続。ただし「報告」ではなく「対話・助言」の場として再定義。
- 自律は一夜で生まれない。段階的な移行と伴走支援が不可欠。
ポイント:「仕組みの撤廃」ではなく「意味の再設計」。目的に基づく会議・目標が必要。
回避設計
上記のリスクを防ぐには、ティールの理念を支える実務設計が欠かせません。 自律を支えるのは「ルール」ではなく「透明性」と「対話の仕組み」です。
- 助言プロセスの必須化:意思決定時に関係者の助言を求めるプロセスを明文化。
- 可視化ダッシュボード:進捗・成果・助言履歴を共有できるプラットフォームを整備。
- リスク門番(合議制):重大リスクは複数人で審議・判断する仕組みを導入。
- 衝突のルール:対立や意見不一致を前提とし、合意不要・異議申し立てを制度化。
- 法令・監査ラインの独立性:法務・監査・情報セキュリティ部門はフラット構造から独立しチェック機能を保つ。
ポイント:「自由の裏には仕組みがある」。ルールを最小限に、透明性を最大化せよ。
成果測定と継続改善:OKR・KPIツリー・サーベイ
ティール型の運営は「導入して終わり」ではありません。OKR・KPI・サーベイを連動させ、学習の儀式で定着させることで、組織の適応力を継続的に高めます。
OKR設計――O=パーパスの具現化テーマ/KR=行動・成果の混合指標
OKRは、O(Objective)=パーパスの具現化テーマ、KR(Key Results)=行動・成果の混合指標として設計します。数値だけでなく、助言プロセスや透明性などティール固有の行動指標を含めます。
| 要素 | 例 |
|---|---|
| O | 「自律・分散・協調を加速し、意思決定時間を短縮する」 |
| KR1(行動) | 助言プロセス実施率を90%へ(意思決定ログの有無で判定) |
| KR2(成果) | 重要意思決定の中央値リードタイムを5営業日→2営業日に短縮 |
| KR3(文化) | 心理的安全性スコアを+0.5pt向上(5段階パルス) |
Tips:KRは「行動(プロセス)×成果(アウトカム)」のハイブリッドで作ると、定着と効果の両立がしやすい。
KPIツリー例――意思決定速度/助言プロセス遵守率/情報公開率/心理的安全性
ティールのKPIは「自律を支える仕組みの健全性」を測る指標を中心に据えます。下記のようにツリー化し、部門・チームへ分解します。
- 最上位KPI:意思決定速度(リードタイム中央値/P95)
- プロセスKPI:
- 助言プロセス遵守率(意思決定ログに助言者記録がある比率)
- 情報公開率(意思決定ログの社内公開比率/公開までの遅延)
- ロール更新頻度(任期終了時の更新実施率/遅延件数)
- 文化KPI:
- 心理的安全性スコア(5段階)/自由記述のポジネガ比
- 相互フィードバック実施率(360度の回収率/遅延率)
- 成果KPI:新提案の採択数/実験数→収益・顧客価値への転換率
可視化:ダッシュボードで週次更新。KPIに紐づく意思決定ログへのリンクを付与し、学習材料にする。
サーベイ運用――月次“パルス+フリーコメント”/四半期ラーニングレビュー
量的スコアと自由記述の両方を取り、「数字の背景」を理解します。スコアだけの運用は逆効果になりやすいため、対話とセットで活用します。
- 月次パルス:5~8問の短問+フリーコメント(所要1~3分)。匿名可。
- 集計:チーム単位で即共有。良い実践例をピックアップして全社ナレッジ化。
- 四半期ラーニングレビュー:サーベイ×KPI×OKR達成度を突き合わせ、制度・ロール・情報公開の改善策を決定。
設計ポイント:サーベイは「査定材料」にしない。学習と対話の入口として設計する。
学習の“儀式”――役割の入替(任期付き)/カタリストのローテーション
学習を文化にするには、儀式化(リズム化)が有効です。任期付きロールとカタリストのローテーションで、権限の固定化を防ぎます。
- ロール任期:3~6か月を標準。期末にロールレビュー&引き継ぎを実施。
- カタリスト・ローテーション:各期10%程度を入替。新陳代謝と多視点を確保。
- 月次レトロ:成功・失敗・学びをテンプレで共有(判断背景リンクを必須項目に)。
- 四半期ガバナンスレビュー:助言プロセス、公開ルール、紛争解決の見直しを定例化。
合言葉:「仕組みは固定しない」。運用で学び、四半期ごとに小改訂していく。
FAQ&導入チェックリスト(すぐ使える)
ティール組織の導入を検討する際に多く寄せられる質問と、すぐに活用できるチェックリストをまとめました。 理論だけでなく実践に移す際の「判断基準」としてお使いください。
FAQ
- ティール組織とホラクラシーの違いは?
ティール組織は「価値観・進化思想」としての概念フレーム、ホラクラシーはそれを実務化した運用モデルです。 ティール=思想、ホラクラシー=仕組みと捉えると理解しやすいでしょう。 - 完全ティールでないと意味がない?
いいえ。部分導入(助言プロセスやロール設計など)でも効果はあります。 重要なのは「自律・分散・協調」の原則を、自社の文脈に合わせて取り入れることです。 - 規制業種でも可能?
はい。法的制約の中でも、権限分散の範囲設計や情報共有・フィードバック文化の強化は可能です。 完全フラット化よりも「自律的意思決定の拡張」が現実的です。 - ミドルの役割は?
管理者から支援者・カタリストへと役割を再定義します。 方向を決めるのではなく、助言・調整・学習促進を担う存在にシフトします。 - 短期的成果は出る?
すぐに財務成果が出るとは限りません。まずはパイロットで行動KPI(助言率・心理的安全性)を測定し、 そこから事業KPIへの転換を図ることが持続的な成果につながります。
補足:すべてに共通するポイントは「完璧を目指さない」こと。小さく試して学習する姿勢が鍵です。
導入20項目チェック(抜粋)
下記は、ティール導入を検討する企業向けの実践チェックリスト(抜粋)です。 各項目を「実施済/準備中/未着手」で確認し、ボトルネックを可視化しましょう。
- パーパスの更新プロセス:存在意義を定期的に見直す仕組みがある。
- 助言プロセスの明文化:意思決定前に関係者・専門家の助言を得るルールがある。
- 情報開示範囲:経営・財務・人事情報を原則オープンにしている。
- 360度評価の準備:多面評価制度を導入または試行している。
- 心理的安全性の測定基盤:サーベイまたは定性ヒアリングを定期実施している。
- 紛争解決手順:上下関係ではなく、対話と合意形成で解決するルールを整備している。
- 任期付きロール設計:役職を固定せず、3〜6か月単位で見直すサイクルを持っている。
- 監査・法務の独立ライン:自律的な組織であっても、監査・法務が独立してチェック機能を果たす。
実践ポイント:チェック結果をチームで共有し、改善アクションをOKR・KPIツリーに組み込む。
まとめ:ティール組織は“理想論”ではなく、進化の方向性である
ティール組織は「管理を手放す」「完全フラットにする」といった誤解が先行しがちですが、実際は 目的に基づき自律し、協働しながら進化し続けるための組織デザインです。 重要なのは、制度を真似ることではなく、透明性/助言プロセス/心理的安全性/学習の儀式といった 原則を、自社の文化と事業に合わせて段階的に取り入れることです。
また、ティールは“完璧なゴール”ではなく、進化の方向性。 レッド/アンバー/オレンジ/グリーンの良さも尊重しつつ、小さく試し、学び、改善する ことが成功の鍵です。パイロット運用から始め、OKR・KPI・サーベイによる計測と振り返りで、 自律と信頼にもとづく組織文化を育てていきましょう。
本記事が、自社の組織づくりを見直し、働きがいと成果が両立するチームをつくるための 一歩となれば幸いです。より具体的な制度設計や導入支援をご希望の場合は、 ぜひお気軽にご相談ください。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求