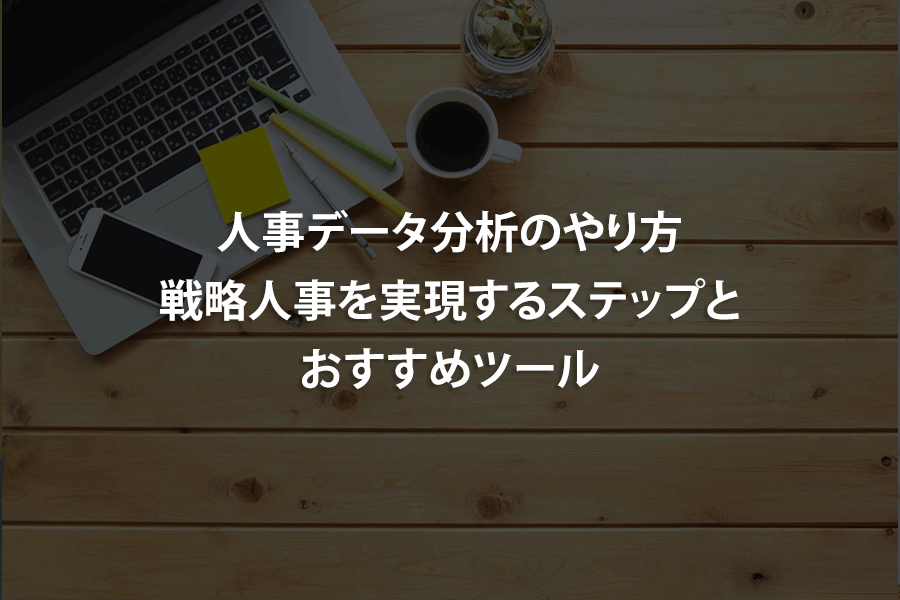
人事データ分析とは?定義と注目される背景
人事データ分析(HRデータ分析/ピープルアナリティクス)とは、勤怠・評価・給与・スキル・エンゲージメントなど 従業員に関する多様なデータを収集・統合・可視化・統計解析し、採用・配置・育成・評価・離職抑制といった 人事意思決定の精度を高める取り組みです。経験や勘に寄りがちな判断を、データドリブンに置き換えることで、 組織課題の早期発見と施策の再現性向上をめざします。
近年は人的資本の開示義務化や労働人口減少、現場の多様化・複雑化を背景に、戦略人事の実現手段として 人事データ分析の重要性が一段と高まっています。まずは定義と背景を押さえ、取り組みの全体像を理解しましょう。
人事データ分析とピープルアナリティクスの違い
一般に両者はほぼ同義で使われますが、使い分ける場合は次のように整理できます。
- 人事データ分析:人事領域のデータ(勤怠・評価・給与 等)を収集→整備→集計→可視化→統計解析する一連の分析行為に焦点。
- ピープルアナリティクス:分析で得た知見を経営・事業・人事施策へ実装し、成果創出までを含む マネジメント手法(活用プロセス)に焦点。
つまり、「人事データ分析」=分析スキル/手段、「ピープルアナリティクス」=価値創出の枠組みとして捉えると、 施策立案やKPI連動まで発想が広がり、業務効果(効率化)と経営効果(業績・生産性)を両立できます。
労働人口減少・戦略人事・テクノロジー進化という3つの潮流
人事データ分析が注目される背景には、次の3大メガトレンドがあります。
- 労働人口の減少:限られた人員で成果を最大化するには、生産性の可視化・人材の最適配置・早期育成が不可欠。 データに基づく育成・配置で一人ひとりのパフォーマンスを底上げします。
- 戦略人事の推進:採用・育成・評価を経営戦略と連動させるには、仮説検証可能な 定量データが必須。人事データ分析は施策の質とスピードを高め、PDCAを回しやすくします。
- テクノロジーの進化:クラウド、BI、AI、RPAの普及で、収集・統合・可視化・分析のコストが大幅低減。 中小企業でも段階的に導入しやすい環境が整っています。
これらの潮流が重なり、人事(HR)×データ×分析による意思決定が、短期の効率化のみならず 中長期の人的資本価値の向上に直結する時代になっています。
経営課題と人事データ活用の関係性
| 経営課題 | 必要な人事データ(例) | 分析・示唆(例) |
|---|---|---|
| 生産性向上・人件費最適化 | 勤怠、評価、職種/スキル、売上/利益寄与 | ハイパフォーマー特性、時間当たり付加価値の可視化、配置最適化 |
| 離職率低減・採用効率化 | 退職理由、等級/給与、面談記録、サーベイ | 離職リスク因子の特定、要因別の対策優先度 |
| 人的資本の開示・説明責任 | 研修/スキル、エンゲージメント、ダイバーシティ指標 | KPIの標準化、年次トレンド、投資対効果の可視化 |
このように、経営が求める成果(KGI/KSF)→必要データ→分析→施策実装→検証という一貫した流れを設計することで、 人事データ分析は戦略人事の中核機能として機能します。まずは目的と指標を明確化し、信頼できるデータ基盤を整えることが成功の第一歩です。
人事データ分析の目的と活用メリット
人事データ分析の最大の目的は、従業員や組織の状態を「可視化」し、感覚ではなくデータに基づく意思決定を行うことです。
採用・配置・育成・評価といったあらゆる人事業務を定量的に捉えることで、組織全体の生産性向上と従業員満足度の両立を実現します。
ここでは、人事データ分析がもたらす主な効果と、戦略的な活用方法を解説します。
採用・配置・育成・評価など各フェーズへの影響
人事データ分析は、社員のライフサイクル全体にわたって活用できます。
- 採用:応募者データと入社後の評価を紐づけ、「活躍する人材の共通点」を特定。採用ミスマッチの防止や採用ROIの向上に貢献します。
- 配置:スキル・パーソナリティ・成果データをもとに、最適な人材配置を支援。チーム構成の最適化や早期戦力化を促します。
- 育成:評価・研修・キャリア志向のデータを分析し、個別最適な育成プランを設計。エンゲージメント向上や離職防止につながります。
- 評価:客観的なデータを用いることで、評価の属人化・バイアスを防止。透明性と納得度の高い人事制度運用を実現します。
このように、データを活用することで人事プロセスの「感覚頼み」から脱却し、再現性のある成果創出が可能になります。
経営戦略との連動による「戦略人事」への貢献
人事データ分析は、単なる人材管理の効率化にとどまらず、経営戦略と人材戦略を結びつける「戦略人事」を実現する手段です。
たとえば、企業の中期経営計画における「新規事業拡大」「海外展開」「デジタル化推進」といった目標に対して、 どの部署にどんなスキルを持つ人材がどれだけ必要かを定量的に把握できます。 分析結果をもとに、採用・育成・配置・報酬制度をデータで裏付けて設計することで、 経営戦略の実行力を支える人事体制を構築できます。
経営視点からの「人材ポートフォリオ管理」や「人的資本のROI分析」は、データドリブン経営を支える重要な基盤です。
また、人的資本開示やガバナンス強化が求められる今、人事データ分析は企業価値向上の指標としても活用されています。
組織課題の可視化・従業員エンゲージメント向上
組織の「見えない課題」をデータで可視化することは、人事データ分析の大きな強みです。 例えば、離職率や残業時間、エンゲージメントスコアなどのデータを定期的にモニタリングすることで、 問題が顕在化する前に早期対策を講じることができます。
特に、従業員サーベイや1on1記録などの定性データを組み合わせることで、心理的安全性・職場満足度・上司部下関係など、 数字だけでは見えない課題も明らかにできます。
- 離職予兆を検知し、ハイリスク層に早期フォロー
- モチベーションデータと業績を関連づけて、“活躍する環境”の要因を特定
- サーベイ結果を可視化して、従業員エンゲージメントの改善PDCAを継続
このようなデータ活用により、従業員の「声」を経営判断に反映し、働きがいのある組織づくりを実現します。
人事データ分析のステップ(初心者向けプロセス)
人事データ分析は、いきなり高度な分析を行うものではありません。
「目的を明確にする」→「必要なデータを集める」→「データベースを整備する」→「分析・検証する」→「施策に活かす」
というプロセスを段階的に進めることが成功の鍵です。ここでは、初心者でも実践しやすい5つのステップを紹介します。
①目的設定 ― 何を明らかにしたいかを明確化
最初のステップは、人事データ分析の目的を明確にすることです。
たとえば、「離職率を下げたい」「採用のミスマッチを減らしたい」「評価制度を改善したい」など、目的によって分析の方向性が変わります。
目的が曖昧なままデータを集めても、有効な示唆は得られません。
まずは経営課題・組織課題を整理し、「何を知りたいのか」「どんな意思決定につなげたいのか」を具体化しましょう。
例:「営業職の離職率が高い理由を明らかにし、早期離職を防止する施策を設計したい」
このように、仮説思考をもって目的を設定することで、分析の方向性がブレず、成果につながるデータ活用が可能になります。
②データ収集 ― 勤怠・評価・離職・満足度などの収集範囲
次に行うのは、目的に応じたデータの収集です。人事データは多岐にわたりますが、最初は基本的な項目から始めましょう。
- 勤怠データ:残業時間・出勤時間・有給取得率など(労働時間・健康状態の分析)
- 評価データ:人事評価・スキルレベル・成果目標など(ハイパフォーマー分析・育成方針)
- 離職データ:退職者の年齢・職種・勤続年数・退職理由(離職リスクの特定)
- 満足度データ:従業員サーベイ・エンゲージメントスコア(職場環境・心理的安全性の把握)
データは可能な限り定量(数値)×定性(コメント・意識)を組み合わせることで、より実態に即した分析が可能になります。
③データベース構築 ― 統合・整備・アクセス権設計
収集したデータは、バラバラのままでは活用できません。
Excelやクラウド型タレントマネジメントシステムを活用し、データを統合・整理しましょう。
データベース構築のポイントは以下の通りです。
- 統合:勤怠・評価・人事異動などのデータを統一フォーマットで一元管理
- 整備:重複・欠損・形式不一致などを修正し、分析しやすい構造に整える
- アクセス権:個人情報を含むため、閲覧・編集権限を適切に設計(セキュリティ対策)
これらを整備することで、後工程の分析精度と信頼性が大幅に向上します。
④分析と仮説検証 ― 定量×定性データの統合分析
データが揃ったら、いよいよ分析フェーズです。
まずは目的に沿って仮説を立てることから始めましょう。
例:「評価の高い社員は残業時間が短い傾向があるのではないか?」
この仮説をデータで検証することで、実態とのギャップを明らかにできます。
また、数値データ(定量)だけでなく、面談記録やアンケートコメント(定性)も活用することで、 「なぜそうなったのか」という根本原因を深掘りできます。
- クロス集計や相関分析で関係性を確認
- BIツールでグラフ化し、視覚的に傾向を把握
- テキストマイニングでコメント内容の傾向を抽出
重要なのは、分析結果を「事実」として受け止め、感情や先入観に左右されない判断を行うことです。
⑤施策への落とし込み ― 結果を基に改善サイクルへ
分析の目的は「気づき」で終わらせず、具体的な施策につなげることです。
例えば、退職リスクが高い層が特定できた場合、キャリア面談の頻度を上げたり、報酬体系を見直すなどの対策を検討します。
また、施策を実行した後は、効果検証(KPIモニタリング)を行いましょう。
改善施策 → 検証 → 再分析 のサイクルを回すことで、データドリブンな人事運営が定着します。
このサイクルを継続することで、「分析する人事」から「戦略を創る人事」へと進化できます。
まず分析すべき人事データ3選
人事データ分析を始める際、「どのデータから分析すればよいのか分からない」という声をよく耳にします。
ここでは、初心者でもすぐに取り組めて、効果が出やすい3つの人事データを紹介します。
どれも組織課題の発見や改善施策につながる重要な情報源です。
評価データ ― ハイパフォーマーの傾向分析
評価データは、人材育成や配置戦略に直結する最も価値の高いデータです。
高い業績を上げている社員(ハイパフォーマー)の共通点を抽出することで、再現可能な育成・採用モデルを構築できます。
- 高評価者の特徴(スキル・行動・勤務形態など)をデータで可視化
- 評価項目ごとのスコア分布から成果に寄与する因子を特定
- ハイパフォーマーの傾向をもとに、次世代リーダー候補を発掘
また、同じ評価でも部署や上司によって基準が異なる場合は、評価のばらつき(評価者バイアス)を数値で検出し、 公平性・一貫性を高める手がかりにもなります。
退職者データ ― 離職原因の特定と防止施策
退職者データは、組織の“健康状態”を映し出す鏡のような存在です。
退職時アンケートや面談記録などを分析することで、離職の背景にある構造的な問題を特定できます。
- 年齢層・勤続年数・評価スコアなどを軸にした離職傾向の把握
- 部署別・上司別・職種別の離職率比較でリスクの集中箇所を可視化
- 退職理由をカテゴリ化し、再発防止の優先度を設定
さらに、退職者データを在職者データと照らし合わせることで、離職予兆モデル(リスクスコア)の構築も可能です。 これにより、早期のフォローやエンゲージメント施策を展開できます。
勤怠データ ― 健康・モチベーション管理への応用
勤怠データは、従業員のコンディションを定量的に把握するための基本情報です。
出勤時間・残業時間・休暇取得率などの推移を追うことで、業務負荷やメンタル面の兆候を早期に察知できます。
- 残業時間の急増や出勤時刻の乱れによる過労・ストレス兆候の検知
- 有給取得率と評価・エンゲージメントの関連性を分析
- 勤怠データを活用したワークライフバランス改善の指標設定
特に、勤怠データは日次で更新されるため、リアルタイムに近い状態で組織の変化を追跡できるのが強みです。
ケーススタディ:従業員満足度×生産性の相関分析
ここでは、実際の分析事例として「従業員満足度」と「生産性」の関係を分析したケースを紹介します。
ある企業では、年2回のエンゲージメントサーベイ結果を部門別に集計し、営業利益・業績KPIと突き合わせて相関を調査しました。
その結果、「上司への信頼」「チーム内コミュニケーション」スコアが高い部門ほど生産性が高いという傾向が明らかに。
さらに、この結果を踏まえ、管理職研修やチームビルディング施策を重点的に実施したところ、 翌年度には離職率が10%改善し、営業利益率も上昇しました。
データ分析の価値は「数値を出すこと」ではなく、「行動を変えること」。
仮説→分析→施策→検証のサイクルを回すことが、人事DX成功の鍵です。
分析精度を高めるためのデータ環境整備
人事データ分析の成果を左右するのは、「どれだけ精度の高いデータを扱えるか」です。
分析技術やツールだけでなく、データを整備し、正確・安全に運用する基盤づくりが不可欠です。
ここでは、精度と信頼性を高めるための環境整備のポイントを解説します。
人事データベースの構築ポイント(フォーマット統一・権限管理)
効果的な人事データ分析を行うには、まずデータベースの設計と整備が重要です。
Excelなどの分散管理ではデータの整合性が保てず、分析時にミスや欠損が生じやすくなります。
- フォーマットの統一:氏名・所属・評価・勤怠などの項目を共通化し、全社で同じ基準で記録。
- 項目命名ルールの標準化:「部署名」「部門名」など表記ゆれを防ぐルールを設定。
- アクセス権限の設計:個人情報保護のため、役職・職務に応じた閲覧/編集範囲を明確化。
また、分析目的を見据えたデータ設計(例:時系列分析用の履歴テーブル)を行うことで、後工程での活用効率が格段に上がります。
データガバナンスとセキュリティ対策(信頼性・透明性の確保)
人事データは機密性が高いため、分析の前提としてガバナンス(管理体制)とセキュリティの整備が不可欠です。
信頼できるデータを扱うことが、分析結果への信頼と透明性を支えます。
- データ更新ルール:入力頻度・責任者・チェック体制を明確化。
- アクセスログ管理:いつ・誰が・どのデータにアクセスしたかを記録し、不正利用を防止。
- 暗号化・匿名化:個人特定が不要な分析には匿名化処理を適用し、情報漏えいリスクを低減。
- バックアップと監査:データ損失や改ざん防止のための定期バックアップ・監査対応を実施。
特に、人的資本開示や社外レポート作成では、データの信頼性と説明責任が求められます。
そのため、「いつでも正しいデータを提示できる状態」を保つことが重要です。
AI・RPA活用によるデータ収集・更新の自動化
データ分析のボトルネックになりやすいのが、「データ入力や更新の手間」です。
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用することで、この課題を大幅に解消できます。
- AI解析:評価コメントやサーベイ回答を自然言語処理で分類・スコア化。
- RPA自動処理:勤怠・給与・人事システム間でのデータ転記を自動化。
- クラウド連携:各種SaaS(勤怠・評価・採用管理ツール)をAPIで統合。
自動化によって、ヒューマンエラーや更新漏れを防ぎ、リアルタイムで最新のデータが反映されるようになります。
これにより、人事担当者は分析や戦略立案などの高付加価値業務に時間を使えるようになります。
「正確で安全、かつ継続的に更新されるデータ基盤」こそが、人事データ分析を成功に導く最重要要素です。
人事データ分析に使える代表的ツール
人事データ分析を効率的かつ正確に行うには、目的に合ったツールの選定が欠かせません。
Excelのような身近なものから、AI分析を搭載した高機能なタレントマネジメントシステムまで、選択肢は多岐にわたります。
ここでは、人事データ分析でよく利用される代表的なツールと、導入の際に確認すべきポイントを紹介します。タレントマネジメントツール
タレントマネジメントツールは、従業員のプロフィール・評価・スキル・キャリア志向などを一元的に管理できるシステムです。
人事データの集約・分析・可視化までを包括的にサポートするため、データ分析の入門として最適です。
- ツールA:顔写真ベースのUIで、組織全体の人材配置・スキルマップを直感的に把握可能。
- ツールB:評価・目標管理・1on1・人材育成を統合し、データドリブンな人事運営を実現。
- ツールC:データに基づいた人材戦略立案を支援。AIによる離職予測機能も搭載。
- ツールD:グローバル対応の大規模人事システム。多国籍企業や上場企業に導入実績多数。
これらのツールは、人材情報の一元管理+分析+レポーティングを実現し、戦略人事の基盤を構築します。
分析ツール(Excel・R・Python・JMPなど)
データ分析を手軽に始めたい場合、汎用的な分析ツールの活用がおすすめです。
特にExcelは多くの企業ですでに導入されており、初期投資なしで分析をスタートできます。
- Microsoft Excel:ピボットテーブルや条件付き書式を活用すれば、基礎的な統計分析が可能。
- R:無料の統計解析ソフト。グラフ生成や相関・回帰分析など学術レベルの分析に対応。
- Python:AI・機械学習と相性が良く、大規模データの自動分析に最適。
- JMP:SAS社が提供するビジュアル重視の統計解析ソフト。分析過程を直感的に理解できる。
初心者はまずExcelから始め、徐々にRやPythonでの高度分析へステップアップするのが効果的です。
BIツール(Tableau/Looker Studio/Power BI)
BI(Business Intelligence)ツールは、蓄積された大量のデータを可視化・共有するためのツールです。
経営層や現場が同じデータを基に議論できるようになるため、意思決定のスピードと精度が向上します。
- Tableau:直感的なドラッグ&ドロップ操作で、インタラクティブな可視化が可能。
- Looker Studio(旧Googleデータポータル):無料で利用でき、GoogleスプレッドシートやBigQueryと連携しやすい。
- Power BI:Microsoft製BIツール。Excelとの親和性が高く、社内展開が容易。
BIツールは、分析結果をグラフやダッシュボードでリアルタイムに共有できる点が大きな魅力です。
部署横断的な意思決定や経営報告にも役立ちます。ツール選定のチェックポイントと導入プロセス
ツールを導入する際は、「何を分析したいか」「誰が使うか」「どのデータを扱うか」を明確にすることが重要です。
無理に高機能なツールを導入するよりも、自社の課題に合ったスケーラブルな設計がポイントです。✔ チェックポイント
- 目的に合致した機能(例:離職分析、評価傾向分析、スキルマッピングなど)
- 既存システム(勤怠・給与・評価)の連携可否
- データのセキュリティ・アクセス権設定の柔軟性
- 操作性・UIのわかりやすさ(現場ユーザーが使えるか)
- 導入・運用コスト(初期費用+月額+サポート費)
✔ 導入プロセス
- 現状分析(課題・目的・利用データの整理)
- ツール候補の比較検討・デモ確認
- 導入スケジュール・権限設計・データ移行計画の策定
- 試験運用・フィードバック・本格導入
人事データ分析ツールは、導入して終わりではなく「運用と改善の継続」が成功のカギです。
定期的に分析結果を振り返り、組織課題の変化に応じてツールをアップデートしていきましょう。人事データ分析の成功事例と失敗パターン
人事データ分析の導入に成功している企業と、途中でつまずく企業には明確な違いがあります。
ここでは、実際の成功・失敗事例をもとに、成果を出すためのポイントを解説します。成功事例①:評価データを基に育成施策を設計した企業
A社では、全社員の評価データとスキル情報を統合し、ハイパフォーマーの行動特性を分析しました。
その結果、「早期に成果を上げる社員は、上司との1on1頻度が高い」という傾向が判明。
A社はこの分析をもとに、管理職向けの面談トレーニングや目標設定支援制度を導入しました。半年後には、中途入社社員の定着率が15%向上し、評価分布の偏りも減少。
データ分析をもとに仮説を立て、施策に反映させる好循環が生まれた成功事例です。成功事例②:退職データ分析で離職率を30%削減
B社では、過去3年間の退職者データを分析し、「評価スコア」「年齢層」「上司との関係性」「勤務時間」など複数の指標を可視化しました。
その結果、評価が高い若手社員ほど離職率が高いという意外な傾向が発見されました。原因を深掘りすると、成長意欲が高い社員ほど「昇進機会の少なさ」「給与の停滞」に不満を持っていたことが分かりました。
そこで、B社はキャリア面談制度とスキルアップ支援制度を新設。結果、翌年度には離職率が約30%減少しました。データをもとに課題を特定し、行動につなげたことが成功の決め手でした。
失敗事例①:目的不在・データ分断・担当不明確の落とし穴
一方で、C社では人事データ分析プロジェクトを立ち上げたものの、「目的を定義しないままデータを集め始めた」ことが失敗の原因となりました。
各部署が独自フォーマットでデータを保有しており、集約作業に多大な工数が発生。分析以前に、データ整備に半年以上を費やしました。さらに、分析結果を誰がどう活用するのか明確でなかったため、「報告書だけが作られて施策に反映されない」状態に。
結果として、現場の理解が進まず、分析プロジェクト自体が立ち消えになりました。このケースは、目的設定・ガバナンス・役割分担の欠如が生んだ典型的な失敗パターンといえます。
成功の鍵:仮説思考と経営層巻き込みの重要性
成功している企業に共通するのは、分析を単なるデータ処理ではなく、経営課題解決のプロセスとして位置づけている点です。
- 仮説思考:「なぜその課題が起きているのか」を仮説化し、データで検証する姿勢。
- 経営層の巻き込み:経営陣がデータ分析の意義を理解し、意思決定に活用する文化を醸成。
- 現場との連携:分析担当者と現場マネジャーが協働し、施策実行まで責任を共有。
人事データ分析は、ツール導入よりも「目的設定と文化づくり」が成功を左右します。
経営層を含む全社的な合意形成のもとで取り組むことで、データ活用が“組織の意思決定インフラ”として根付いていきます。成功の鍵は「ツール」ではなく「戦略」。
データから洞察を導き、行動を変えることこそが、人事データ分析の本質です。人事データ分析の課題と今後のトレンド
人事データ分析は多くのメリットをもたらしますが、実際の現場ではさまざまな課題にも直面します。
データの整備や運用体制の構築、プライバシー保護、属人化防止など、乗り越えるべき壁は少なくありません。
ここでは、代表的な課題と、今後のトレンド・方向性を整理します。データ整備コスト・プライバシー対応・属人化の課題
人事データ分析を継続的に運用する上で、最初に直面するのがデータ整備と管理体制の課題です。
- データ整備コスト:各部署やシステムでフォーマットが異なり、統合作業に多くの時間とコストがかかる。
- プライバシー対応:個人情報や評価データを扱うため、匿名化・アクセス制限・法令遵守が必須。
- 属人化:特定の担当者しか操作・分析できない状態になると、運用が停滞しやすい。
これらの課題を防ぐためには、データガバナンスの設計と、継続的な教育・運用ルールの明文化が重要です。
特に中小企業では、まず「集めるデータを絞り、少しずつ分析領域を広げる」段階的導入が現実的です。AIによる自動分析・人材スコアリングの進化
近年、AI技術の進化により、人事データ分析は自動化・予測型分析の時代へと進化しています。
これまで専門知識が必要だった統計分析も、AIが自動で相関関係を抽出し、予測モデルを生成できるようになりました。
- AI解析:テキストコメントを自然言語処理で分類し、エンゲージメント傾向を可視化。
- スコアリング:スキル・成果・行動データをもとに、ハイパフォーマー予測や離職リスク検知を実現。
- チャット型BI:「誰が」「どの部署で」「どんな傾向にあるか」を自然言語で検索可能。
これにより、分析担当者の負担は軽減され、現場マネジャーや経営層も直感的にデータを使いこなす時代が訪れています。
“AI×人事データ分析”は、データを「見る」から「活かす」へと進化させる原動力です。
人的資本経営との連動 ― データ活用が「価値」になる時代へ
人的資本経営(Human Capital Management)への注目が高まる中、人事データ分析は企業価値の根幹を支える要素となっています。
2023年以降、上場企業には人的資本の情報開示が義務化され、「人材の質」「育成」「多様性」「エンゲージメント」などの指標を定量的に報告する必要が生まれました。これにより、人事データは単なる内部管理指標ではなく、投資家やステークホルダーに対する信頼の証としての役割を持ち始めています。
- 人的資本KPIの設定:離職率・研修投資・女性管理職比率などの数値管理。
- 可視化レポート:ダッシュボードや人的資本レポートとして開示。
- 経営との統合:財務データと組み合わせた「人×業績」の相関分析。
今後は、人的資本経営とデータ分析を融合させた「HRデータドリブン経営」が主流になるでしょう。
データを“管理資産”から“経営資源”へと昇華させることが、企業競争力の鍵を握ります。まとめ|人事データ分析の意義とこれからの展望
人事データ分析は、単なる数値の集計ではなく、組織の未来を描くための戦略ツールです。
勤怠・評価・離職・エンゲージメントといったデータを統合的に活用することで、組織課題の「原因」と「改善策」を科学的に導き出せます。
特に、AIやBIツールの進化により、これまで専門家しか扱えなかった分析が、現場レベルでも容易に実施できるようになりました。ただし、成果を上げるには「データを集めること」ではなく、目的を明確にし、経営と現場が一体となって活用することが不可欠です。
データを“見る”から“活かす”へ。人事データ分析は、社員一人ひとりの成長を促し、企業の持続的な成長へとつなげる鍵となります。まずは自社で扱える範囲のデータから分析を始め、「小さく始めて大きく育てる」ことが成功の第一歩です。
戦略人事・人的資本経営を支える基盤として、人事データ分析の取り組みを継続的に進化させていきましょう。





 導入までの流れ
導入までの流れ







 無料体験
無料体験 資料請求
資料請求